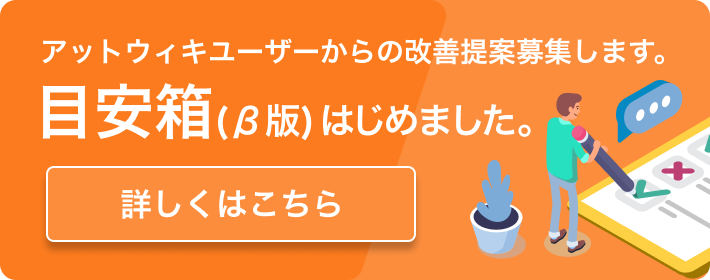「…う~もう訳わからんですぅ…」
はぁ、と大きな溜め息を吐いて、翠星石は大きく伸びをする。
「こんなんでクリスマスに間に合うですかね…」溜め息を吐きつつ翠星石は自身の手元に視線を移す。彼女の手には編み棒が握られており、周りには雑誌と毛糸玉が転がっている。
―『クリスマス』、12月になると街はクリスマス一色に変わり、誰もがその日に思いを馳せる。
特に、若いカップルたちにとってはバレンタインの次に貴重なイベントである。
聖なる一夜を愛する人と過ごしたい…そんな想いを馳せながら翠星石もクリスマスへ向けて準備をしている…が作業は難航しているようだ。
その作業というのはプレゼントの用意である。
彼女は編みかけの毛糸をじっと見つめる。
「まだここまでしか編めてないですぅ…」
力無く呟いて、青い毛糸にそっと触れる。
彼女が編んでいるのはマフラー。蒼星石へのクリスマスプレゼントだ。
今年は翠星石にとって蒼星石と恋人になってから迎える初めてのクリスマス。
…とは言っても、彼女たちの場合、恋人になる以前も今まで一緒にクリスマスを過ごして来たのだから大して変わらないかもしれない。
はぁ、と大きな溜め息を吐いて、翠星石は大きく伸びをする。
「こんなんでクリスマスに間に合うですかね…」溜め息を吐きつつ翠星石は自身の手元に視線を移す。彼女の手には編み棒が握られており、周りには雑誌と毛糸玉が転がっている。
―『クリスマス』、12月になると街はクリスマス一色に変わり、誰もがその日に思いを馳せる。
特に、若いカップルたちにとってはバレンタインの次に貴重なイベントである。
聖なる一夜を愛する人と過ごしたい…そんな想いを馳せながら翠星石もクリスマスへ向けて準備をしている…が作業は難航しているようだ。
その作業というのはプレゼントの用意である。
彼女は編みかけの毛糸をじっと見つめる。
「まだここまでしか編めてないですぅ…」
力無く呟いて、青い毛糸にそっと触れる。
彼女が編んでいるのはマフラー。蒼星石へのクリスマスプレゼントだ。
今年は翠星石にとって蒼星石と恋人になってから迎える初めてのクリスマス。
…とは言っても、彼女たちの場合、恋人になる以前も今まで一緒にクリスマスを過ごして来たのだから大して変わらないかもしれない。
けれど、せっかく「姉妹」から「恋人」という関係に変われたのだから今までとは違う夜を過ごしたい。恋人という関係になったのだと、感じたい。
デートの約束は既にしてある。
誘って来たのは蒼星石だ。否、いつもデートに誘ってくれたりするのは蒼星石の方からなのだが。お互い極度の照れ屋なため恋人になってからというもの、それまでは普通に繋いでいた手も自然に握れなくなってしまい、キスをするのも三ヶ月くらいかかった。
照れ屋にも程があるだろう。
それでも、蒼星石がいつも勇気を出して翠星石をリードする。
一方、翠星石はリードしてもらう度に、申し訳ないと思うのだがどうしても変に緊張してしまい、誘えない。
自分の意気地無さに嫌気が差していた。
けれど蒼星石はそんな翠星石を理解し、
『焦らなくていい、君がそうしたいって思った時でいいよ』
大切だから、無理やりというのは嫌なんだと言ってくれる。
だから、キス以上の関係に進むのも翠星石がOKの返事をするまでずっと蒼星石は待っており、翠星石はそのような蒼星石の言葉や心遣いにに救われ本当に蒼星石に愛されているのだと実感するのだ。
デートの約束は既にしてある。
誘って来たのは蒼星石だ。否、いつもデートに誘ってくれたりするのは蒼星石の方からなのだが。お互い極度の照れ屋なため恋人になってからというもの、それまでは普通に繋いでいた手も自然に握れなくなってしまい、キスをするのも三ヶ月くらいかかった。
照れ屋にも程があるだろう。
それでも、蒼星石がいつも勇気を出して翠星石をリードする。
一方、翠星石はリードしてもらう度に、申し訳ないと思うのだがどうしても変に緊張してしまい、誘えない。
自分の意気地無さに嫌気が差していた。
けれど蒼星石はそんな翠星石を理解し、
『焦らなくていい、君がそうしたいって思った時でいいよ』
大切だから、無理やりというのは嫌なんだと言ってくれる。
だから、キス以上の関係に進むのも翠星石がOKの返事をするまでずっと蒼星石は待っており、翠星石はそのような蒼星石の言葉や心遣いにに救われ本当に蒼星石に愛されているのだと実感するのだ。
だが、自分から誘うことも出来ない状態なのにもっと触れたいなどと思う身勝手な自分がいる。
告白も蒼星石からだった。
してもらってばかりでは駄目だ。
―だから今回は、自分から勇気を出したい。
そう意気込んで、彼女は勇気を出す第一歩としてプレゼントに手編みのマフラーを贈ることにした。
だが彼女は編み物をしたことがない初心者なのでそれは難題だ。
とりあえず編み方を知らなければお話にならないので翠星石は手芸店で本と編み棒を購入し、毛糸の色を選んだ。
何色もある中から翠星石は迷わずに青色の毛糸玉を手に取った。青色を見るだけで翠星石の脳裏に蒼星石の顔が浮かぶ。…今でもそうだ。
編みながらこの毛糸の色を見る度に常に蒼星石の顔が浮かび、恋しくなる。
まるで、恋人になる前の、誰よりも傍にいるのに想いを伝えたくてもなかなか伝えられず、もどかしく切ない思いをしていたあの頃のように…。
そこまで考えて、翠星石はその思考を振り切るようにふるふると頭を振り、大きく深呼吸をする。
「…蒼星石と恋人になってから初めてのクリスマスです…絶対何が何でも頑張るですぅ!」
ぐっと拳を握り締める。もう、あの頃とは違う。
告白も蒼星石からだった。
してもらってばかりでは駄目だ。
―だから今回は、自分から勇気を出したい。
そう意気込んで、彼女は勇気を出す第一歩としてプレゼントに手編みのマフラーを贈ることにした。
だが彼女は編み物をしたことがない初心者なのでそれは難題だ。
とりあえず編み方を知らなければお話にならないので翠星石は手芸店で本と編み棒を購入し、毛糸の色を選んだ。
何色もある中から翠星石は迷わずに青色の毛糸玉を手に取った。青色を見るだけで翠星石の脳裏に蒼星石の顔が浮かぶ。…今でもそうだ。
編みながらこの毛糸の色を見る度に常に蒼星石の顔が浮かび、恋しくなる。
まるで、恋人になる前の、誰よりも傍にいるのに想いを伝えたくてもなかなか伝えられず、もどかしく切ない思いをしていたあの頃のように…。
そこまで考えて、翠星石はその思考を振り切るようにふるふると頭を振り、大きく深呼吸をする。
「…蒼星石と恋人になってから初めてのクリスマスです…絶対何が何でも頑張るですぅ!」
ぐっと拳を握り締める。もう、あの頃とは違う。
やっと両想いになれたのだから。
間に合うかどうかなんて言っていられない。
間に合わせなければ。
料理以外の物を手作りしたことがなく、する気もなかった翠星石にとって編み物をするなど自分でも驚く程珍しいことだ。『恋をしたら女の子は無敵☆』というフレーズを耳にしたことがあるが、あながち嘘ではない。
投げ出したいと思うこともあるけれど頑張れている。沈んでいた気持ちが元に戻った翠星石は編み棒を握り、再び作業を再開した。
翠星石が熱中し始めたと同時に隣室のドアが静かに開き、微かに光が漏れるその部屋からコップを片手に蒼星石が現れた。時刻は午前12時を過ぎている。
今の時間まで蒼星石は勉強をしていたのだった。翠星石は昼型なのに対し、蒼星石は夜型なのだ。水分を取りながら勉強していた蒼星石は飲み干したコップを片付けるべく、部屋から出てキッチンへ向かう。
コップを片付け、自室に入る際にふと隣室に視線を移すとドアの隙間から明かりが漏れていることに気づく。
隣室は姉であり恋人の翠星石の部屋だ。
「…あれ?」
どうして明かりが漏れているのだろうか。
翠星石がまだ起きているのか。
しかし、翠星石は普段ならばこの時間とっくに眠っているはずだ。
間に合うかどうかなんて言っていられない。
間に合わせなければ。
料理以外の物を手作りしたことがなく、する気もなかった翠星石にとって編み物をするなど自分でも驚く程珍しいことだ。『恋をしたら女の子は無敵☆』というフレーズを耳にしたことがあるが、あながち嘘ではない。
投げ出したいと思うこともあるけれど頑張れている。沈んでいた気持ちが元に戻った翠星石は編み棒を握り、再び作業を再開した。
翠星石が熱中し始めたと同時に隣室のドアが静かに開き、微かに光が漏れるその部屋からコップを片手に蒼星石が現れた。時刻は午前12時を過ぎている。
今の時間まで蒼星石は勉強をしていたのだった。翠星石は昼型なのに対し、蒼星石は夜型なのだ。水分を取りながら勉強していた蒼星石は飲み干したコップを片付けるべく、部屋から出てキッチンへ向かう。
コップを片付け、自室に入る際にふと隣室に視線を移すとドアの隙間から明かりが漏れていることに気づく。
隣室は姉であり恋人の翠星石の部屋だ。
「…あれ?」
どうして明かりが漏れているのだろうか。
翠星石がまだ起きているのか。
しかし、翠星石は普段ならばこの時間とっくに眠っているはずだ。
自分と同じように勉強しているのだろうか。
否、彼女は昼型だ。
宿題などは日が明るい内に片付けてしまう彼女が夜にやるなどないに等しいのだが。
「…まあ、いいか」
もしかしたら何かやり残した課題などがあったのかもしれない。
彼女のことだ、ありそうである。
そう考えて些か疑問を持ちつつも自分なりに解釈し、蒼星石は静かに自室へ戻って行った。
否、彼女は昼型だ。
宿題などは日が明るい内に片付けてしまう彼女が夜にやるなどないに等しいのだが。
「…まあ、いいか」
もしかしたら何かやり残した課題などがあったのかもしれない。
彼女のことだ、ありそうである。
そう考えて些か疑問を持ちつつも自分なりに解釈し、蒼星石は静かに自室へ戻って行った。
―*―*―*―*―*―
「えっと…ここがこうなって…」
翌日、翠星石は昼休みに学校の被服室で編み物の続きをしていた。
本当は教室でやりたかったのだが、教室には蒼星石がいる。
蒼星石とは同じクラスで、席は自分の斜め後ろだ。
普段なら嬉しいと思えるのだが、マフラーを編んでいることを秘密にしたい翠星石にとってこういう時困ってしまう。
今まではそういうことに配慮し、家でだけやっていたが編み物初心者の彼女にとっては簡単ではなく、時間を有する。
家でやっているだけではとても間に合わない。
なので最終手段として被服室を借りることにしたのだ。
(いつもならこんな天気のいい日の昼休みは蒼星石と前庭でお弁当食べるですのに…)
「えっと…ここがこうなって…」
翌日、翠星石は昼休みに学校の被服室で編み物の続きをしていた。
本当は教室でやりたかったのだが、教室には蒼星石がいる。
蒼星石とは同じクラスで、席は自分の斜め後ろだ。
普段なら嬉しいと思えるのだが、マフラーを編んでいることを秘密にしたい翠星石にとってこういう時困ってしまう。
今まではそういうことに配慮し、家でだけやっていたが編み物初心者の彼女にとっては簡単ではなく、時間を有する。
家でやっているだけではとても間に合わない。
なので最終手段として被服室を借りることにしたのだ。
(いつもならこんな天気のいい日の昼休みは蒼星石と前庭でお弁当食べるですのに…)
時折、蒼星石は部活のミーティングに行ってしまうことはあるけれど、それ以外はほとんど共に過ごしている。
そう考えると自分にとって蒼星石と共にいる時間は本当に多いのだと改めて実感する。
「…これから二週間は一緒に過ごせない日々が続くですぅ…ごめんなさいです…蒼星石…」
その頃、教室では案の定蒼星石が翠星石を探していた。
「…翠星石どこ行ったんだろう?」
いつもなら一緒に前庭に行くというのに。
先に行っていると思い、前庭に行って見たが居らず、では教室かと戻ってみても居ない。
(何か用事があって居ないのかもしれないし…)昨夜と同じように解釈し、蒼星石は仕方なく席に着いた。
しかし、翌日もその翌日も翠星石は昼休みになると姿を消し、家に帰ってもすぐに自室へこもり、夜は彼女の部屋から明かりが漏れていた。
ある日、気になった蒼星石は真紅に尋ねた。
「…真紅、最近翠星石が昼休みになると居なくなるんだけど何か知らないかい?」
「さあ…私は何も聞いていないけれど」
「…そうか。ありがとう」
真紅も知らないようだ。では一時的なものかと再び解釈した蒼星石だったがそれからも翠星石が教室にいない日々は続く。
そう考えると自分にとって蒼星石と共にいる時間は本当に多いのだと改めて実感する。
「…これから二週間は一緒に過ごせない日々が続くですぅ…ごめんなさいです…蒼星石…」
その頃、教室では案の定蒼星石が翠星石を探していた。
「…翠星石どこ行ったんだろう?」
いつもなら一緒に前庭に行くというのに。
先に行っていると思い、前庭に行って見たが居らず、では教室かと戻ってみても居ない。
(何か用事があって居ないのかもしれないし…)昨夜と同じように解釈し、蒼星石は仕方なく席に着いた。
しかし、翌日もその翌日も翠星石は昼休みになると姿を消し、家に帰ってもすぐに自室へこもり、夜は彼女の部屋から明かりが漏れていた。
ある日、気になった蒼星石は真紅に尋ねた。
「…真紅、最近翠星石が昼休みになると居なくなるんだけど何か知らないかい?」
「さあ…私は何も聞いていないけれど」
「…そうか。ありがとう」
真紅も知らないようだ。では一時的なものかと再び解釈した蒼星石だったがそれからも翠星石が教室にいない日々は続く。
再度、真紅に尋ねてみたが「わからない」と返され、今度は本人に尋ねてみたが翠星石は「何でもない」と返すだけだ。
本人がそう言うのなら…と納得したものの、彼女が昼休みに姿を消す日々は続き、昼休みだけならまだしも毎晩部屋のドアから漏れる光が夜更かししていることを物語っていた。
「……おかしい」
おかしすぎる。
最初はいくら姉といえど、翠星石にもプライベートがあるのだと自分に言い聞かせていた蒼星石だったが、さすがにそうは思えなくなって来た。
現に翠星石は授業中もずっと欠伸を繰り返し、眠そうにしている。
時にはうたた寝をしそうになって、それでも起きようと睡魔と戦っている。
そして、今日も翠星石は4限目の授業が終わるとすぐに弁当と鞄を持ってどこかへ行こうとする。とうとう痺れを切らした蒼星石は立ち上がり、教室の出口へ向かおうとする翠星石の腕を掴んだ。「 !? …蒼星石!?」「…どこへ行くんだい?翠星石」
「…え…?」
「どこへ、行くんだい?」
蒼星石は腕を掴んだまま、真剣な眼差しで翠星石を見つめる。
有無を言わさないような、鋭さを伴う眼差しだった。
一方翠星石は突然のことに驚き、顔が真っ青になる。
「…えっと……」
「……最近、昼休みになると必ず居なくなるよね?」
「う……」
「…どうして最近教室から居なくなるんだい?
…どこで何をしてるの?」
蒼星石の問い掛けに翠星石は口を開こうとするが言葉は出ない。
「…翠星石、僕は責めてるんじゃない。
ただ…最近君の様子が変だから心配してるだけなんだ。…心配だから理由を知りたい、それだけなんだ」
それを聞いた翠星石の肩がピクリと震える。
蒼星石は翠星石の返答を待つが翠星石は眉根を寄せ、口を閉じたり開いたりするだけだ。
「……どうして答えない?」
蒼星石は気が長い方だが、言い澱む翠星石の様子に次第に苛立ちを覚え、声音が硬くなる。
(ど、どうしましょう…なんて答えれば…)
言いたい、けれど今言う訳にはいかない。困惑する翠星石を見兼ねた蒼星石は溜め息を吐き、静かに口を開いた。
「……わかったよ。
こんなに聞いても答えてくれないってことは僕にも言えないことなんだ?」
「 ! …それは…!」
「……もう、いいよ。
引き止めてごめん」
「蒼星石…!」
抑揚のない声音で翠星石にそう告げて掴んでいた腕を離し、蒼星石は踵を返して静かに自席へと戻って行く。
翠星石はその背に声をかけることはしなかった。否、出来なかった。
本人がそう言うのなら…と納得したものの、彼女が昼休みに姿を消す日々は続き、昼休みだけならまだしも毎晩部屋のドアから漏れる光が夜更かししていることを物語っていた。
「……おかしい」
おかしすぎる。
最初はいくら姉といえど、翠星石にもプライベートがあるのだと自分に言い聞かせていた蒼星石だったが、さすがにそうは思えなくなって来た。
現に翠星石は授業中もずっと欠伸を繰り返し、眠そうにしている。
時にはうたた寝をしそうになって、それでも起きようと睡魔と戦っている。
そして、今日も翠星石は4限目の授業が終わるとすぐに弁当と鞄を持ってどこかへ行こうとする。とうとう痺れを切らした蒼星石は立ち上がり、教室の出口へ向かおうとする翠星石の腕を掴んだ。「 !? …蒼星石!?」「…どこへ行くんだい?翠星石」
「…え…?」
「どこへ、行くんだい?」
蒼星石は腕を掴んだまま、真剣な眼差しで翠星石を見つめる。
有無を言わさないような、鋭さを伴う眼差しだった。
一方翠星石は突然のことに驚き、顔が真っ青になる。
「…えっと……」
「……最近、昼休みになると必ず居なくなるよね?」
「う……」
「…どうして最近教室から居なくなるんだい?
…どこで何をしてるの?」
蒼星石の問い掛けに翠星石は口を開こうとするが言葉は出ない。
「…翠星石、僕は責めてるんじゃない。
ただ…最近君の様子が変だから心配してるだけなんだ。…心配だから理由を知りたい、それだけなんだ」
それを聞いた翠星石の肩がピクリと震える。
蒼星石は翠星石の返答を待つが翠星石は眉根を寄せ、口を閉じたり開いたりするだけだ。
「……どうして答えない?」
蒼星石は気が長い方だが、言い澱む翠星石の様子に次第に苛立ちを覚え、声音が硬くなる。
(ど、どうしましょう…なんて答えれば…)
言いたい、けれど今言う訳にはいかない。困惑する翠星石を見兼ねた蒼星石は溜め息を吐き、静かに口を開いた。
「……わかったよ。
こんなに聞いても答えてくれないってことは僕にも言えないことなんだ?」
「 ! …それは…!」
「……もう、いいよ。
引き止めてごめん」
「蒼星石…!」
抑揚のない声音で翠星石にそう告げて掴んでいた腕を離し、蒼星石は踵を返して静かに自席へと戻って行く。
翠星石はその背に声をかけることはしなかった。否、出来なかった。
(蒼星石が…怒ってるです…)
自席に戻った蒼星石は机から本を取り出し、何事もなかったかのように本を開く。端から見ればいつもと変わらない。
けれど、翠星石にはわかる。蒼星石が怒っているということが。
「……っ」
暫し、その場に立ち尽くす。翠星石はちらりと蒼星石を見遣り、やがて彼女も静かに教室を出て行った。
翠星石が教室を出て行くと蒼星石は本から視線を翠星石が出て行った方へと移した。
(…なんで…!)
何故、何も答えないのか。そんなに知られたくないことがあるのか。
「蒼星石」
名前を呼ばれ、ふと顔を上げれば目の前に真紅が立っている。
「…真紅…何か用かい?」
「…その…」
「…さっきのこと見てたんだろう?別に何ともないから」
「…翠星石のこと、怒っているの?」
その言葉にドクンと蒼星石の心臓が跳ねた。
「……別に。僕は…ただ心配なだけだ。最近、昼休みには居なくなるし授業中はずっと眠そうにしてるから。
…でも、余計なお世話だったようだ」
心配だった。プライベートがあることは重々承知している。だからそれに対して怒っている訳ではない。
しかし、翠星石本人に自覚はないかもしれないが、疲れた顔をしている。きっと睡眠不足が原因だ。
自席に戻った蒼星石は机から本を取り出し、何事もなかったかのように本を開く。端から見ればいつもと変わらない。
けれど、翠星石にはわかる。蒼星石が怒っているということが。
「……っ」
暫し、その場に立ち尽くす。翠星石はちらりと蒼星石を見遣り、やがて彼女も静かに教室を出て行った。
翠星石が教室を出て行くと蒼星石は本から視線を翠星石が出て行った方へと移した。
(…なんで…!)
何故、何も答えないのか。そんなに知られたくないことがあるのか。
「蒼星石」
名前を呼ばれ、ふと顔を上げれば目の前に真紅が立っている。
「…真紅…何か用かい?」
「…その…」
「…さっきのこと見てたんだろう?別に何ともないから」
「…翠星石のこと、怒っているの?」
その言葉にドクンと蒼星石の心臓が跳ねた。
「……別に。僕は…ただ心配なだけだ。最近、昼休みには居なくなるし授業中はずっと眠そうにしてるから。
…でも、余計なお世話だったようだ」
心配だった。プライベートがあることは重々承知している。だからそれに対して怒っている訳ではない。
しかし、翠星石本人に自覚はないかもしれないが、疲れた顔をしている。きっと睡眠不足が原因だ。
翠星石が蒼星石のことを見抜けるように、蒼星石も翠星石のことを見抜ける。
だからどんなに翠星石がいつも通りに振る舞ったとて、蒼星石には通じない。それでも翠星石は何でもないと無理をして笑う。それが、見ていられなかった。
「そんなことないわ、翠星石だって貴方が心配していることちゃんとわかっているわ。
ただ…今は貴方にも伝えられないことがあるのよ」
その言葉に、蒼星石は違和感を感じた。
まるで、知っているような口ぶりだ。
「…随分わかったようなことを言うね。
…もしかして…君は翠星石が隠していることを知っているのか?」
目の前の真紅を見据え、問いただす。
問われた真紅はその問いに少々言い澱んだものの、頷いた。
「…ええ。翠星石に口止めされていたの」
「 ! そう…知ってたのか…。道理でね…なんとなくそうなんじゃないかと思ってはいたよ」
「ごめんなさい…」
いつも通りの冷静な声音の中に微かな怒りが滲んでいることに真紅は気づく。
蒼星石は掠れた声で続ける。
「……なんで…君が知ってる?なんで君まで知ってるのに僕には教えてくれないんだ!?なんで…心配もさせてくれない?翠星石は…僕のことが嫌いなのか…?」
だからどんなに翠星石がいつも通りに振る舞ったとて、蒼星石には通じない。それでも翠星石は何でもないと無理をして笑う。それが、見ていられなかった。
「そんなことないわ、翠星石だって貴方が心配していることちゃんとわかっているわ。
ただ…今は貴方にも伝えられないことがあるのよ」
その言葉に、蒼星石は違和感を感じた。
まるで、知っているような口ぶりだ。
「…随分わかったようなことを言うね。
…もしかして…君は翠星石が隠していることを知っているのか?」
目の前の真紅を見据え、問いただす。
問われた真紅はその問いに少々言い澱んだものの、頷いた。
「…ええ。翠星石に口止めされていたの」
「 ! そう…知ってたのか…。道理でね…なんとなくそうなんじゃないかと思ってはいたよ」
「ごめんなさい…」
いつも通りの冷静な声音の中に微かな怒りが滲んでいることに真紅は気づく。
蒼星石は掠れた声で続ける。
「……なんで…君が知ってる?なんで君まで知ってるのに僕には教えてくれないんだ!?なんで…心配もさせてくれない?翠星石は…僕のことが嫌いなのか…?」
「蒼星石、翠星石を怒らないであげて頂戴。
あの子が貴方を嫌うはずないわ。あの子は貴方が大好きだもの」
「だったらなんで…!」「大好きだけど今は言えないのよ。どんなに互いを想い合っていても、そういう時があるのよ。
蒼星石、貴方は翠星石を愛しているのでしょう?大切なのでしょう?」
「……当たり前だよ」
「だったら、彼女を信じなさい。
大丈夫、もうすぐわかるわ」
真紅はそう言って微笑むと廊下へ出て行った。
「どうすればいいですか…」
どんよりとしたオーラを纏い、翠星石は被服室に篭って編み物の続きをしていた。しかし、手は動いているものの頭の中は上の空だ。
「どうして編み物くらいでこんなことに…」
クリスマスのプレゼントを用意しているだけなのに何故、よりによって贈る相手と険悪な雰囲気にならなければいけないのか。
「…こんなことになるなら…最初から秘密になんてしなければ良かったですぅ…」
秘密にしようとしたのが悪かったのか。
ただ、驚かせたかっただけだというのに。
それが返って裏目に出てしまった。
「翠星石のせいで…蒼星石を怒らせちゃったですぅ…。このままじゃ…クリスマスどころか嫌われちゃうですぅ…」
あの子が貴方を嫌うはずないわ。あの子は貴方が大好きだもの」
「だったらなんで…!」「大好きだけど今は言えないのよ。どんなに互いを想い合っていても、そういう時があるのよ。
蒼星石、貴方は翠星石を愛しているのでしょう?大切なのでしょう?」
「……当たり前だよ」
「だったら、彼女を信じなさい。
大丈夫、もうすぐわかるわ」
真紅はそう言って微笑むと廊下へ出て行った。
「どうすればいいですか…」
どんよりとしたオーラを纏い、翠星石は被服室に篭って編み物の続きをしていた。しかし、手は動いているものの頭の中は上の空だ。
「どうして編み物くらいでこんなことに…」
クリスマスのプレゼントを用意しているだけなのに何故、よりによって贈る相手と険悪な雰囲気にならなければいけないのか。
「…こんなことになるなら…最初から秘密になんてしなければ良かったですぅ…」
秘密にしようとしたのが悪かったのか。
ただ、驚かせたかっただけだというのに。
それが返って裏目に出てしまった。
「翠星石のせいで…蒼星石を怒らせちゃったですぅ…。このままじゃ…クリスマスどころか嫌われちゃうですぅ…」
力無く呟いて翠星石は机に突っ伏する。
このままではクリスマスを迎える前に別れ話になってしまう。じわじわと視界が滲んでくる。
滲んだ視界には青色の毛糸が映る。
蒼星石は本気で怒っていた。彼女が怒ることなど滅多にないというのに。もし本当に別れ話になってしまったらこのマフラーが存在する意味はなくなってしまう。
どうせ嫌われて貰って貰えなくなるならいっそのこと投げ出してしまおうか…そう思った時、被服室のドアが開いた。
翠星石の心臓が跳ねる。「翠星石、大丈夫?」
入って来たのは真紅だった。
「真…紅…」
「さっきのことがあったから様子を見に来たのだけれど…って翠星石!?泣いているの!?」
「な…泣いてなんかねぇです…泣いて…なん…か…」
駆け寄って来る真紅に言葉を返そうとしても翠星石の瞳からは涙が溢れるだけだ。
「翠星石、落ち着いて」「蒼星石を…おこ…怒らせちまった…です…ぅ!嫌われちゃっ…たですぅ!」
「何を言っているの。
こんなことくらいで蒼星石が貴方を嫌いになるはずがないでしょう。
それに、蒼星石のことは一応私がなんとかしておいたから大丈夫よ」
その言葉に翠星石は目を瞠る。
「ふぇ…?なんとか?」
「ええ、大丈夫…と言っても多分だけれど。
とりあえず、貴方が蒼星石にどうしても言えない理由があるということだけは伝えたわ。
マフラーのことは一切話してないから安心して頂戴」
真紅が宥めるようにそう言うと翠星石は俯いた。何か気に障るようなことを言ったのかと心配になった真紅が声をかけようとすると、やがて翠星石が言葉を発した。
「真紅…私は…間違っているですか?」
「間違う…?」
「私は…ただ驚かせたかっただけなんです…。
それなのに蒼星石を怒らせるわ、真紅には迷惑かけるわで…最悪ですぅ…」
「間違ってなんかいないのだわ。
貴方は大切な人を喜ばせようとしただけだもの」「でも…」
「私に迷惑をかけて悪いと思うなら、必ずマフラーを完成させて頂戴。
でなければ蒼星石の怒りを買うことを承知で話した私の立場がないわ」
「真紅…」
机上の編みかけのマフラーを見遣り、手に取ると真紅は翠星石にそれを手渡す。
「あともう少しじゃないの。初心者なのにここまで編めるなんて尊敬するわ。
せっかく頑張ったんだもの、必ず渡しなさいな」「…真紅…ありがとうです」
翠星石は礼を言い、そっとマフラーを受け取った。
このままではクリスマスを迎える前に別れ話になってしまう。じわじわと視界が滲んでくる。
滲んだ視界には青色の毛糸が映る。
蒼星石は本気で怒っていた。彼女が怒ることなど滅多にないというのに。もし本当に別れ話になってしまったらこのマフラーが存在する意味はなくなってしまう。
どうせ嫌われて貰って貰えなくなるならいっそのこと投げ出してしまおうか…そう思った時、被服室のドアが開いた。
翠星石の心臓が跳ねる。「翠星石、大丈夫?」
入って来たのは真紅だった。
「真…紅…」
「さっきのことがあったから様子を見に来たのだけれど…って翠星石!?泣いているの!?」
「な…泣いてなんかねぇです…泣いて…なん…か…」
駆け寄って来る真紅に言葉を返そうとしても翠星石の瞳からは涙が溢れるだけだ。
「翠星石、落ち着いて」「蒼星石を…おこ…怒らせちまった…です…ぅ!嫌われちゃっ…たですぅ!」
「何を言っているの。
こんなことくらいで蒼星石が貴方を嫌いになるはずがないでしょう。
それに、蒼星石のことは一応私がなんとかしておいたから大丈夫よ」
その言葉に翠星石は目を瞠る。
「ふぇ…?なんとか?」
「ええ、大丈夫…と言っても多分だけれど。
とりあえず、貴方が蒼星石にどうしても言えない理由があるということだけは伝えたわ。
マフラーのことは一切話してないから安心して頂戴」
真紅が宥めるようにそう言うと翠星石は俯いた。何か気に障るようなことを言ったのかと心配になった真紅が声をかけようとすると、やがて翠星石が言葉を発した。
「真紅…私は…間違っているですか?」
「間違う…?」
「私は…ただ驚かせたかっただけなんです…。
それなのに蒼星石を怒らせるわ、真紅には迷惑かけるわで…最悪ですぅ…」
「間違ってなんかいないのだわ。
貴方は大切な人を喜ばせようとしただけだもの」「でも…」
「私に迷惑をかけて悪いと思うなら、必ずマフラーを完成させて頂戴。
でなければ蒼星石の怒りを買うことを承知で話した私の立場がないわ」
「真紅…」
机上の編みかけのマフラーを見遣り、手に取ると真紅は翠星石にそれを手渡す。
「あともう少しじゃないの。初心者なのにここまで編めるなんて尊敬するわ。
せっかく頑張ったんだもの、必ず渡しなさいな」「…真紅…ありがとうです」
翠星石は礼を言い、そっとマフラーを受け取った。
その夜、翠星石は蒼星石の部屋の前に立っていた。帰宅してからも夕食の時も蒼星石の態度は素っ気なく、早々と自室へ向かってしまった。
きっと怒っているのだ。あの瞳を思い出すと、足がすくんでしまう。
(だけど…謝らなくちゃですぅ…)
部屋の前に立つだけで心臓が早鐘を打つ。
深呼吸をして、翠星石はドアをノックする。
「…蒼星石?起きてるですか?」
「………」
返事はない。怯みそうになるのを堪え、翠星石は静かに口を開いた。
「話したくないなら構わないです…だけど、どうしても伝えたいことがあるです。独り言だと思ってもいいから…聞いて下さい」
震える気持ちを宥めながら翠星石は口を開く。
「蒼星石…その…昼間はごめんなさいです…。
昼間だけじゃないですね…心配かけて…ごめんなさい。貴方が心配してくれていること知っていたのに隠し事して…それでも話せなくて…本当にごめんなさい」
「………」
「でも、でもね…貴方が嫌いだからとかそんな理由で隠し事してるんじゃないんです…。
本当の本当に、大したことじゃないんですけど今は…言えないんです。
だけどもうすぐ言えますから信じて下さい…私は貴方が大好きです。
だから…お願い…嫌いにならないで…」
きっと怒っているのだ。あの瞳を思い出すと、足がすくんでしまう。
(だけど…謝らなくちゃですぅ…)
部屋の前に立つだけで心臓が早鐘を打つ。
深呼吸をして、翠星石はドアをノックする。
「…蒼星石?起きてるですか?」
「………」
返事はない。怯みそうになるのを堪え、翠星石は静かに口を開いた。
「話したくないなら構わないです…だけど、どうしても伝えたいことがあるです。独り言だと思ってもいいから…聞いて下さい」
震える気持ちを宥めながら翠星石は口を開く。
「蒼星石…その…昼間はごめんなさいです…。
昼間だけじゃないですね…心配かけて…ごめんなさい。貴方が心配してくれていること知っていたのに隠し事して…それでも話せなくて…本当にごめんなさい」
「………」
「でも、でもね…貴方が嫌いだからとかそんな理由で隠し事してるんじゃないんです…。
本当の本当に、大したことじゃないんですけど今は…言えないんです。
だけどもうすぐ言えますから信じて下さい…私は貴方が大好きです。
だから…お願い…嫌いにならないで…」
(…だめ…また泣いちゃいそうですぅ…)
声が震え、嗚咽に変わる。止まらなくなりそうなので翠星石が早々と蒼星石の部屋の前から離れようと背を向けたその時部屋のドアが開き、蒼星石が現れ、翠星石の腕を捕み、抱き寄せた。
「 !? そう…せ…?」「…ごめん…ごめん翠星石…っ」
翠星石を抱きしめる蒼星石の腕に力がこもる。
突然抱きしめられた翠星石は驚いて涙で濡れた瞳を見開く。
「…わかってるよ。
君がそんなつもりじゃなかったってこと…わかってた。わかってたのに…。心配だからなんて言ったけど…本当は…寂しかったんだ…」
わかっていた。彼女がそのようなことをするはずがないということを。
しかし、いつも隣にいる翠星石が傍に居ないことが嫌だった。
一人になって改めて、痛い程彼女の存在が自分にとって大きいことに気づいた。
「…蒼星石…本当に…ごめんなさいです…」
先のことばかりで、一番身近にいる蒼星石の気持ちを考えていなかった。彼女は自分のどんな些細な変化でも見逃すはずがないというのに。
「…君が謝ることないよ。僕が悪かった。
君を困らせて…。でも、もう平気だから。
…信じてるよ。大切だから…君のことを愛してるから」
声が震え、嗚咽に変わる。止まらなくなりそうなので翠星石が早々と蒼星石の部屋の前から離れようと背を向けたその時部屋のドアが開き、蒼星石が現れ、翠星石の腕を捕み、抱き寄せた。
「 !? そう…せ…?」「…ごめん…ごめん翠星石…っ」
翠星石を抱きしめる蒼星石の腕に力がこもる。
突然抱きしめられた翠星石は驚いて涙で濡れた瞳を見開く。
「…わかってるよ。
君がそんなつもりじゃなかったってこと…わかってた。わかってたのに…。心配だからなんて言ったけど…本当は…寂しかったんだ…」
わかっていた。彼女がそのようなことをするはずがないということを。
しかし、いつも隣にいる翠星石が傍に居ないことが嫌だった。
一人になって改めて、痛い程彼女の存在が自分にとって大きいことに気づいた。
「…蒼星石…本当に…ごめんなさいです…」
先のことばかりで、一番身近にいる蒼星石の気持ちを考えていなかった。彼女は自分のどんな些細な変化でも見逃すはずがないというのに。
「…君が謝ることないよ。僕が悪かった。
君を困らせて…。でも、もう平気だから。
…信じてるよ。大切だから…君のことを愛してるから」
「嫌いに…なってないですか…?」
不安げに翠星石が蒼星石を見つめる。
それに対し、蒼星石はふっと笑う。
「馬鹿だな…こんなことくらいで嫌いになる訳ないじゃないか…なれる訳がないよ…」
「ありがと…です…」
「クリスマスのデート…行ける?」
「もちろんですよ」
「良かった」
こうして蒼星石と和解することが出来た翠星石はそれからも編み物を続け、ようやくマフラーを完成させることが出来た。「やっと…やっと出来たですぅ!」
完成したマフラーを目の前に翠星石はバンザイのポーズをする。
「長かったです…本当に…」
マフラーを手にとり、胸に抱く。一つのマフラー制作に色々なことがあったけれど完成させることが出来た。
明日はイヴ、デートの日だ。努力が功を奏す時。翠星石にとって勇気を出す時だ。
「後は、あの言葉を伝えるだけ…ですね」
不安げに翠星石が蒼星石を見つめる。
それに対し、蒼星石はふっと笑う。
「馬鹿だな…こんなことくらいで嫌いになる訳ないじゃないか…なれる訳がないよ…」
「ありがと…です…」
「クリスマスのデート…行ける?」
「もちろんですよ」
「良かった」
こうして蒼星石と和解することが出来た翠星石はそれからも編み物を続け、ようやくマフラーを完成させることが出来た。「やっと…やっと出来たですぅ!」
完成したマフラーを目の前に翠星石はバンザイのポーズをする。
「長かったです…本当に…」
マフラーを手にとり、胸に抱く。一つのマフラー制作に色々なことがあったけれど完成させることが出来た。
明日はイヴ、デートの日だ。努力が功を奏す時。翠星石にとって勇気を出す時だ。
「後は、あの言葉を伝えるだけ…ですね」
―*―*―*―*―
クリスマスイヴ当日。
待ちに待ったデートの日。道を行き来するカップルたちに紛れながら翠星石と蒼星石は駅前のイルミネーションを見て回っていた。
これは二人にとって毎年恒例になっている。
「綺麗ですねー!
さすが駅前のイルミネーション、毎年グレードアップしてるですぅ!」
クリスマスイヴ当日。
待ちに待ったデートの日。道を行き来するカップルたちに紛れながら翠星石と蒼星石は駅前のイルミネーションを見て回っていた。
これは二人にとって毎年恒例になっている。
「綺麗ですねー!
さすが駅前のイルミネーション、毎年グレードアップしてるですぅ!」
「そうだね…。翠星石、あのツリーの下行ってみようよ」
駅前の中心に立っている輝く巨大ツリーを指差し、蒼星石が翠星石の手を握る。
(あ…////)
何気ないその行為に胸が高鳴る。
落ち着かなければ。どうしても先程から蒼星石を意識してしまう。
蒼星石はそれには気づかず翠星石をツリーの下に誘導する。
「綺麗だね」
「は、はい!そうですね…」
ツリーを見上げる蒼星石の横顔をちらりと見遣る。
辺りはすっかり暗くなっており周りもカップルだらけ、もうそろそろプレゼントを渡してもいい頃だ。
―渡すのならば、今がチャンス!
「そ、蒼星石!」
「うん?何、翠星石」
蒼星石がツリーから翠星石に視線を移す。
(うっ…////)
見つめられて、ただでさえ落ち着きのなかった心臓が早鐘を打つ。
こんな感覚、蒼星石に告白された時以来だ。
プレゼントなんて毎年渡しているというのに渡すだけでこんなに緊張するとは思ってもいなかった。
「翠星石?」
「あ…えっとですね…その……こっこれ!」
勢いよく蒼星石の目の前に緑色のリボンが付いた水色の包みを差し出す。「…これは…?」
「ぷ…プレゼントです。クリスマスの…////」
「! …僕に?」
「そ、そうです!」
「…ありがとう////…開けてもいい?」
その問いかけにコクリと頷く。それを認め、蒼星石が包みを開け始める。どんな反応をするだろうか、喜んでくれるだろうか。
ドキドキしながら蒼星石の様子を見る。
包みが完全に解かれた。「…わあ…!」
現れたそれに、蒼星石が感嘆の声を挙げる。
現れたのは青色の手編みのマフラー。
「これ…翠星石が作ったのかい?」
「ですぅ。その…初めてですから上手くないですけど…」
「そんなことない。
すごいよ…!手編みなんて……あ…!もしかして…翠星石が隠してた事って…」
「…マフラーのことです。当日まで秘密にしたくて…」
「…これのこと…だったのか。ん?……てことは僕はすごい勘違いを…!」
真実を理解した蒼星石の顔が赤く染まる。
翠星石は自分のためにプレゼントを用意してくれていただけ。それなのに自分は何やら一人で誤解して騒いでいた…と考えると恥ずかしすぎる。
「…~~っ////」
「蒼星石…ごめんなさいですぅ!大したことじゃないのに大ごとにしちゃって…」
「いや…翠星石は悪くないよ。…ごめん、一人で勘違いしてて…マフラーありがとう。
…すごく嬉しいよ////」嬉しそうに微笑んで蒼星石はマフラーを自分の首に巻く。
駅前の中心に立っている輝く巨大ツリーを指差し、蒼星石が翠星石の手を握る。
(あ…////)
何気ないその行為に胸が高鳴る。
落ち着かなければ。どうしても先程から蒼星石を意識してしまう。
蒼星石はそれには気づかず翠星石をツリーの下に誘導する。
「綺麗だね」
「は、はい!そうですね…」
ツリーを見上げる蒼星石の横顔をちらりと見遣る。
辺りはすっかり暗くなっており周りもカップルだらけ、もうそろそろプレゼントを渡してもいい頃だ。
―渡すのならば、今がチャンス!
「そ、蒼星石!」
「うん?何、翠星石」
蒼星石がツリーから翠星石に視線を移す。
(うっ…////)
見つめられて、ただでさえ落ち着きのなかった心臓が早鐘を打つ。
こんな感覚、蒼星石に告白された時以来だ。
プレゼントなんて毎年渡しているというのに渡すだけでこんなに緊張するとは思ってもいなかった。
「翠星石?」
「あ…えっとですね…その……こっこれ!」
勢いよく蒼星石の目の前に緑色のリボンが付いた水色の包みを差し出す。「…これは…?」
「ぷ…プレゼントです。クリスマスの…////」
「! …僕に?」
「そ、そうです!」
「…ありがとう////…開けてもいい?」
その問いかけにコクリと頷く。それを認め、蒼星石が包みを開け始める。どんな反応をするだろうか、喜んでくれるだろうか。
ドキドキしながら蒼星石の様子を見る。
包みが完全に解かれた。「…わあ…!」
現れたそれに、蒼星石が感嘆の声を挙げる。
現れたのは青色の手編みのマフラー。
「これ…翠星石が作ったのかい?」
「ですぅ。その…初めてですから上手くないですけど…」
「そんなことない。
すごいよ…!手編みなんて……あ…!もしかして…翠星石が隠してた事って…」
「…マフラーのことです。当日まで秘密にしたくて…」
「…これのこと…だったのか。ん?……てことは僕はすごい勘違いを…!」
真実を理解した蒼星石の顔が赤く染まる。
翠星石は自分のためにプレゼントを用意してくれていただけ。それなのに自分は何やら一人で誤解して騒いでいた…と考えると恥ずかしすぎる。
「…~~っ////」
「蒼星石…ごめんなさいですぅ!大したことじゃないのに大ごとにしちゃって…」
「いや…翠星石は悪くないよ。…ごめん、一人で勘違いしてて…マフラーありがとう。
…すごく嬉しいよ////」嬉しそうに微笑んで蒼星石はマフラーを自分の首に巻く。
「暖かい…。似合う?」「もちろんですよ!翠星石が作ったんですから似合うに決まってますぅ」翠星石は嬉しそうに笑う。喜んで貰えて良かった。
「ねえ、翠星石。
…僕からもプレゼント」「え…?」
「目、閉じて」
「 ? こうですか?」
「…そう、そのまま…」耳元で囁いて、蒼星石が目を閉じたままの翠星石の唇に自分の唇を重ねる。
(え…!?)
唇に触れた温かく柔らかい感触。それがキスだと気づくのに多少時間がかかった。そして左手にも温もりを感じる。
「…もう、目を開けていいよ」
その声にゆっくりと瞼を開く。目の前には頬を赤く染めた蒼星石の顔。
顔が熱くなるのを感じながら自分の左手に違和感を感じて視線を移す。
「え!?これ…!」
左手の薬指にはエメラルドの石が付いた銀色の指輪が光っている。
「…僕からのクリスマスプレゼント。
エンゲージリングの代わり…ずっと一緒にいる証」
照れ臭そうに蒼星石が付け加える。
「…ありがとうです…蒼星石…////」
どうしよう、すごく嬉しい。翠星石は嬉しそうに自分の左手を見つめ、右手で包むようにする。
が、幸せの余韻に浸ろうとしたその時、ある事を思い出した。
「じゃ…翠星石、そろそろ歩く?」
「あ…待つです!」
「 ? どうしたの?」
翠星石はじっと蒼星石を見る。まだ終わっていない、言わなければ、あの「言葉」を。
(ゆ、勇気を…出すですよ!翠星石!)
瞬間、翠星石は蒼星石の頬を両手で包み…そっと唇を重ねた。
そして唇をした後、耳元に囁きゆっくりと離れる。直後、蒼星石の瞳が大きく見開かれた。
「……え?翠星石…!?」
「……本気…ですからね?」
互いの顔はこれでもかという程赤い。
やっと出せた勇気。
でも、本番はこれから…。今までとは違う、二人ののクリスマスはまだ始まったばかり―…。
「ねえ、翠星石。
…僕からもプレゼント」「え…?」
「目、閉じて」
「 ? こうですか?」
「…そう、そのまま…」耳元で囁いて、蒼星石が目を閉じたままの翠星石の唇に自分の唇を重ねる。
(え…!?)
唇に触れた温かく柔らかい感触。それがキスだと気づくのに多少時間がかかった。そして左手にも温もりを感じる。
「…もう、目を開けていいよ」
その声にゆっくりと瞼を開く。目の前には頬を赤く染めた蒼星石の顔。
顔が熱くなるのを感じながら自分の左手に違和感を感じて視線を移す。
「え!?これ…!」
左手の薬指にはエメラルドの石が付いた銀色の指輪が光っている。
「…僕からのクリスマスプレゼント。
エンゲージリングの代わり…ずっと一緒にいる証」
照れ臭そうに蒼星石が付け加える。
「…ありがとうです…蒼星石…////」
どうしよう、すごく嬉しい。翠星石は嬉しそうに自分の左手を見つめ、右手で包むようにする。
が、幸せの余韻に浸ろうとしたその時、ある事を思い出した。
「じゃ…翠星石、そろそろ歩く?」
「あ…待つです!」
「 ? どうしたの?」
翠星石はじっと蒼星石を見る。まだ終わっていない、言わなければ、あの「言葉」を。
(ゆ、勇気を…出すですよ!翠星石!)
瞬間、翠星石は蒼星石の頬を両手で包み…そっと唇を重ねた。
そして唇をした後、耳元に囁きゆっくりと離れる。直後、蒼星石の瞳が大きく見開かれた。
「……え?翠星石…!?」
「……本気…ですからね?」
互いの顔はこれでもかという程赤い。
やっと出せた勇気。
でも、本番はこれから…。今までとは違う、二人ののクリスマスはまだ始まったばかり―…。
- あああああ。愛し合うって良い事ですね。
心がふわふわして、温かい気分になれました。
-- 胡蝶 (2011-03-30 13:47:15)