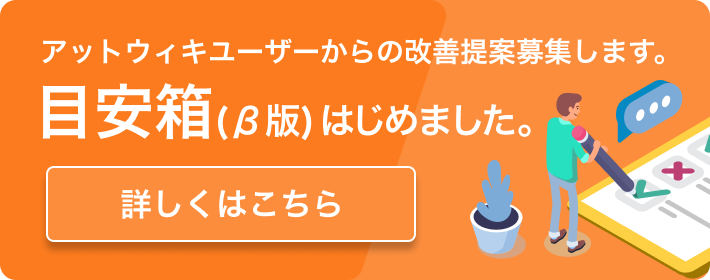84pの小説
遊義皇第14話
最終更新:
84gzatu
-
view
| 星5認定、招待状はどこに? セカンドハンター、デュエルアドバイザー、トレーディングコンサルタントなどの多くの専門職がある昨今のDM事情。 それらの職業で優遇される『星5』の認定大会だが、毎年10万人を超える募集があり、今後は『招待状』を持つデュエリストのみに参加資格が与えられることとなった。 招待状は特定の人物が複数枚所有しており、その人物を見つけ出す人望が最低条件、とのI2社からの公式発表となっている。 この決定に伴い、偽の招待状が市場に出回っている。 以上、週間デュエルニュースより抜粋。 |
壱
朱が染みこんだように、ところどころ赤くなった秋の山道。
オフロードには全く似合っていないが、木々以上に赤いオープンカーは、大人1人に子供2人を乗せて走る。
オフロードには全く似合っていないが、木々以上に赤いオープンカーは、大人1人に子供2人を乗せて走る。
「あぁー、できればもうちょっと赤くなった頃に来たかったなァ。
葉が全然落ちてねぇや。」
葉が全然落ちてねぇや。」
「なあ? なにが楽しいんだ? ただ赤くなるだけだろ?
…俺は梅雨の方が好きだね、虫やヘビなんかがウジャウジャ出るんだ。」
…俺は梅雨の方が好きだね、虫やヘビなんかがウジャウジャ出るんだ。」
近すぎてもダメということだろうか、山育ちの刃咲に紅葉狩りの風情は分からないらしい。
オープンカーでオフロードを走るというだけで似合わないのに、助手席はリュックサック2つ、後部座席もチャイルドシートで埋まっている。
これで風情と思え、というのも、福助や刃咲には酷かもしれない。
オープンカーでオフロードを走るというだけで似合わないのに、助手席はリュックサック2つ、後部座席もチャイルドシートで埋まっている。
これで風情と思え、というのも、福助や刃咲には酷かもしれない。
「あぁー…少なくとも、タバコも吸えねぇドライブよりマシじゃねぇ?」
「子供が居るのに吸うな、大人としてのマナーだろ。」
「あぁー、天井も無い車でタバコ吸っても誰も困らないと思うんだがね、俺は。」
それはざっと2時間前。
久々に連絡してみると、状況は激変していた。
ウォンビックたちヴァイソンダーヅの加入によって、次の作戦に必要な人数が揃った。
拠点となる大阪に最短で帰るにはオセロ村で車を調達しなければならないが、余っている車はひとつだけ。
久々に連絡してみると、状況は激変していた。
ウォンビックたちヴァイソンダーヅの加入によって、次の作戦に必要な人数が揃った。
拠点となる大阪に最短で帰るにはオセロ村で車を調達しなければならないが、余っている車はひとつだけ。
それは刃咲家が二封気に頼まれて用意していた真っ赤なオープンカー。
しかし、所有権は未だに刃咲家が持っており、そのせいで自賠責保険の条件として家族の誰かが乗っている必要があった。
結果として、チャイルドシート2つ付けたオフロードを走るオープンカー、というコメディのような物体が出来上がった。
しかし、所有権は未だに刃咲家が持っており、そのせいで自賠責保険の条件として家族の誰かが乗っている必要があった。
結果として、チャイルドシート2つ付けたオフロードを走るオープンカー、というコメディのような物体が出来上がった。
「あぁー、にしても、福助の親はよく許したよな?
俺みたいな見ず知らずのミステリアス男に子供を任す、ってのもよ。」
俺みたいな見ず知らずのミステリアス男に子供を任す、ってのもよ。」
「あれ? 言ってませんか? 僕、親居ませんよ?」
驚くほどあっさりと福助は言ったが、そのあっさりさのせいでどういう意味かクロックは理解が遅れた。
「あぁー…そりゃぁ…その、悪ィ。」
「ああ、死んだわけじゃないですよ?
ただ消息不明なんで、それで親戚の壱華ちゃんの家でお世話になってるんです。」
ただ消息不明なんで、それで親戚の壱華ちゃんの家でお世話になってるんです。」
壱華の両親となら、クロックは面識があった。
朝からデュエルをしていた中に、そう自己紹介をする中年夫婦は居た。
朝からデュエルをしていた中に、そう自己紹介をする中年夫婦は居た。
「あぁー…早く見つかると良いな。」
「ありがとうございます。
でも、顔も覚えてない両親ですから、心配はしてないんです。」
でも、顔も覚えてない両親ですから、心配はしてないんです。」
「あぁー、それでもまぁ、見つからないより見つかった方が…ん?」
その時、クロックはあることに気が付いた。
自分たちが乗っている車のガソリンメーターの指している位置が思いっきり『E』に近い。
エンプティ。 ハンプティ・ダンプティでもなければ、エンプレスでもプティングでもない。
EとはエンプティのE、ガス欠だ。
自分たちが乗っている車のガソリンメーターの指している位置が思いっきり『E』に近い。
エンプティ。 ハンプティ・ダンプティでもなければ、エンプレスでもプティングでもない。
EとはエンプティのE、ガス欠だ。
「…あぁー、蕎祐、福助、ちょっと聞きたいんだが…この辺り、ガススタンド有ったっけ?」
その質問に状況を察知した刃咲の顔から血の気が引いた。
「…クロック、まさか…山ん中で…ガス欠、ってことは…ねえよな?」
「あぁー…こりゃ、俺たちが消息不明になっちまうかなぁー?」
「そうみたいですねー、ははは。」
本気で笑えない状況でも余裕のある福助5歳、状況がわかってるんだろうか、彼は。
とにかく、エンジンを止めるクロック。
とにかく、エンジンを止めるクロック。
「あぁー、どうすっかな。 引き返すにしても足りねぇが…戻れるだけ戻って、あとは徒歩で帰るか?」
「それか他のドライバーに事情を言ってガソリンを分けてもらうか、だな。
マトモな大人なら、山に入る前にガソリンの確認ぐらいしてるだろうしな。」
マトモな大人なら、山に入る前にガソリンの確認ぐらいしてるだろうしな。」
陰にクロック批判まで絡める刃咲。
「あぁー…蕎祐? こんな山奥に誰が通るんだ?」
「誰かは分からないが、現にあそこに居る。」
刃咲が差した方向には、たしかに人間が居た。
しかもひとりではない、テントを中心に確実に5人は居るし、しかもその内の数人は刃咲たちに気が付き、注目している。
しかもひとりではない、テントを中心に確実に5人は居るし、しかもその内の数人は刃咲たちに気が付き、注目している。
「あぁー…なんだ、あの怪しい連中。 山の中で何してるんだ?」
自分たちも山の中でガス欠になっているのを棚において警戒するクロック。
「すみませーん、ガス欠になっちゃったんですけどー、分けてもらえませんかーっ!」
「静かにしてくださーい!」
近づいてから喋れば良いのに、やまびこが聞こえるほどの声で問う福助に、予想内の応答が返る。
「あぁー…近づいてから交渉するぞ。 静かにしてろよ?」
「心理学的には、快活な子供は大人に不信感を持ってるらしいぜ?
…お前が全部やってくれれば任せられれば黙ってるよ。」
…お前が全部やってくれれば任せられれば黙ってるよ。」
「…とりあえず、黙ってろ。」
クロックはオープンカーの特権といわんばかりに、ドアを開けずにまたいで下車した。
そして刃咲と福助のチャイルドシートのベルトを手際悪く外す。
そして刃咲と福助のチャイルドシートのベルトを手際悪く外す。
「あぁー…なんだ? テレビ局か何かか? ありゃァ。」
よく見れば、アウトドアだというのに、みなりが整っている人間が多すぎる。
カメラやら集音機材を持ったスタッフも居るし、何かを撮影しているのは間違いない。
被写体の男はアイマスクとデュエルディスクを装着しているが、デッキホルダーにはカードは入っておらず、手元に1枚だけ持っている。
カメラやら集音機材を持ったスタッフも居るし、何かを撮影しているのは間違いない。
被写体の男はアイマスクとデュエルディスクを装着しているが、デッキホルダーにはカードは入っておらず、手元に1枚だけ持っている。
「…あぁー、なにやってんだ?」
「お静かにっ…お願いします。」
集音機材を持っているスタッフの言葉に、クロックたち3人は成り行きを見守っている。
「シュっ…。」
被写体の男は、手元に持っていた1枚のカードを持っている手を声にあわせて静かに、それでいて速く振った。
カード手裏剣とかカード投げとか呼ばれる曲芸だった。
投げたカードは木に突き刺さり、その衝撃で何枚かの葉が落ちる。
よく見れば、当たった木には、既に数十枚のカードが刺さっていた。
カード手裏剣とかカード投げとか呼ばれる曲芸だった。
投げたカードは木に突き刺さり、その衝撃で何枚かの葉が落ちる。
よく見れば、当たった木には、既に数十枚のカードが刺さっていた。
「外れたのは21枚目と32枚目、刺さったのは38枚。」
投げきった男は、言ってからアイマスクを外した。
一流の狙撃手は撃った瞬間に当たるかどうか瞬間的に理解するという。
それと同じで、彼にとってはカードが当たったかどうか見なくても判断できる、ということなのだろう。
一流の狙撃手は撃った瞬間に当たるかどうか瞬間的に理解するという。
それと同じで、彼にとってはカードが当たったかどうか見なくても判断できる、ということなのだろう。
「はい、オッケー。」
この場の責任者と思しき女性の言葉に、カメラや集音機のスタッフが手を休める。
女性はクロックへと向き直り、軽く会釈した。
女性はクロックへと向き直り、軽く会釈した。
「すいませんでした、どういったご用で?」
「あぁー、もう喋って良いんだな?
ガス欠しちまってよ、ガソリンを分けて欲しいんだが、余ってないか?」
ガス欠しちまってよ、ガソリンを分けて欲しいんだが、余ってないか?」
「えーっと、大滝さん、ガソリン、余ってましたっけ?」
「あります。 トライアル用に200リッター余分に持ってきましたから。」
大滝と呼ばれたスタッフは明快に答えた後、車のトランクの中から実際に数を数える。
「確認しましたー。 売れます。」
「あぁー、なら20ぐらい頼めるか?」
「ええ、もちろ…」
「待ていッ! このウェンディエゴ様の名乗りを聞けッ!」
一昔前のヒーローのように止めに入ったのは、先ほどカードを投げていた男だ。
そこにきて、クロックはその男に見覚えが有ったらしい。
そこにきて、クロックはその男に見覚えが有ったらしい。
「あぁー、ウェンディエゴって、ひょっとして飛べない風船 のロールウィッツ・ウェンディエゴか?」
「って、テメェッ! このウェンディエゴ様が名乗る前に名前を言うんじゃないッ!
名乗れないじゃねぇかッ! バッカじゃねぇのォっ!」
名乗れないじゃねぇかッ! バッカじゃねぇのォっ!」
大声を出した男…ロールウィッツは、子供相手とは思えないほどの大声は、ヤマビコの形でリピートされる。
「って、この、バカチンがあッツ!」
大滝と呼ばれていたスタッフが、目にも留まらぬスピードで“何か”でロールウィッツの後頭部を叩く。
「なにをすッだーッ! 信二ィッッ!」
フルネームは、大滝信二らしい。
こう、コメントに困るぐらい普通の名前だ。
こう、コメントに困るぐらい普通の名前だ。
「こっちのセリフですよ、ロールウィッツ! ファンは大事にしろって言ったでしょう!」
殴ってヘコんだガソリン缶を投げ捨てつつ、大滝は刃咲に頭を下げる。
「すいません、ロールウィッツは挑戦が失敗しちゃってちょっとイライラしてるもので!」
「あぁー、ファンってわけじゃねぇし、そういうのはいいよ。
それよか、あぁー、それじゃあ、本物なんだよな? あんたら。」
それよか、あぁー、それじゃあ、本物なんだよな? あんたら。」
「本物の飛べない風船 メンバーだよ。」
「へぇー。 じゃあさっきのって…」
「クロック。 ちょっと紹介しろ。 誰だこいつら。」
本人達を前にして、堂々と知らない発言。
福助も知らなかったようだが、聞き方を選んでるうちに毒舌の方が質問した。
福助も知らなかったようだが、聞き方を選んでるうちに毒舌の方が質問した。
「あぁー、飛べない風船って書いてそう読むんだよ。
『デュエル界の奇行子』を自称してるチーム、貴族の公に子供じゃなくて、奇妙な行動の子供、って書いて。」
『デュエル界の奇行子』を自称してるチーム、貴族の公に子供じゃなくて、奇妙な行動の子供、って書いて。」
「…奇行って、何したんだ?」
よくぞ聞いてくれました、と言わんばかりにロールウィッツがふんぞり返る。
「考案は全てこのウェンディエゴ様! バッカな一般人には思いつかないような
あるときは、海に潜って水中でデュエル! 勝者は当然ウェンディエゴ!
あるときは、目隠しして記憶だけでデュエル! 勝者は当然ウェンディエゴ!
あるときは、-40℃の冷蔵庫の中でデュエル! 勝者は当然ウェンディエゴ!」
あるときは、海に潜って水中でデュエル! 勝者は当然ウェンディエゴ!
あるときは、目隠しして記憶だけでデュエル! 勝者は当然ウェンディエゴ!
あるときは、-40℃の冷蔵庫の中でデュエル! 勝者は当然ウェンディエゴ!」
「潔いまでのダメ大人だな、あんた…」
「あるときは、犬ゾリを操り、犬デッキでデュエル! 勝者は当然ウェンディエゴ!
あるときは、500円以内で構築したデッキでデュエル! 勝者は当然ウェンディエゴ!
あるときは、海馬瀬人のコスプレをして〔青眼の銀ゾンビ〕デッキでデュエル! 勝者は当然ウェンディエゴ!」
あるときは、500円以内で構築したデッキでデュエル! 勝者は当然ウェンディエゴ!
あるときは、海馬瀬人のコスプレをして〔青眼の銀ゾンビ〕デッキでデュエル! 勝者は当然ウェンディエゴ!」
「オイ、人の話を…」
「あるときは、ロボットダンスをしながら機械族デッキでデュエル! 勝者は当然ウェンディエゴ!
そう! このウェンディエゴこそレジェンド・オブ・レジェンド! デュエリスト・オブ・デュエリスト!
天下の天才デュエリスト、そうこのウェンディエゴ様がぶぎァ」
そう! このウェンディエゴこそレジェンド・オブ・レジェンド! デュエリスト・オブ・デュエリスト!
天下の天才デュエリスト、そうこのウェンディエゴ様がぶぎァ」
まくし立てるロールウィッツに、刃咲は脛を踏みつけて、閉口させた。
喋っているときに口を閉めれば舌を噛むわけで…ロールウィッツの口からはダラダラと流血している。
喋っているときに口を閉めれば舌を噛むわけで…ロールウィッツの口からはダラダラと流血している。
「なぢをするんじだぁーッ!」
「ウゼぇよ、ダメ大人。 空気ぐらい読めよ。」
睨みつけるロールウィッツに、刃咲は悪びれもしていない。
「このバッカ野郎…バイクは運転できるか、テメェ。」
「どう見たら俺が乗れる年齢に見える?」
「ならばッ! そっちの男はどうだ? 外人の。」
「あぁー? 大型なら13から乗ってっけど?」
あっさりと無免許発言するクロック、基本的にスルーだ。
「ならば、運転するのは外人、お前で良い!
勝負の方法は、このウェンディエゴ様考案のバイクに乗ってのデュエル、新感覚デュエル、ライディング・デュエルだ!」
勝負の方法は、このウェンディエゴ様考案のバイクに乗ってのデュエル、新感覚デュエル、ライディング・デュエルだ!」
バカと天才は紙一重、という言葉がある。
冷静に考えて、バイクに乗りながらデュエルする必要性はなく、奇行でしかない。
が、このロールウィッツの発想は、数十年後、ネオドミノシティで開催されるライディング・デュエルに先駆けていた。
やはり、天才とバカは紙一重である。
冷静に考えて、バイクに乗りながらデュエルする必要性はなく、奇行でしかない。
が、このロールウィッツの発想は、数十年後、ネオドミノシティで開催されるライディング・デュエルに先駆けていた。
やはり、天才とバカは紙一重である。
弐
寝起きの悪いホーティックは、時計を見ると頭が一気に覚める実感を持った。
昨日は、夜遅くまでウォンビックとデュエルし、オセロ村でのクロックのデュエルを観戦し、寝室でホーティックが眠ったのが5時過ぎ。
そして、今はデジタル時計には『AM9:22』の表記。
しかし、他のベッドには誰も寝ていない。
――しまった、寝坊した――焦りがホーティックの寝ぼけた頭を覚醒させたのだ。
昨日は、夜遅くまでウォンビックとデュエルし、オセロ村でのクロックのデュエルを観戦し、寝室でホーティックが眠ったのが5時過ぎ。
そして、今はデジタル時計には『AM9:22』の表記。
しかし、他のベッドには誰も寝ていない。
――しまった、寝坊した――焦りがホーティックの寝ぼけた頭を覚醒させたのだ。
「やっちゃったかなー……。」
今、ホーティックたちが居るマンションは正念党が拠点として使っているマンションの一室。
普段からホーティックはここに住んでいるので食糧や現金の保管場所や、パソコンのパスコードも知っているが、他のメンバーはそれを知らない。
つまり、自分が起きなければ電子メールでの連絡などの任務だけでなく、食事すらできないのだ。
普段からホーティックはここに住んでいるので食糧や現金の保管場所や、パソコンのパスコードも知っているが、他のメンバーはそれを知らない。
つまり、自分が起きなければ電子メールでの連絡などの任務だけでなく、食事すらできないのだ。
「すいません、寝坊しまし…あれ?」
ワイシャツの襟を正す間も惜しみ、急行したホーティックはダイニングで予想もしていない光景を目の当たりにした。
んがぁあああああっっ~~ァ
フゥ……フゥー
ギィギッリギッギギィ
テーブルに突っ伏して大イビキを上げる神次郎。
ソファーを枕に静かに眠るウォンビック。
ウォンビックの腹の上に歯軋りしながら大の字に眠るトガ。
壁に寄りかかり、寝ているのかも起きているのかも分からないエビエス。
……とどのつまり、コイツらはベッドに行くのが面倒で、ここで眠っただけだ。
ソファーを枕に静かに眠るウォンビック。
ウォンビックの腹の上に歯軋りしながら大の字に眠るトガ。
壁に寄りかかり、寝ているのかも起きているのかも分からないエビエス。
……とどのつまり、コイツらはベッドに行くのが面倒で、ここで眠っただけだ。
「……みなさーん、もう9時です。 起きてください。」
「……ん、ンのァ……。」
「おはようございます、モーガン第3幹部、ブラックマイン幹部候補。」
さほど大声というわけでもなかったのだが、ウォンビックは緩やかに目を開けた。
だが、トガと神次郎は未だに歯軋りとイビキを止める気配がない。
ウォンビックはトガを猫か何かのように持ち上げ、自分が枕にしていたソファーに移してから立ち上がった。
だが、トガと神次郎は未だに歯軋りとイビキを止める気配がない。
ウォンビックはトガを猫か何かのように持ち上げ、自分が枕にしていたソファーに移してから立ち上がった。
「…ニッポンの家は暖かいのは良いが、天上が低いのが難点だな。」
「それは有りますね。
ニッポンは“大多数である”ということを美徳としている民族ですから。
日本人の平均身長で考えると、これぐらいで良いんですよ。」
ニッポンは“大多数である”ということを美徳としている民族ですから。
日本人の平均身長で考えると、これぐらいで良いんですよ。」
「…ホーティック、給料を前借させてくれ。
大多数が美味いという朝飯を食いたいんだが、金はドルしか持ってない、トガと俺の分を頼む。」
大多数が美味いという朝飯を食いたいんだが、金はドルしか持ってない、トガと俺の分を頼む。」
「食事なら隣の部屋のをどうぞ。 カンヅメとレトルトがあります。
飲み物は厨房の冷蔵庫の中…冷凍庫に入ってるアイスや冷凍食品もご自由にどうぞ。」
飲み物は厨房の冷蔵庫の中…冷凍庫に入ってるアイスや冷凍食品もご自由にどうぞ。」
ウォンビックは、我が耳を疑った。
ホーティックは3ヶ国語以上を喋れるが、自分は母国語の英語のみ。
その関係で、なにかヒヤリングのミスがあったのではない、と。
ホーティックは3ヶ国語以上を喋れるが、自分は母国語の英語のみ。
その関係で、なにかヒヤリングのミスがあったのではない、と。
「自由というのは…食い放題、という意味か?」
「ええ、基本的に党員は貯蓄食糧の使用は原則自由。
外で食べたいなら、ストックのカードをカードショップに持って行って換金して、そのお金でどうぞ。」
外で食べたいなら、ストックのカードをカードショップに持って行って換金して、そのお金でどうぞ。」
ホーティックが当然のように言っているが、ウォンビックには信じがたいことばかりだった。
「食べ放題にカード取り放題って…正念党の資金源はどうなってるんだ?」
「カードハント、に決まってるじゃないですか。」
当たり前でしょう、と言わんばかりにホーティックが云う。
「俺もヴァイソンダーヅの長としてやっていたが、そこまでの黒字はでなかった。
…そこまで稼いでいるのか? 正念党は?」
…そこまで稼いでいるのか? 正念党は?」
「んー、それじゃあ、実際に見てください。」
言いながらホーティックはデスクトップパソコンの電源を入れる。
「…なんだ?」
ディスプレイに表示されたのは、大量のカード名。
そしてその横には値段と思われる数字に、いくつかの日付、よくわからない数字も多い。
そしてその横には値段と思われる数字に、いくつかの日付、よくわからない数字も多い。
「現在、正念党が保有している“本物”のレアカードたちです。
コピーカードを売る場合も有りますが…主にこれらが売り物となります。
このリスト自体は、パスワードさえ知っていれば一般のパソコンからでも見れます。
パスワードを知らなくても、セキュリティ突破のノウハウを持っている人間なら簡単に進入できます。」
コピーカードを売る場合も有りますが…主にこれらが売り物となります。
このリスト自体は、パスワードさえ知っていれば一般のパソコンからでも見れます。
パスワードを知らなくても、セキュリティ突破のノウハウを持っている人間なら簡単に進入できます。」
「これが全て在庫なのか…?」
「ええ、中には奪い取ったカードも有りますが、買い取ったカードも多く有ります。
おそらく、ウォンビックさんたちは在庫を作らず、奪い取ったカードはすぐに売っていたのでは?」
おそらく、ウォンビックさんたちは在庫を作らず、奪い取ったカードはすぐに売っていたのでは?」
喋りながらもホーティックはキーボードを叩き、画面内に反映させていく。
「ああ、そうしなければ金にならないし、大量のカードを管理する余裕も無かったからな。」
「そこに無駄が出やすいんですよ。
闇市同然では仲立ちブローカーも増える。
ダーヅの皆さんの手元に入る値段も末端価格の数分の一、下手をすれば数十分の一です。
…すいません、手が離せなくなります。 あとの説明はエビエスさん、お願いします。」
闇市同然では仲立ちブローカーも増える。
ダーヅの皆さんの手元に入る値段も末端価格の数分の一、下手をすれば数十分の一です。
…すいません、手が離せなくなります。 あとの説明はエビエスさん、お願いします。」
ホーティックの言葉に、エビエスがゆったりと壁から背を離す。
画面上で行われる情報の交換に、ホーティックが熱中しキーボードを乱打する。
画面上で行われる情報の交換に、ホーティックが熱中しキーボードを乱打する。
「で…正念党は何をする組織なんだ?」
「デュエルモンスターズのデイトレード…ですね。
仕入れ・販売・強奪を大規模でしていれば儲かるんですよ。
今はデュエルバブルの真っ只中…経済状況からしてまだ膨らみますし。」
仕入れ・販売・強奪を大規模でしていれば儲かるんですよ。
今はデュエルバブルの真っ只中…経済状況からしてまだ膨らみますし。」
デュエルバブル。
現在、世界規模でこのカードゲームの経済効果は異常とも言うべき膨らみ方をしている。
値段が急落するカードは確かに存在するが、それでも価値が上がるカードは確実に上がり続けている。
このバブルが弾けるリミットというのも予想が割れており、3年前に『あと2年で弾ける』と予想して恥をかいた研究者も居れば、あと1000年は続くとする者まで居る。
現在、世界規模でこのカードゲームの経済効果は異常とも言うべき膨らみ方をしている。
値段が急落するカードは確かに存在するが、それでも価値が上がるカードは確実に上がり続けている。
このバブルが弾けるリミットというのも予想が割れており、3年前に『あと2年で弾ける』と予想して恥をかいた研究者も居れば、あと1000年は続くとする者まで居る。
「それならカードハントをやる意味なんてないんじゃないか? 充分に企業としてやっていけるだろう。」
「確かにあなたのように“ハンデ”のあるデュエリスト、というのもそうは居ませんからね。
並の稼ぎで満足できるならば、党員となる必要は有りませんね。」
並の稼ぎで満足できるならば、党員となる必要は有りませんね。」
ウォンビックは孤児院を運営している。
職業というのは、家族が増えれば選択肢も減っていくものである。
結婚は出費を4倍にする…というのはイギリスのことわざにあるが、子供が増えれば4倍どころの騒ぎではない。
職業というのは、家族が増えれば選択肢も減っていくものである。
結婚は出費を4倍にする…というのはイギリスのことわざにあるが、子供が増えれば4倍どころの騒ぎではない。
「だから、要点だけを教えてくれないか? お前の話は回りくどい。」
「…皮肉も通じないのか、この筋肉ダルマは…」
「何か言ったか?」
「いえ、別に。
昔から富豪というのは、金をダイヤなどの価値が変わりにくい高級品に変え、税金逃れをすることが有ります。
しかし、現金を物に替えるだけでも相当の経済的負担になりますし、物によっては維持費がかかります。」
昔から富豪というのは、金をダイヤなどの価値が変わりにくい高級品に変え、税金逃れをすることが有ります。
しかし、現金を物に替えるだけでも相当の経済的負担になりますし、物によっては維持費がかかります。」
金の有る人間というものは奇妙なもので、充分な蓄えがあるのに国に略取されるのを渋る。
取られて困るわけでもないのに、犯罪というリスクを犯して金を持っていないことにし、脱税。
ここまで云われ、ウォンビックも気が付いた。
取られて困るわけでもないのに、犯罪というリスクを犯して金を持っていないことにし、脱税。
ここまで云われ、ウォンビックも気が付いた。
「…ダイヤやワインの代わりに、レアカードを買い込む、というわけか。」
「その通りです。
レアカードを買い込むことには何の違法性も無い。
法整備をしようにも所詮はトレーディングカード、オモチャです。
どうやっても課税対象にはできませんし、購入・売却も容易で維持費も掛からない、理想的でしょう?」
レアカードを買い込むことには何の違法性も無い。
法整備をしようにも所詮はトレーディングカード、オモチャです。
どうやっても課税対象にはできませんし、購入・売却も容易で維持費も掛からない、理想的でしょう?」
「つまり、そういう連中にレアカードを斡旋して儲けている、というわけか?」
「そういうこともありますけが、解としては不適当ですね。
正解は『脅迫してでもデュエルを受けさせ、そのアンティで奪う』、です。」
正解は『脅迫してでもデュエルを受けさせ、そのアンティで奪う』、です。」
その率直な回答にウォンビックは納得したらしく頷き、薄く笑っている。
「…思ったより俺好みな組織のようだな、正念党は。」
「何がですか?」
「脅してまでデュエルするなら、盗んだ方が速いだろう?
気に入った、ドッグ&マン以上にヴァイソンダーヅ向きのルールだ。」
気に入った、ドッグ&マン以上にヴァイソンダーヅ向きのルールだ。」
「あなたのような人にも気に入っていただければ、私も光栄です。」
露骨な言い回しにやっとこと、ウォンビックはあることに気が付いた。
「…エビエス、ひょっとしてお前、俺のことが嫌いか?」
「敵だったにも関わらず、私が苦労して入った七人衆に労せず加わった。
しかも私が敬愛するシャモン様にもあっさりと気に入られていますしね。
好意は持っていませんし、仮にあなたが不幸な目に遭えば喜びますね、確実に。」
しかも私が敬愛するシャモン様にもあっさりと気に入られていますしね。
好意は持っていませんし、仮にあなたが不幸な目に遭えば喜びますね、確実に。」
「…鉄柱を叩いたゴルククラブのように曲がった性格だな、お前。
シャモンや神次郎のようなシンプルなヤツも好きだが、お前のようなタイプも好きだな、俺は。」
シャモンや神次郎のようなシンプルなヤツも好きだが、お前のようなタイプも好きだな、俺は。」
「…私と違って、皮肉がお上手で。」
エビエスは、ウォンビックのこの豪放さが嫌いだった。
自分と違って下品で、それでいてそこがシャモンには好かれそうな。
…結婚は出費を4倍にするが、悲しみを半分にし、喜びを倍にする…イギリスのことわざである。
ウォンビックの孤児院には何人の子供が居るのかはエビエスは知らない。
だが、とにかくこの男の喜びは果てしないであろう、とは予想できた。
自分と違って下品で、それでいてそこがシャモンには好かれそうな。
…結婚は出費を4倍にするが、悲しみを半分にし、喜びを倍にする…イギリスのことわざである。
ウォンビックの孤児院には何人の子供が居るのかはエビエスは知らない。
だが、とにかくこの男の喜びは果てしないであろう、とは予想できた。
「…ちょっと見てもらえますか、エビエスさん、ウォンビックさん。
口で説明するのも難しいので、お願いします。」
口で説明するのも難しいので、お願いします。」
パソコンのモニターを見ると、それは何かの動画サイトのようだ。
どこかの山道だろうか、紅葉の中にデュエルディスクを付けた男が写っている。
どこかの山道だろうか、紅葉の中にデュエルディスクを付けた男が写っている。
「…これはアイアンバルーンですね。
“最強・最驚”を吹聴する変人デュエルチーム…これがどうしました?」
“最強・最驚”を吹聴する変人デュエルチーム…これがどうしました?」
「手違いがあったらしく、今回の対戦相手は差し替えだそうです。
相手はトライクバイクで2人乗り、ひとりが運転してもうひとりがデュエル、だそうです。」
相手はトライクバイクで2人乗り、ひとりが運転してもうひとりがデュエル、だそうです。」
トライクバイクとは、3輪タイプのバイク…なのに普通自動車免許で運転できるというよくわからない乗り物。
日本ではあまり親しみはないが、外国ではポピュラーな乗り物である。
そのバイクに運転手として乗っているのは、紫のコートに身を包んだバイクの似合うアメリカ人。
日本ではあまり親しみはないが、外国ではポピュラーな乗り物である。
そのバイクに運転手として乗っているのは、紫のコートに身を包んだバイクの似合うアメリカ人。
「クロックじゃないか? この男?」
「…ジュフ第四幹部、のようですね。」
二人乗りのトライクバイクの運転手、それはクロック・ジュフその人だった。
そしてデュエルディスクを構えた相乗りしている少年にも、ホーティックだけは見覚えがある。
オセロ村で出会った少年、刃咲蕎祐だ。
そしてデュエルディスクを構えた相乗りしている少年にも、ホーティックだけは見覚えがある。
オセロ村で出会った少年、刃咲蕎祐だ。
「…集合に遅刻した上、まさか遊んでいるとは…呆れましたよ。
このようなことをなさるからパワードカードを預けられないというのに。
ジュフ第四幹部は…未だに幹部としての自覚が足りていないようですね。」
このようなことをなさるからパワードカードを預けられないというのに。
ジュフ第四幹部は…未だに幹部としての自覚が足りていないようですね。」
「欲しいとすら言ったこともありませんけどね、クロックさんは。」
「…パワードカードには興味が無いが、このデュエルは注目に値するがな。
朝飯を食いながら見せてもらう。」
朝飯を食いながら見せてもらう。」
神経質なエビエスに対し、ホーティックやウォンビックは危機感はおろか、むしろ楽しそうだ。
エビエスのヒステリックな神経は、こういう態度にイライラする。
エビエスのヒステリックな神経は、こういう態度にイライラする。
参
「世界初! バイクに乗りながらのデュエル! 時代先取り!
実況はオレ様、エビル大滝と!」
実況はオレ様、エビル大滝と!」
「エヴォルテクター・キョーコがお送りしますゥッ」
カメラを持ったスタッフに向け、2人の男女が軽快に喋る。
男の方はサングラスに金髪カツラ、女の方はプロレスのマスク、共に鍛え上げた身体に露出の高い服を着ている。
そんな司会者2人から20メートルほど離れた地点、バイクを最終調整するクロックと刃咲は冷ややかな視線を送っていた。
男の方はサングラスに金髪カツラ、女の方はプロレスのマスク、共に鍛え上げた身体に露出の高い服を着ている。
そんな司会者2人から20メートルほど離れた地点、バイクを最終調整するクロックと刃咲は冷ややかな視線を送っていた。
「あぁー…グラサンやマスクひとつで印象が変わるなぁ。」
「だよなぁ、グラサンで垂れ目をカバーで箔が付いてる。
…プロレスマスクのオバチャンは、6歳はサバ読めるわ、マスク付けると。」
…プロレスマスクのオバチャンは、6歳はサバ読めるわ、マスク付けると。」
クロックはミラーの角度調整、刃咲は後部席のベルトを短くしてサイズを調整する。
「ほう、お前たちは中々見所があるな。
このウェンディエゴ様と同じ意見を出せるとは!
あの2人は外聞を気にしすぎる、デュエルは楽しむものだ。」
このウェンディエゴ様と同じ意見を出せるとは!
あの2人は外聞を気にしすぎる、デュエルは楽しむものだ。」
同じく遠目に大滝とキョーコに感想を飛ばすこの男は、この発案者にして飛べない風船のリーダー、ロールウィッツ・ウェンディエゴ。
今現在、バイクの前輪を取り外すべくホイールと格闘している。
今現在、バイクの前輪を取り外すべくホイールと格闘している。
「最初に、このデュエルを見ているキッズ&シニアどもにバッドなニュースッ!」
「えええ、なんだろォッ。」
「当初は、うちのリーダーのロールウィッツと、ハゲヤ・マリアの王魔 研介のデュエルだった!
だがしかーしッ なんとなんとなんとォ! 王魔のヤローがドタキャンしやがった、あのヤロー!」
だがしかーしッ なんとなんとなんとォ! 王魔のヤローがドタキャンしやがった、あのヤロー!」
「えーっ、どうするのぉ! エビルゥ!」
台本を噛まずに正確に喋るエヴォルテクターキョーコとエビル大滝。
どうでもいいがこの人たち、素顔を晒していてもこんなにハッちゃけて喋れるんだろうか。
どうでもいいがこの人たち、素顔を晒していてもこんなにハッちゃけて喋れるんだろうか。
「心配無用! 今回はガス欠の車でハイキングなんぞしてやがったバカどもを拉致ってやった!」
「ええ、バイクに乗りながらデュエルなんて、素人さんにできるのォ?」
「今回はハンディキャップをくれてやるぜ、オレ様、優しいぃいーッ!
飛び入りの連中が使うのは2人乗りが可能なトライクバイク。
ヤローが運転して、デュエルはちょこんと後ろに乗ったガキが担当だ!」
飛び入りの連中が使うのは2人乗りが可能なトライクバイク。
ヤローが運転して、デュエルはちょこんと後ろに乗ったガキが担当だ!」
「ええ、ロールウィッツのバイクに、シロートのトライクなんかで追いつけるのぉ?」
「そこもハンディキャップをくれてやるゼッ!
そのハンディとは…あとで説明してやるぜ!」
そのハンディとは…あとで説明してやるぜ!」
「ロールウィッツのバイクは排気量700㏄のカスタムハーレーっ!
並みのハンディじゃトライクバイクに勝ち目は無いわね…何キロ走るんだったかしら?」
並みのハンディじゃトライクバイクに勝ち目は無いわね…何キロ走るんだったかしら?」
「山を丸々降りる約73キロのコース! 急カーブあり! 坂あり! 難所だ!」
難所といえば言葉はいいが、ようは自治体の予算不足なだけだ。
ガードレールやアスファルト舗装もされていないような部分も多い、ただの田舎道だ。
ガードレールやアスファルト舗装もされていないような部分も多い、ただの田舎道だ。
「さぁて、拉致られた2人にインタビューだ! 遺言になるかもしれないなぁー!」
「笑えるわー! エビルゥ!」
傍から見ると、カメラの移動速度にあわせて神経質に歩く仮装した大滝や今日子の方が笑える。
「さぁ! 名前を言ってくれよー! 戒名ならあとで俺がつけてやるぜー!」
「刃咲蕎祐だ。」
「あぁー、クロック・ジュフだ。
…あんたらも大変だな、そういうキャラ作り…信二。」
…あんたらも大変だな、そういうキャラ作り…信二。」
「ハッハッハァー!
なんのことだァー!? クロォーック! 俺はエビル大滝だぜーッ!?」
なんのことだァー!? クロォーック! 俺はエビル大滝だぜーッ!?」
さすがはプロ、ポーカーフェイスのエビル大滝こと大滝信二くん。
カメラを持っているスタッフが、口パクで“生中継! 生中継!”と口パクしている。
カメラを持っているスタッフが、口パクで“生中継! 生中継!”と口パクしている。
「クロック、お前は空気読め。」
「あぁー、何が?」
「…ガンバリマス、オウエンシテクダサイ。
つーことで、あっちのロールウィッツのインタビューをしてくれよ。」
つーことで、あっちのロールウィッツのインタビューをしてくれよ。」
一瞬、大滝やキョーコだけでなく、スタッフからも『助かった』という表情が伺えた。
「OK! 行くぜキョーコ!」
「OK! エビル!」
空気も読めないヤツへのインタビューを早々と切り上げ、ロールウィッツへと向う。
「今日は勝てるか? ウィッツ!」
「バッカモノがァッ!
このウェンディエゴ様がシロートに負けるわけがあるかァッ!
別のデュエリストに賭けるのは、ドブに捨てるのも同じことッ!
勝って魅せる、それはこのウェンディエゴ様だッ! ロールウィッツ・ウェンディエゴだ!」
このウェンディエゴ様がシロートに負けるわけがあるかァッ!
別のデュエリストに賭けるのは、ドブに捨てるのも同じことッ!
勝って魅せる、それはこのウェンディエゴ様だッ! ロールウィッツ・ウェンディエゴだ!」
このロールウィッツという男、インタビューを受けるには向いている男だった。
天性のパフォーマー、と言おうか。
天性のパフォーマー、と言おうか。
「さて! これから10分間、賭けの時間だ!
トレーディング・リストに基づき、登録しているカードを賭けてくれ!」
トレーディング・リストに基づき、登録しているカードを賭けてくれ!」
カメラのスタッフが指を上げた合図に続き、エビル大滝やエヴォルテクターキョーコの肩から力が抜けた。
「ジュフさん! やっている間はあくまでもエヴォルテクター・キョーコです!
ちゃんとキャラクターは守ってもらわないと困ります!」
ちゃんとキャラクターは守ってもらわないと困ります!」
「あぁー、悪いことしちまったか?
ところでよ、さっき最後に言ってた『トレーディング・リスト』ってなんだ?」
ところでよ、さっき最後に言ってた『トレーディング・リスト』ってなんだ?」
「参加するお客様は事前にカードを管理センターに預けていただきます。
そしてネットのギャンブルで特定の方に好きなだけカードを賭けてもらいます。
賭けに勝ったら、賭けたカードを金銭レートに可変し、同等と思われるカードを得ます。」
そしてネットのギャンブルで特定の方に好きなだけカードを賭けてもらいます。
賭けに勝ったら、賭けたカードを金銭レートに可変し、同等と思われるカードを得ます。」
さほど悪いと思ってないクロックにさほど気を悪くした様子も無く、今日子はテキパキと説明してみせた。
「あぁー…よくわかんねぇな。」
「細かいルールを説明すると10分じゃ終らないんですが…。
現金を賭けるよりもゲーム感覚が強くて人気なんですよ、知りませんか?」
現金を賭けるよりもゲーム感覚が強くて人気なんですよ、知りませんか?」
「あぁー、知らねぇなあ。」
レアハンターならば、その辺りの事情に詳しくなければならないはずなのだが。
クロックは『ただ強いレアハンター』であり、正念党の他業務も兼任しているホーティックやエビエスとは異なるらしい。
クロックは『ただ強いレアハンター』であり、正念党の他業務も兼任しているホーティックやエビエスとは異なるらしい。
「とにかく、賭けが終る10分後までにスタート地点に移動しないと。
デュエルのルールは大丈夫ですね?」
デュエルのルールは大丈夫ですね?」
「あぁー、そっちもよくわかんねぇな。」
「そっちは俺が覚えてる。 クロックはトライクの運転だけやってろ。
ようはバイクの停止がサレンダー扱い、チェックポイントを先に通過したら1ドロー、だろ?」
ようはバイクの停止がサレンダー扱い、チェックポイントを先に通過したら1ドロー、だろ?」
「ええ、ジュフさんたちは普通に走っていただいて結構です。」
どうにも、引っかかる言い回しだった。
「そういえば、さっきロールウィッツはハンデをつけるって言い方してたけど…具体的になにをするんだ?」
「それは、これです。」
今日子が取り出したのは、一枚の魔法カードだった。
| 闇 | フィールド魔法 | ||
| フィールド上に表側表示で存在する悪魔族・魔法使い族モンスターの攻撃力・守備力は200ポイントアップする。 フィールド上に表側表示で存在する天使族モンスターの攻撃力・守備力は200ポイントダウンする。 |
|||
「…それが、何か?」
「このカードはデュエルディスクとは別のソリッドビジョンシステムにセットされます。
このソリッドビジョンシステムは、ロールウィッツのライフが減れば減るほど強く実体化します。」
このソリッドビジョンシステムは、ロールウィッツのライフが減れば減るほど強く実体化します。」
その説明に驚く刃咲に、首をかしげるクロック。
「あぁー、つまり、ライフが減るとロールウィッツの悪魔族や魔法使い族が強化される、ってことか?」
「いえ、実体化はしても効果は無視されます。
デュエルディスクにセットされていない無関係のカードですから。」
デュエルディスクにセットされていない無関係のカードですから。」
「あぁー、じゃあ、なんの…?」
「目隠し、か?」
刃咲は、半分信じられないような、半分怖そうな、そんな神妙な表情になっていた。
「そうです、ライフが減るほど〔闇〕で視界が悪化します。
そうすればスピードを出せなくなり、サレンダーもありえます。」
そうすればスピードを出せなくなり、サレンダーもありえます。」
「つまり、ハンディってのはネット配信での建前、実は普通に走るんだな?」
「ハーッハッハ! そんなセコいマネをこのウェンディエゴ様がするわけがないだろうがァっ!」
答えたのは今日子ではなく、ハーレーを転がすロールウィッツだった。
「ハンデとしては軽すぎたか?」
「そうじゃない! この先はガードレールもない、普通に危険な道。
そんな道を目隠し運転なんて…マジで死ぬぞ!」」
そんな道を目隠し運転なんて…マジで死ぬぞ!」」
「危なくないデュエルなんて、面白いか?」
「…何?」
「失敗したら痛い目みるから面白いんじゃねぇか?
わからねぇかなぁ、ガキにはよ?」
わからねぇかなぁ、ガキにはよ?」
刃咲を見下すように、自分が正しいと信じて疑わない男がそこに居た。
少年は悟った、こいつは伊達じゃない、マジだ、と。
少年は悟った、こいつは伊達じゃない、マジだ、と。
-