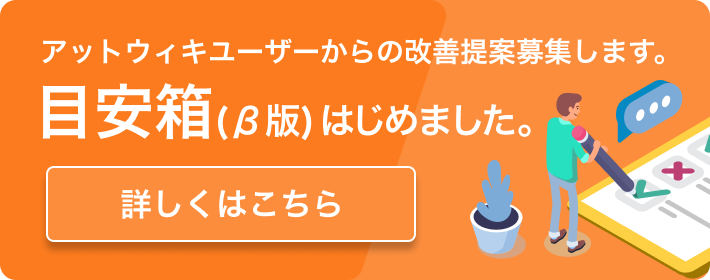CMWC NONEL COMPETITION
アンハッピー・エンド2
最終更新:
cmwc
-
view
CMWC NONEL COMPETITION6
アンハッピー・エンド(後編)
作:江沢 稽
「究」の章
病院ですべて話す、という加寿内を信じて、依頼人と私は穴にいた二人の搬送された病室の一室にいた。病院まで私はつき添いとして救急車に同乗していった。怪我人から目を離すな、という指示に従う意味でもこれは好都合だった。法螺貝の婆さんには加寿内から連絡がいったのだろう。
狭い病室のベッドにいるのは二人。私たちが穴の底にいるのを発見した男女だ。女性のほうは穴居純子。髪の長いこのキャリアウーマンを絵に描いたような利発そうな女性は、金成満の有能なブレーンの一人だという。気の弱そうな男性のほうは、やはり金成家の書生。名前は下部久というらしい。加寿内から聞かされた新しい情報はそれくらいのものだった。
気まずい空気が漂うなか、ようやく探偵が到着した。
「どうも、お二人ともお加減はいかがですか」
下部が口を開く。
「探偵さんですか。あなたのおかげで穴居さんも私も見つけてもらえたそうで。本当にありがとうございます」
「いえいえ、感謝するならこちらの法螺貝さんにお願いしますよ」
「あなたが。それはそれはどうもありがとうございます」
下部が恐縮したように顔をゆがめる。一方、穴居はショックから立ち直っていないのか、焦点の定まっていないような視線をなんとなく加寿内のほうに向けているだけでまだ一言も言葉を発していない。
「穴居さん、下部さん。実はお二人に聞いていただきたい話があるのです。煎餅をもってきましたので、それを食べながらでもどうぞ」
そう前置きをして、加寿内は法螺貝が語った奇天烈な話を聞かせた。不思議だ、という顔をしながらも落ち着いて話に耳を傾けていた下部とは対照的に穴居はひどく驚いていた。無理もない。とても信じられないような荒唐無稽な物語だ。
「この風変わりな話を私はこう解釈しました。すべては本当に起きたことだ、と」
「確かに私は穴居さんを見つけて助けを呼ぼうとして穴に落ちてしまいましたが、スパイなんかではありませんよ。穴居さんもアリスの黒ウサギなんかではないですし、金成社長も地下帝国と組んでいるわけではありません」
はははと笑う下部を無視して、加寿内は淡々と語りだした。
「最大の謎はアリスの黒ウサギです。こいつの特徴は片耳ということです。穴居さん、あなたのその長い髪をヘアゴムかなにかを使い、後ろで一本縛りにしたら、そして走ったら、月明かりにうつるそのシルエットは片耳のウサギが走っているように見えませんかね」
穴居はぽかんと口を開けたままでいる。
「そして、あなたが全身黒づくめの格好でいたら、片耳の黒ウサギの出来上がりじゃないですか」
「加寿内、でも、さすがに顔が黒というのは」
「大き目の色の濃いサングラスをかけて、黒いスカーフのようなもので口元を覆っていたら顔も黒くなるね」
「そりゃそうだろうけど、そんな人目を忍ぶようなことをする理由がないじゃないか。それに懐中時計はどうだ。今時、そんなレトロなものを」
「あれは懐中時計じゃなくてストップウォッチさ。見たことあるだろう、陸上競技なんかでコーチが使う首にかけるタイプのを。子どものころ、体育の先生が持っていなかったかい。あれを遠目から見たら、懐中時計になる」
「そのへんはなんとでもいいようがあるさ。どうして本家のアリスのウサギみたいに頻繁に時計を気にして何度もバタバタ穴から出たり入ったりしていたかが説明できないと」
「あれはまさしく時間を気にしていたんだよ。時間をはかってリハーサルをしていたんだ。何度も何度も毎晩毎晩ね」
「なんのリハーサルだよ」
「少しは自分で考えてみろよ。ウサギはなにをしていた? まず縄梯子を使って穴に入る。そして、しばらくすると縄梯子を使って穴から出てくる。次は屋敷のほうへダッシュ。そして、駆け戻ってくる。この一連の動作を時間をはかりながらくり返していたね。そして、昨夜はなにが起きた? 九時過ぎに縄梯子を使って穴にもぐる。九時半ごろ、下部さんがやってくる。下部さんが助けを呼びにいこうとして落ちる。この時間に下部さんが来るのはいつものことだが、穴に落ちたのはアクシデントだ。しばらくすると縄梯子を使ってウサギは穴から出てくる。なぜか縄梯子を穴に投げる。そして、屋敷のほうへ走る。しばらくすると駆け戻ってくる。さぁ、そして、なにが起こった?」
「いつものようにまた穴に入った」
「違うね。リハーサルとの大きな違いがあったろう。昨夜のこのときだけはウサギは縄梯子を使わずに穴に飛び込んだんだ」
「それはそうだろう。だって、穴に投げてしまったんだから縄梯子は使えない」
「使えない、のではなく、使わなかったのじゃないか」
「どうしてそんなことを? 穴に飛び込んだら怪我をするに決まっている」
「そうだよ、わかりきったことさ。だから、飛び込んだ奴はそれを承知でそうしたんだ」
「そんな馬鹿な。何度もいうけど、そんなことをしたらただじゃ済まない」
「そうさ、だから、ウサギは怪我をしたかったのさ」
「なぜ?」
「そうすれば、アリバイが偽造できるからさ」
「アリバイだって!」
「そうだ。いいかい、この騒ぎにおいて下部さんが穴に落ちたことはアクシデントとして考えなければならないんだよ。下部さんが穴に落ちなかったら、どうなった? 穴居さんのところにはまもなく助けが来るだろう」
「そうだね」
「助けが来るまでのわずかな時間で悪事を行ったらどうなる。本当は怪我をしていないのに、穴のなかにいることを発見させることで、すでに負傷していると誤解させる。下部さんが助けを呼びに穴を離れたところで、用意してあった縄梯子を使って脱出。そして、素早く犯行を済ませ、助けが来ないうちに大急ぎで再び穴に戻る。その際、今度は本当に穴に落ちてねんざでもすれば、最初に発見されたときから怪我をして穴から出られなかったと思わせることができ、アリバイが偽造できるだろう」
「待てよ、そのアイデアには穴がある」
「穴? これ以上、穴を増やしてどうするんだい」
「茶化すのはよせ。いいか、犯行時刻が最初の発見後であると明確にされない限り、そのアリバイは無意味だ」
「こりゃ驚いた。君にしては鋭いじゃないか。そうだよ。だから、犯人は凶行の時間を明確にするため、発砲音を聞かせるため、拳銃という凶器を用いたんだ」
「拳銃! でも、誰もそんな音は聞いちゃいないし、誰が撃たれたって……あ、そうか、まさか、金成さんが撃たれたんじゃ」
「どうした、さえているじゃないか。頭でも打ったかい。そのまさかだよ」
「でも、音は。発砲音は誰も聞いていないじゃないか。あんな広い屋敷じゃ近隣の住人に音を聞かせるのは無茶だ」
「君も頭の固い奴だな。発砲音は下部さんに聞かせる計画だったんだ。でも、アクシデントでそれは失敗した。そうですね、穴居さん」
問いかけにも穴居は無表情のままで黙っている。
「穴の底であなたは途方に暮れたことでしょう。毎日、九時半ごろに穴のところを見回りに来る下部さんはペースメーカー利用者だから携帯電話を持っていない。だから、その場で救急車を呼ばれることはなく、必ず助けを呼ぶ電話をかけに屋敷に戻る。理想的なカモだった。計画どおり、下部さんは穴であなたを発見し、助けを呼びにいった。あなたは練習したように屋敷に急ぎ、金成氏に発砲。穴に飛び降りた。ところがまもなく来るはずの助けが一向に来ない。下部さんまでもが穴に落ちてしまったからです。そのまま、夜が明けた」
「もし、そうだとして」
ここで穴居純子がようやく口を開いた。初めて耳にした彼女の声は女性的な顔立ちに似合わず、低い男のようなものだった。
「もし、そうだとして、証拠はあるのですか。私がそんなことをしたという証拠が」
「こんな計画を立てるあなたのことだ。当然、気づいていらっしゃるのでしょう。証拠があることには」
「なんでしょう?」
そらとぼけるという感じで穴居は尋ねる。
「あなたの計画では後で処分するはずだった。だが、この状況では処分はできません。探せば、必ず見つかるはずです。あなたが落ちた穴の底には、あなたが変装に使った後で埋めた黒い衣装と縄梯子、それに凶器の拳銃、そして、それらを隠す穴を掘るために使ったスコップがあるはずです」
視線という視線が穴居純子に集まる。やがてため息を一つ吐くと、静かに女は語りだした。
「ついてないなぁ。昔っからそうなんですよ、私、つくづくついていないんです。踏み台にするはずだった青年実業家は思った以上に切れ者で利用することもできず、会社を乗っ取るためにと入念に準備していたアリバイ工作は結局、無意味。計画は予想外のところから破綻。しかも、文字どおりの痛い目にあうなんてね。それもリハーサルの段階から本番まですべて嘘つき婆に見られていたなんてね。加えて加寿内中なんて探偵まで出てくるとはね。ほんと、ついてない。まぁ、考えようによっちゃついてたのかな。あのまま、穴の底で痛い思いをし続けることになったかもしれないと考えるとね。この脚じゃ、ここから逃げ切れないだろうし。あぁあ、リスク背負ってせっかく殺したのにな。刑務所いくだけじゃない。これじゃあ、社長を殺し損じゃない」
「本当についていないと思ってますか」
「思わずにはいられないわよ。これ以上、ついてないことなんて人生で起こらないんじゃないの」
「これを見てもそう思いますかね」
すっとドアが開いて、どこかで見たことのある男性が病室に入ってきた。
「しゃ、社長」
下部が震える声で叫んだ。加寿内が微笑みながら金成に語りかける。
「社長、わざわざすみません。そうそう、可愛がってらっしゃるリンダちゃんは、ひょんなことからボクの事務所で保護することになりました。今、大家さんに預かってもらっていますので、社長が退院されるまではこちらで責任を持って面倒みさせてもらいます」
リンダ? ひょっとしてあの猿のことか。そんなことを考えているとヒステリックな笑い声が聞こえてきた。穴居純子だ。
「なんだ、ほんとについてないんだ。『人を呪わば穴二つ』か。よくいったものだわ。結局、私、社長も殺せなかったんだぁ。わざわざ一発、脚に撃ち込んで動けなくさせてから心臓を狙ったのに。それでもダメだったか。ちゃんと当たったと思ったんだけどな」
「ちゃんと当たったんですよ」
加寿内の言葉にきょとんとする穴居。その鼻面に突きつけるように加寿内はあるものを示した。
「これは……」
加寿内の手にした小さな透明のビニール袋には、なにかの欠片が入っていた。
「これはベナンチョ君という留学生が開発した《ムエタイのキックでも割れない》かた焼き煎餅です。金成社長のもらったこの煎餅だけはどういうわけかほかの製品と比べても非常にかたかった。防弾チョッキ並みにね。しかも、運よく金成社長はこいつを左の胸ポケットに突っ込んだままでいた。いやぁ、しかし、恐るべきかたさです。一緒にポケットに入っていた携帯電話の見事な壊れっぷりから銃撃の衝撃はうかがいしることができますが、まさか煎餅がね」
おどけるように肩をすくめてしゃべる加寿内に金成がいう。
「うちの占い師に予言されてたんですよ。『遠からず銃撃される。幸運の鍵は煎餅屋』って。まさか本当に当たるとは。クビにするつもりでしたが、大事に置いておくことにしますよ」
そう笑う金成を見てから天を仰ぎ、穴居はぼやく。
「あーあ、ほんとついてないんだ。私って」
「いいえ、ついてますよ。少なくともあなたは人殺しじゃない。不幸はもう……」
狭い病室のベッドにいるのは二人。私たちが穴の底にいるのを発見した男女だ。女性のほうは穴居純子。髪の長いこのキャリアウーマンを絵に描いたような利発そうな女性は、金成満の有能なブレーンの一人だという。気の弱そうな男性のほうは、やはり金成家の書生。名前は下部久というらしい。加寿内から聞かされた新しい情報はそれくらいのものだった。
気まずい空気が漂うなか、ようやく探偵が到着した。
「どうも、お二人ともお加減はいかがですか」
下部が口を開く。
「探偵さんですか。あなたのおかげで穴居さんも私も見つけてもらえたそうで。本当にありがとうございます」
「いえいえ、感謝するならこちらの法螺貝さんにお願いしますよ」
「あなたが。それはそれはどうもありがとうございます」
下部が恐縮したように顔をゆがめる。一方、穴居はショックから立ち直っていないのか、焦点の定まっていないような視線をなんとなく加寿内のほうに向けているだけでまだ一言も言葉を発していない。
「穴居さん、下部さん。実はお二人に聞いていただきたい話があるのです。煎餅をもってきましたので、それを食べながらでもどうぞ」
そう前置きをして、加寿内は法螺貝が語った奇天烈な話を聞かせた。不思議だ、という顔をしながらも落ち着いて話に耳を傾けていた下部とは対照的に穴居はひどく驚いていた。無理もない。とても信じられないような荒唐無稽な物語だ。
「この風変わりな話を私はこう解釈しました。すべては本当に起きたことだ、と」
「確かに私は穴居さんを見つけて助けを呼ぼうとして穴に落ちてしまいましたが、スパイなんかではありませんよ。穴居さんもアリスの黒ウサギなんかではないですし、金成社長も地下帝国と組んでいるわけではありません」
はははと笑う下部を無視して、加寿内は淡々と語りだした。
「最大の謎はアリスの黒ウサギです。こいつの特徴は片耳ということです。穴居さん、あなたのその長い髪をヘアゴムかなにかを使い、後ろで一本縛りにしたら、そして走ったら、月明かりにうつるそのシルエットは片耳のウサギが走っているように見えませんかね」
穴居はぽかんと口を開けたままでいる。
「そして、あなたが全身黒づくめの格好でいたら、片耳の黒ウサギの出来上がりじゃないですか」
「加寿内、でも、さすがに顔が黒というのは」
「大き目の色の濃いサングラスをかけて、黒いスカーフのようなもので口元を覆っていたら顔も黒くなるね」
「そりゃそうだろうけど、そんな人目を忍ぶようなことをする理由がないじゃないか。それに懐中時計はどうだ。今時、そんなレトロなものを」
「あれは懐中時計じゃなくてストップウォッチさ。見たことあるだろう、陸上競技なんかでコーチが使う首にかけるタイプのを。子どものころ、体育の先生が持っていなかったかい。あれを遠目から見たら、懐中時計になる」
「そのへんはなんとでもいいようがあるさ。どうして本家のアリスのウサギみたいに頻繁に時計を気にして何度もバタバタ穴から出たり入ったりしていたかが説明できないと」
「あれはまさしく時間を気にしていたんだよ。時間をはかってリハーサルをしていたんだ。何度も何度も毎晩毎晩ね」
「なんのリハーサルだよ」
「少しは自分で考えてみろよ。ウサギはなにをしていた? まず縄梯子を使って穴に入る。そして、しばらくすると縄梯子を使って穴から出てくる。次は屋敷のほうへダッシュ。そして、駆け戻ってくる。この一連の動作を時間をはかりながらくり返していたね。そして、昨夜はなにが起きた? 九時過ぎに縄梯子を使って穴にもぐる。九時半ごろ、下部さんがやってくる。下部さんが助けを呼びにいこうとして落ちる。この時間に下部さんが来るのはいつものことだが、穴に落ちたのはアクシデントだ。しばらくすると縄梯子を使ってウサギは穴から出てくる。なぜか縄梯子を穴に投げる。そして、屋敷のほうへ走る。しばらくすると駆け戻ってくる。さぁ、そして、なにが起こった?」
「いつものようにまた穴に入った」
「違うね。リハーサルとの大きな違いがあったろう。昨夜のこのときだけはウサギは縄梯子を使わずに穴に飛び込んだんだ」
「それはそうだろう。だって、穴に投げてしまったんだから縄梯子は使えない」
「使えない、のではなく、使わなかったのじゃないか」
「どうしてそんなことを? 穴に飛び込んだら怪我をするに決まっている」
「そうだよ、わかりきったことさ。だから、飛び込んだ奴はそれを承知でそうしたんだ」
「そんな馬鹿な。何度もいうけど、そんなことをしたらただじゃ済まない」
「そうさ、だから、ウサギは怪我をしたかったのさ」
「なぜ?」
「そうすれば、アリバイが偽造できるからさ」
「アリバイだって!」
「そうだ。いいかい、この騒ぎにおいて下部さんが穴に落ちたことはアクシデントとして考えなければならないんだよ。下部さんが穴に落ちなかったら、どうなった? 穴居さんのところにはまもなく助けが来るだろう」
「そうだね」
「助けが来るまでのわずかな時間で悪事を行ったらどうなる。本当は怪我をしていないのに、穴のなかにいることを発見させることで、すでに負傷していると誤解させる。下部さんが助けを呼びに穴を離れたところで、用意してあった縄梯子を使って脱出。そして、素早く犯行を済ませ、助けが来ないうちに大急ぎで再び穴に戻る。その際、今度は本当に穴に落ちてねんざでもすれば、最初に発見されたときから怪我をして穴から出られなかったと思わせることができ、アリバイが偽造できるだろう」
「待てよ、そのアイデアには穴がある」
「穴? これ以上、穴を増やしてどうするんだい」
「茶化すのはよせ。いいか、犯行時刻が最初の発見後であると明確にされない限り、そのアリバイは無意味だ」
「こりゃ驚いた。君にしては鋭いじゃないか。そうだよ。だから、犯人は凶行の時間を明確にするため、発砲音を聞かせるため、拳銃という凶器を用いたんだ」
「拳銃! でも、誰もそんな音は聞いちゃいないし、誰が撃たれたって……あ、そうか、まさか、金成さんが撃たれたんじゃ」
「どうした、さえているじゃないか。頭でも打ったかい。そのまさかだよ」
「でも、音は。発砲音は誰も聞いていないじゃないか。あんな広い屋敷じゃ近隣の住人に音を聞かせるのは無茶だ」
「君も頭の固い奴だな。発砲音は下部さんに聞かせる計画だったんだ。でも、アクシデントでそれは失敗した。そうですね、穴居さん」
問いかけにも穴居は無表情のままで黙っている。
「穴の底であなたは途方に暮れたことでしょう。毎日、九時半ごろに穴のところを見回りに来る下部さんはペースメーカー利用者だから携帯電話を持っていない。だから、その場で救急車を呼ばれることはなく、必ず助けを呼ぶ電話をかけに屋敷に戻る。理想的なカモだった。計画どおり、下部さんは穴であなたを発見し、助けを呼びにいった。あなたは練習したように屋敷に急ぎ、金成氏に発砲。穴に飛び降りた。ところがまもなく来るはずの助けが一向に来ない。下部さんまでもが穴に落ちてしまったからです。そのまま、夜が明けた」
「もし、そうだとして」
ここで穴居純子がようやく口を開いた。初めて耳にした彼女の声は女性的な顔立ちに似合わず、低い男のようなものだった。
「もし、そうだとして、証拠はあるのですか。私がそんなことをしたという証拠が」
「こんな計画を立てるあなたのことだ。当然、気づいていらっしゃるのでしょう。証拠があることには」
「なんでしょう?」
そらとぼけるという感じで穴居は尋ねる。
「あなたの計画では後で処分するはずだった。だが、この状況では処分はできません。探せば、必ず見つかるはずです。あなたが落ちた穴の底には、あなたが変装に使った後で埋めた黒い衣装と縄梯子、それに凶器の拳銃、そして、それらを隠す穴を掘るために使ったスコップがあるはずです」
視線という視線が穴居純子に集まる。やがてため息を一つ吐くと、静かに女は語りだした。
「ついてないなぁ。昔っからそうなんですよ、私、つくづくついていないんです。踏み台にするはずだった青年実業家は思った以上に切れ者で利用することもできず、会社を乗っ取るためにと入念に準備していたアリバイ工作は結局、無意味。計画は予想外のところから破綻。しかも、文字どおりの痛い目にあうなんてね。それもリハーサルの段階から本番まですべて嘘つき婆に見られていたなんてね。加えて加寿内中なんて探偵まで出てくるとはね。ほんと、ついてない。まぁ、考えようによっちゃついてたのかな。あのまま、穴の底で痛い思いをし続けることになったかもしれないと考えるとね。この脚じゃ、ここから逃げ切れないだろうし。あぁあ、リスク背負ってせっかく殺したのにな。刑務所いくだけじゃない。これじゃあ、社長を殺し損じゃない」
「本当についていないと思ってますか」
「思わずにはいられないわよ。これ以上、ついてないことなんて人生で起こらないんじゃないの」
「これを見てもそう思いますかね」
すっとドアが開いて、どこかで見たことのある男性が病室に入ってきた。
「しゃ、社長」
下部が震える声で叫んだ。加寿内が微笑みながら金成に語りかける。
「社長、わざわざすみません。そうそう、可愛がってらっしゃるリンダちゃんは、ひょんなことからボクの事務所で保護することになりました。今、大家さんに預かってもらっていますので、社長が退院されるまではこちらで責任を持って面倒みさせてもらいます」
リンダ? ひょっとしてあの猿のことか。そんなことを考えているとヒステリックな笑い声が聞こえてきた。穴居純子だ。
「なんだ、ほんとについてないんだ。『人を呪わば穴二つ』か。よくいったものだわ。結局、私、社長も殺せなかったんだぁ。わざわざ一発、脚に撃ち込んで動けなくさせてから心臓を狙ったのに。それでもダメだったか。ちゃんと当たったと思ったんだけどな」
「ちゃんと当たったんですよ」
加寿内の言葉にきょとんとする穴居。その鼻面に突きつけるように加寿内はあるものを示した。
「これは……」
加寿内の手にした小さな透明のビニール袋には、なにかの欠片が入っていた。
「これはベナンチョ君という留学生が開発した《ムエタイのキックでも割れない》かた焼き煎餅です。金成社長のもらったこの煎餅だけはどういうわけかほかの製品と比べても非常にかたかった。防弾チョッキ並みにね。しかも、運よく金成社長はこいつを左の胸ポケットに突っ込んだままでいた。いやぁ、しかし、恐るべきかたさです。一緒にポケットに入っていた携帯電話の見事な壊れっぷりから銃撃の衝撃はうかがいしることができますが、まさか煎餅がね」
おどけるように肩をすくめてしゃべる加寿内に金成がいう。
「うちの占い師に予言されてたんですよ。『遠からず銃撃される。幸運の鍵は煎餅屋』って。まさか本当に当たるとは。クビにするつもりでしたが、大事に置いておくことにしますよ」
そう笑う金成を見てから天を仰ぎ、穴居はぼやく。
「あーあ、ほんとついてないんだ。私って」
「いいえ、ついてますよ。少なくともあなたは人殺しじゃない。不幸はもう……」
END
Copyright (c) 2007 江沢 稽 All rights reserved.
Copyright (c) 2007 江沢 稽 All rights reserved.