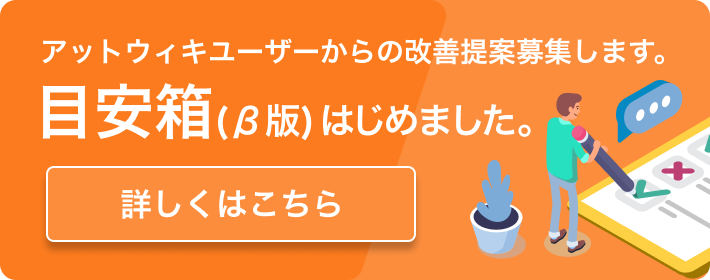CMWC NONEL COMPETITION
千切れた子供
最終更新:
cmwc
-
view
CMWC NONEL COMPETITION4
千切れた子供
~ある霊感とその要因における
『ノエシス』の解明~
『ノエシス』の解明~
塩瀬絆斗
0、千切れた子供
よく覚えている。といってどこまでも細かく覚えているのではない。小学二年生の終わり頃だった。
校舎の二階の廊下は濃い紫色をしていた。中央にはオレンジ色の破線が走っている。踊り場からは直角に二つの廊下が出ていて、他にトイレ、階段、特別教室への入り口が面していた。
そこを通りかかった。
何をしようとしてどこに行こうとしていたのか分からない。放課後だった。しかし、それにしては人気がなさ過ぎたような気がする。廊下はしーんと静まり返っていた。もしかすると、放課後はいつもああだったのかもしれない。一緒にいたのは岡嶋孝太と響隆法<ひびきりゅうほう>だった。
最初に「それ」を見つけたのは僕だった。何かが視界の隅でちらちらとしていたのを覚えている。
ふとそちらを見た。一瞬、僕の体はそこに釘付けされてしまったかのようになった。白と灰色のボーダーの服を着た男の子がいた。ズボンは、分からない。何せ、下半身はなかった。どう言い表せばいいのだろう。男の子の上半身が廊下から生えているといった感じだった。両手が足の代わりをしていて、それで上半身を引きずるように動いているようだった。同じくらいの年齢だろうかと思ったが、少し遠くだったから子供の顔はよく見えなかった。だからのっぺらとした顔は、言いようのない不気味さを誇っていた。その虚ろな様子。体ごと真っ直ぐとこちらを見ているようだった。
大声ではなかったが僕は悲鳴をあげた。
「ああ……あれ」
全員がそちらを見る。一目見て、僕たちはその場から逃げ出した。怖かった。一秒でも早くそこからいなくなりたかった。得体の知れない何かが僕たちを突き動かしていた。
校舎の二階の廊下は濃い紫色をしていた。中央にはオレンジ色の破線が走っている。踊り場からは直角に二つの廊下が出ていて、他にトイレ、階段、特別教室への入り口が面していた。
そこを通りかかった。
何をしようとしてどこに行こうとしていたのか分からない。放課後だった。しかし、それにしては人気がなさ過ぎたような気がする。廊下はしーんと静まり返っていた。もしかすると、放課後はいつもああだったのかもしれない。一緒にいたのは岡嶋孝太と響隆法<ひびきりゅうほう>だった。
最初に「それ」を見つけたのは僕だった。何かが視界の隅でちらちらとしていたのを覚えている。
ふとそちらを見た。一瞬、僕の体はそこに釘付けされてしまったかのようになった。白と灰色のボーダーの服を着た男の子がいた。ズボンは、分からない。何せ、下半身はなかった。どう言い表せばいいのだろう。男の子の上半身が廊下から生えているといった感じだった。両手が足の代わりをしていて、それで上半身を引きずるように動いているようだった。同じくらいの年齢だろうかと思ったが、少し遠くだったから子供の顔はよく見えなかった。だからのっぺらとした顔は、言いようのない不気味さを誇っていた。その虚ろな様子。体ごと真っ直ぐとこちらを見ているようだった。
大声ではなかったが僕は悲鳴をあげた。
「ああ……あれ」
全員がそちらを見る。一目見て、僕たちはその場から逃げ出した。怖かった。一秒でも早くそこからいなくなりたかった。得体の知れない何かが僕たちを突き動かしていた。
1、再会
一人暮らしだから実家に帰るのは久し振りだ。特に深い感慨があるわけではなかったが、故郷というものをはじめて意識したような気がした。ほんの数年だから当然といえば当然なのだが、街並みは相変わらずである。心のどこかで、変化を期待していたのかもしれない。
H駅の改札を出ると、暑さに眩しさが加わってきた。夏が苦手な僕としては身を焼かれる思いだ。カランカランと遮断機が大声を上げる中をS電鉄の白い車体が遠ざかっていく。横っ腹の緑のラインが目に映えた。踏切を渡り、国道を行く。この町は中途半端な大きさの割りに交通量は半端ではない。町のど真ん中を突き抜ける国道からは、逃げ水の中から湧いて出るように光る車がやってくる。その道を脇にそれ、狭い道を行くと小学校が見えてきた。母校のK小学校だ。
今日は、その同窓会だった。
H駅の改札を出ると、暑さに眩しさが加わってきた。夏が苦手な僕としては身を焼かれる思いだ。カランカランと遮断機が大声を上げる中をS電鉄の白い車体が遠ざかっていく。横っ腹の緑のラインが目に映えた。踏切を渡り、国道を行く。この町は中途半端な大きさの割りに交通量は半端ではない。町のど真ん中を突き抜ける国道からは、逃げ水の中から湧いて出るように光る車がやってくる。その道を脇にそれ、狭い道を行くと小学校が見えてきた。母校のK小学校だ。
今日は、その同窓会だった。
「まあ、なんだな、案外変わらないもんだね」
岡嶋は周囲を見回しながら言った。
三次会ともなると人も少なくなる。別個にグループが出来、それぞれ思い出話に花を咲かせている。岡嶋に答えたのは、例に漏れず全く変わった様子のない寺田学だった。
「だが、もう十年以上経つんだよなあ。早いよな」
「そりゃあ、過去を振り返るのなんて一瞬なんだから、短く感じるのは当たり前だろうね」
しれっとした様子でウーロン茶を口に運ぶ響。寺田はちらりと睨むと太い腕を彼の首に巻きつけた。
「お前も本当に変わらねえよな!」
「痛い痛い、やめろよ」
酒の入った寺田は豪快に笑う。そしてビールを響に勧めるのだが、素っ気ない返事が返ってくるばかりだ。
「お酒は駄目なんだよ。一滴も飲めない。まあ、飲めなくても困らないからいいんだけどね」
岡嶋はそんな二人を無視するかのように、うっとりとした目で僕のほうを見る。
「しかし、花村さんは相変わらず可愛かったね」
花村さんというのは当時クラスで一番の人気を誇った女子のことだ。しかし、
「結婚してたな」
「本当。早すぎだよねえ……」
岡嶋は残念そうな顔でグラスを一気に空ける。寺田もこちらの話に興味があるのか、響を放り出して、あり得ねーだとか叫んでいる。それを横目で見ながら、響は首を摩った。
「絆斗<はんと>は昔から女っ気がなかったけど、今はどうなの?」
「リュウ、お前はいつも一言多いんだよ」
このメンバーでその手の話に慣れているのは寺田だった。響は不服そうに腕を組んでいる。
「昔からガキ大将って案外もてるんだよね。不思議で堪らない」
岡嶋が大人しいと思ったら、彼は黙々と酒を流し込んでいた。僕は、恋愛の話は全然駄目だったから、無理矢理に話を変えようと(半ば必死に)切り出した。
「でもさ、この辺って全然変わらないよな。久し振りにS電鉄に乗ったけど、本当に変わらない。もっと変わるものだと思ってたけど」
すると、岡嶋がグラスを置いて僕を凝視した。顔が真っ赤である。元来見つめられるのが苦手な僕は、ついつい彼を睨みつけてしまった。
「なんだよ」
「いやね、そういえばこの前田原先生に会ったのを思い出してさ……」
「田原先生って誰だよ?」
寺田はもはやふんぞり返っていて、その口調も酔っているんだか素面なのか判断に苦しむ。彼に対しては、たいてい響のツッコミが入ることになっている。
「物覚えが悪いね。確か、二年二組だったか四組だったかの先生じゃなかったっけ。僕たちのクラスの隣だったことは覚えてるんだけど」
「いや、僕もよく覚えていないんだけど、確かに二年生のとき隣のクラスの担任だったんだよ。女の先生で……」
「中年の方? 若い方? 俺、若い方の先生は好きだった記憶がある」
寺田は必死に記憶を手繰り寄せるように眉間に皺を寄せて真剣な眼差しだ。僕は記憶力だけはいいから、そのどちらも覚えていた。
「田原先生はおばさんのほうだよ。若いのは小林先生。それで、田原先生がどうしたって?」
「死んだんじゃねえだろうな?」
「君は黙ってたほうがいいね。というより、岡ちゃんは『会った』って言っただろうが。ちゃんと人の話を聞きなよ」
岡嶋はグラスを干すと、新たな酒に手をかけて言う。
「いや、町でばったり会ってさ、向こうもなぜか僕のこと覚えてたみたいで一緒に飲みに行ったんだよ。そこでさ、初めて聞いたんだよ。ほら、田原先生って突然先生辞めちゃったじゃない。覚えてる? 確か、僕たちが三年になってすぐだったんだけど」
僕はうろ覚えだがその記憶はある。色々と面倒見のいい先生で、辞めてしまったのが寂しかったのだ。
そういえば、田原先生は図工の先生になりたかったという話を母だったか、とにかく大人に聞いたことがある。それが叶わなかったのは、確か、赤と緑の見分けがつかないせいだったという。色盲だったのだ。そのためか、田原先生は図工の先生と仲がよかったように思えた。
響は覚えているのかいないのか、何も言わなかったが、寺田は完全に忘れているようだった。いや、知らなかったとでもいうべきか。
「突然辞めちゃったんだよ。それってさ、田原先生の息子さんが亡くなっちゃったからなんだって。僕たちが二年生のときの冬に」
「そうなのか?!」
岡嶋は大きく頷く。少しふらついていていたが、大丈夫だろうか。
「うん。児童には言うべきことじゃないし、子供を見るのさえ辛くなっていたそうだよ。先生の息子さんは当時小学生だったから、あの頃僕たちと大体同じくらいの年だったんだろうね」
「あ、そうか。だから……」
岡嶋は周囲を見回しながら言った。
三次会ともなると人も少なくなる。別個にグループが出来、それぞれ思い出話に花を咲かせている。岡嶋に答えたのは、例に漏れず全く変わった様子のない寺田学だった。
「だが、もう十年以上経つんだよなあ。早いよな」
「そりゃあ、過去を振り返るのなんて一瞬なんだから、短く感じるのは当たり前だろうね」
しれっとした様子でウーロン茶を口に運ぶ響。寺田はちらりと睨むと太い腕を彼の首に巻きつけた。
「お前も本当に変わらねえよな!」
「痛い痛い、やめろよ」
酒の入った寺田は豪快に笑う。そしてビールを響に勧めるのだが、素っ気ない返事が返ってくるばかりだ。
「お酒は駄目なんだよ。一滴も飲めない。まあ、飲めなくても困らないからいいんだけどね」
岡嶋はそんな二人を無視するかのように、うっとりとした目で僕のほうを見る。
「しかし、花村さんは相変わらず可愛かったね」
花村さんというのは当時クラスで一番の人気を誇った女子のことだ。しかし、
「結婚してたな」
「本当。早すぎだよねえ……」
岡嶋は残念そうな顔でグラスを一気に空ける。寺田もこちらの話に興味があるのか、響を放り出して、あり得ねーだとか叫んでいる。それを横目で見ながら、響は首を摩った。
「絆斗<はんと>は昔から女っ気がなかったけど、今はどうなの?」
「リュウ、お前はいつも一言多いんだよ」
このメンバーでその手の話に慣れているのは寺田だった。響は不服そうに腕を組んでいる。
「昔からガキ大将って案外もてるんだよね。不思議で堪らない」
岡嶋が大人しいと思ったら、彼は黙々と酒を流し込んでいた。僕は、恋愛の話は全然駄目だったから、無理矢理に話を変えようと(半ば必死に)切り出した。
「でもさ、この辺って全然変わらないよな。久し振りにS電鉄に乗ったけど、本当に変わらない。もっと変わるものだと思ってたけど」
すると、岡嶋がグラスを置いて僕を凝視した。顔が真っ赤である。元来見つめられるのが苦手な僕は、ついつい彼を睨みつけてしまった。
「なんだよ」
「いやね、そういえばこの前田原先生に会ったのを思い出してさ……」
「田原先生って誰だよ?」
寺田はもはやふんぞり返っていて、その口調も酔っているんだか素面なのか判断に苦しむ。彼に対しては、たいてい響のツッコミが入ることになっている。
「物覚えが悪いね。確か、二年二組だったか四組だったかの先生じゃなかったっけ。僕たちのクラスの隣だったことは覚えてるんだけど」
「いや、僕もよく覚えていないんだけど、確かに二年生のとき隣のクラスの担任だったんだよ。女の先生で……」
「中年の方? 若い方? 俺、若い方の先生は好きだった記憶がある」
寺田は必死に記憶を手繰り寄せるように眉間に皺を寄せて真剣な眼差しだ。僕は記憶力だけはいいから、そのどちらも覚えていた。
「田原先生はおばさんのほうだよ。若いのは小林先生。それで、田原先生がどうしたって?」
「死んだんじゃねえだろうな?」
「君は黙ってたほうがいいね。というより、岡ちゃんは『会った』って言っただろうが。ちゃんと人の話を聞きなよ」
岡嶋はグラスを干すと、新たな酒に手をかけて言う。
「いや、町でばったり会ってさ、向こうもなぜか僕のこと覚えてたみたいで一緒に飲みに行ったんだよ。そこでさ、初めて聞いたんだよ。ほら、田原先生って突然先生辞めちゃったじゃない。覚えてる? 確か、僕たちが三年になってすぐだったんだけど」
僕はうろ覚えだがその記憶はある。色々と面倒見のいい先生で、辞めてしまったのが寂しかったのだ。
そういえば、田原先生は図工の先生になりたかったという話を母だったか、とにかく大人に聞いたことがある。それが叶わなかったのは、確か、赤と緑の見分けがつかないせいだったという。色盲だったのだ。そのためか、田原先生は図工の先生と仲がよかったように思えた。
響は覚えているのかいないのか、何も言わなかったが、寺田は完全に忘れているようだった。いや、知らなかったとでもいうべきか。
「突然辞めちゃったんだよ。それってさ、田原先生の息子さんが亡くなっちゃったからなんだって。僕たちが二年生のときの冬に」
「そうなのか?!」
岡嶋は大きく頷く。少しふらついていていたが、大丈夫だろうか。
「うん。児童には言うべきことじゃないし、子供を見るのさえ辛くなっていたそうだよ。先生の息子さんは当時小学生だったから、あの頃僕たちと大体同じくらいの年だったんだろうね」
「あ、そうか。だから……」
岡嶋は、酒量が多いくせにすぐ気分が悪くなる性質らしい。先程トイレに駆け込んだまま、もう数分が過ぎている。
「多分、あと三十分はトイレに引き篭もりだな」
そういうと、寺田はごくごくと喉を鳴らしてビールを流し込む。彼は酒にはめっぽう強いらしい。僕もよく顔には出ないといわれるが、寺田のようにがぶがぶと飲むわけにはいかない。一度、記憶を失ったことがあるので自重しているのだ。
話はどういうわけか、怪談じみた方向へと向かっていった。夏の夜のなせる業なのだろうか。
「“校長先生の影”ってあったよな」
「ああ、あの正門から見える窓のやつ?」
“校長先生の影”というのは窓に映った人影のことである。正門から見える窓に、まるで影が焼きついたようにくっきりと人の形が見えるのだ。これは今朝もいまだにそこにあった。当時広まった噂によれば、昔校長先生に立候補した人が二人いて、どうにも決め兼ねたのでじゃんけんで決めることにした。すると、当然ながら一人が負けてしまうのだが、その人は悔しさのあまり窓から飛び降り自殺を図ったのだ。彼は死亡し、怨念が窓に乗り移ったということである。
ただえさえ裏手に墓地のある学校だったから、怪談じみた話は腐るほどあったが、“校長先生の影”に関しては実際に目に見える分信憑性を持っていて、語り継がれているのだ。この“影”に関してはもう一つ驚くべき事実がある。実は、その影は外からしか見ることが出来ない。廊下からその窓を見ても何の変哲もなく、気付かないのだ。一説によれば、その窓を廊下側から触ると引き込まれてそのまま下に落ちてしまうという。
この話はどの学年でも尽きることはなかった。
しかし、僕はもっと恐ろしい出来事があったのを覚えている。
「あのさ、その窓のそばの廊下にお化けがいるのを見なかったっけ、俺たち」
「お化けえ?」
寺田は素っ頓狂な声を上げる。
「いや、学は多分見てないよ。俺とリュウと岡ちゃんだけだもん。ほら、リュウ、覚えてない? 下半身のない子供があの窓のそばにいたのを」
僕は自分でこう話していて鳥肌が立った。今思い出してもあのときのことは恐ろしい。鮮明に覚えている。響は目だけで天井を見上げている。暫くして青ざめた顔ををこちらに向けた。
「ああ、あれか……! あの足のない子供か!」
「多分、あと三十分はトイレに引き篭もりだな」
そういうと、寺田はごくごくと喉を鳴らしてビールを流し込む。彼は酒にはめっぽう強いらしい。僕もよく顔には出ないといわれるが、寺田のようにがぶがぶと飲むわけにはいかない。一度、記憶を失ったことがあるので自重しているのだ。
話はどういうわけか、怪談じみた方向へと向かっていった。夏の夜のなせる業なのだろうか。
「“校長先生の影”ってあったよな」
「ああ、あの正門から見える窓のやつ?」
“校長先生の影”というのは窓に映った人影のことである。正門から見える窓に、まるで影が焼きついたようにくっきりと人の形が見えるのだ。これは今朝もいまだにそこにあった。当時広まった噂によれば、昔校長先生に立候補した人が二人いて、どうにも決め兼ねたのでじゃんけんで決めることにした。すると、当然ながら一人が負けてしまうのだが、その人は悔しさのあまり窓から飛び降り自殺を図ったのだ。彼は死亡し、怨念が窓に乗り移ったということである。
ただえさえ裏手に墓地のある学校だったから、怪談じみた話は腐るほどあったが、“校長先生の影”に関しては実際に目に見える分信憑性を持っていて、語り継がれているのだ。この“影”に関してはもう一つ驚くべき事実がある。実は、その影は外からしか見ることが出来ない。廊下からその窓を見ても何の変哲もなく、気付かないのだ。一説によれば、その窓を廊下側から触ると引き込まれてそのまま下に落ちてしまうという。
この話はどの学年でも尽きることはなかった。
しかし、僕はもっと恐ろしい出来事があったのを覚えている。
「あのさ、その窓のそばの廊下にお化けがいるのを見なかったっけ、俺たち」
「お化けえ?」
寺田は素っ頓狂な声を上げる。
「いや、学は多分見てないよ。俺とリュウと岡ちゃんだけだもん。ほら、リュウ、覚えてない? 下半身のない子供があの窓のそばにいたのを」
僕は自分でこう話していて鳥肌が立った。今思い出してもあのときのことは恐ろしい。鮮明に覚えている。響は目だけで天井を見上げている。暫くして青ざめた顔ををこちらに向けた。
「ああ、あれか……! あの足のない子供か!」
僕と響は口々にあの話を語った。
「なんだ、その話?!」
寺田は面食らった表情で叫んだ。
無理もないだろう。あれは、見た者でなければ戦慄出来ない。あの薄暗い廊下の少し離れた場所に、ぽつねんとその男の子の上半身だけがあったのだ。今思い出しただけでも、肌が粟立つ。
すぐに逃げ出してしまったから分からないが、あの時男の子は崩れるようになった気がした。
「……あったね、そんなこと」
響は笑いを引きつらせている。僕はすかさず自分の考えを披露した。
「絶対あれは霊だよ。近くに“校長先生の影”もあったし……。俺たち霊を見たんだぜ」
あの子供を見たという話は、誰からも聞かなかったから、僕たちは特別だったのだろうと少し興奮した。あれを見たのは、おそらく僕たちだけなのだ。
寺田は体を仰け反らせて豪快に笑った。
「バーカ、そんなわけあるかよ!」
「じゃあ、なんだって言うんだよ! 本当にそれくらいしか可能性はないんだぜ」
「はあ……、お前は本当に短絡的で非現実的だな。もっとちゃんと考えてみろよ。その子供ってのはオットセイがやるみたいなポーズをしていただけだ。それを正面から見りゃあ、足がねえように見えるだろ。“オッサンの剃刀”だな、ははは」
「なんだよ、それ?!」
いとも簡単に答えを出されたような感じがあったのだが、意地ではなく反論の余地はあった。厳密にいえば、あったとはいえないかもしれない。
「そんな感じじゃなかったんだよ。そんなポーズしていれば俺にだってその場で分かったよ。本当に下半身がなかったんだ」
「そうかねえ。リュウはどうなんだ?」
響はなにやら思案しているようだった。暫く腕を組んでいると急に目を丸くした。そうして、うんだとかああだとか呟いてにやにや笑いを始めたが、どうしたのか突然真顔になって顎に手をやり俯いてしまった。
「なんだ、どうしたんだよ?」
響は我に返ったように顔を上げたが、沈んだ表情は崩さなかった。しかし、話したい気持ちはあるらしく、ジュースの入ったコップを弄びながら語り始めた。
寺田は面食らった表情で叫んだ。
無理もないだろう。あれは、見た者でなければ戦慄出来ない。あの薄暗い廊下の少し離れた場所に、ぽつねんとその男の子の上半身だけがあったのだ。今思い出しただけでも、肌が粟立つ。
すぐに逃げ出してしまったから分からないが、あの時男の子は崩れるようになった気がした。
「……あったね、そんなこと」
響は笑いを引きつらせている。僕はすかさず自分の考えを披露した。
「絶対あれは霊だよ。近くに“校長先生の影”もあったし……。俺たち霊を見たんだぜ」
あの子供を見たという話は、誰からも聞かなかったから、僕たちは特別だったのだろうと少し興奮した。あれを見たのは、おそらく僕たちだけなのだ。
寺田は体を仰け反らせて豪快に笑った。
「バーカ、そんなわけあるかよ!」
「じゃあ、なんだって言うんだよ! 本当にそれくらいしか可能性はないんだぜ」
「はあ……、お前は本当に短絡的で非現実的だな。もっとちゃんと考えてみろよ。その子供ってのはオットセイがやるみたいなポーズをしていただけだ。それを正面から見りゃあ、足がねえように見えるだろ。“オッサンの剃刀”だな、ははは」
「なんだよ、それ?!」
いとも簡単に答えを出されたような感じがあったのだが、意地ではなく反論の余地はあった。厳密にいえば、あったとはいえないかもしれない。
「そんな感じじゃなかったんだよ。そんなポーズしていれば俺にだってその場で分かったよ。本当に下半身がなかったんだ」
「そうかねえ。リュウはどうなんだ?」
響はなにやら思案しているようだった。暫く腕を組んでいると急に目を丸くした。そうして、うんだとかああだとか呟いてにやにや笑いを始めたが、どうしたのか突然真顔になって顎に手をやり俯いてしまった。
「なんだ、どうしたんだよ?」
響は我に返ったように顔を上げたが、沈んだ表情は崩さなかった。しかし、話したい気持ちはあるらしく、ジュースの入ったコップを弄びながら語り始めた。
2、『ノエシス』
「僕もあれは霊なんだと思う」
寺田のしかめっ面が笑える。理解しがたいといった素振りで彼は何かを言おうとしていたが、響は慌てたように、
「ただ、その霊というのがどういうものなのか説明できそうなんだ」
「どういうものなのかって、霊は霊だろ」
しかめっ面のままの寺田に響はゆっくりと首を振ってみせる。岡嶋はいまだにトイレに篭りっきりだ。大丈夫だろうか。
「いや、そうじゃないんだ。なんていうのか……その、どういう原因であれが現れたのか、分かったような気がするんだ」
響はそこまで言ってから反応を確かめるように僕たちのほうを向いた。たっぷりと間をとって続ける。
「これは多分、宗教学だったり大脳生理学の範疇の問題なんだと思うんだけど、霊感っていうのはある事柄を原因とする意識の変容状態(ASC)における幻覚の認識だと説明されるんだ」
「つまり、霊なんていないってわけじゃねえか」
僕など今の話すら理解できなかったのに、寺田はさらっと言ってのける。
「……それはちょっと難しい問題なんだけど。いる・いないというのが、どのレベルの意味なのか決めないとややこしくなるんだよね。簡単に言うと、意識の中には存在するということかな。でも、本当に霊はいるのかもしれない。まあ、それは別の話だ。
ある事柄っていうのは色々とあって、薬物だったり踊りだったりする。更に面白いのは、それが場所だったりする」
「場所?」
響は僕を見て頷く。ついでにジュースを飲み干し、指で唇を拭う。
「テレビとかで、ここは昔ある人物が非業の死を遂げた場所です、とか言って霊能者を連れて行くのがあるでしょう。そこで霊能者は、ああ見えますとか言うわけだよ。そういう意味の、場所ね」
寺田は鼻で笑う。
「ありゃあ、インチキだろ」
「君と喋っているとどうも話が脱線するな。インチキかどうかではなくて、インチキだとしても何故その霊能者がそういったことを言うのかが問題になる、という話もある。
とにかく、その場所がASCを引き起こし、幻覚を見させるきっかけとなるんだよ。でもさ、なんの関連性もないじゃない。場所と、脳内の変化がどう繋がっているのか。何らかの要素が、そのコネクションを作っていると考えるほかはない。じゃあ、その要素とはなんだろうか」
響は半ば独りごとのようにぶつぶつと言っている。
そんなことより、あの“千切れた子供”はどうなったのか。ここで響は講義を始めるつもりらしいが、一体なんのつもりだろう。何の関係があるのか。
淡々と語る響。
はじめは難色を示していたが、もうにやにやと笑っている寺田。
二人のレベルにまで届きそうもない。だから、僕は口を挟むどころか、どう相槌を打てばいいのかさえ分からなかった。
響は少し恥ずかしそうに口の端を緩めると、グラスを見つめながら、まるでそれに話しかけるようにしていた。
「僕はさ、結構暇だからこういうことを考えたりするんだけど、新しい概念を作ってみようと思ったんだ」
「そりゃあ、たいそうなこった」
「これは昔辞書をひいていて偶然見つけた言葉なんだけど……。ノエシスとノエマなんだ」
寺田はどういうわけか、かーっ、とかいう奇怪な音を立てて天井を仰いだ。
「意味は、ノエシスは意識の作用面。ノエマは意識の対象面。……だったと思う。本当は多分もっと複雑な言葉なんだろうけど、辞書にはそういう風にあるんだ。
この言葉を借りて、新しい物質の概念を考えてみたんだ。
『ノエシス』は、意識の発生時に生じる物質。これは発生された意識を包含している。まあ、意識自体といってしまってもいいのかもしれないけど。個体差によるけれど、長期間残留するものと考えられる。
『ノエマ』は『ノエシス』に対する物質で、発生した『ノエシス』を受容する。この反応によってASCと幻覚が発現する」
もう何がなんだか分からない。寺田は寺田で、フッサールがどうとか、嫌な学問だとかしきりに呟いていた。
「分かりにくいと思うけど、例えば、Aという人がXという場所において意識aを生じるとする。その後、Bという人がXにやって来て、Bの『ノエマ』がa、すなわちAの『ノエシス』に反応する。それがBにASC及び幻覚を生じさせて霊感が発現する。幻覚の内容は『ノエシス』に包含されている意識情報だ。ASC時に意識情報が顕在化するんだと思う。だから、あまり場所は関係なくなっちゃうね。意識が発生された場所ということかな。と、こういった感じなんだけど……」
響は、迷子になってしまったような子供の表情で僕たちを見る。僕は、何とか追いつこうと必死に頭を働かせていたから、彼に応えることが出来た。
つまり、意識を何らかの物質として、それを受容するものがあるということなのだろう。それは所謂、
「なんだかテレパシーみたいな感じだね」
すると響は、ぱあっと明るい表情になり、叫ぶように言った。
「そう! そうなんだよ。この『ノエシス』『ノエマ』っていうのは神経伝達物質の人間間バージョンみたいなもので、こういう風に考えるとテレパシーもあながちあり得ないということにはならないんだよね。『ノエシス』を特定の人間の意識(ノエマ)に飛ばすことができるのかもしれない。『ノエシス』と『ノエマ』がリアルタイムで反応するのかもしれない。だから、僕は最近テレパシーは本当にあるんじゃないかって思ってきたよ」
「阿呆なこと言ってないで、先を続けろよ」
響はむっとした顔を一瞬寺田に向けたが、すぐに続けた。
「ええと、さっき僕は『ノエシス』は長期間残留すると言ったけど、これは時間の経過よりは意識のレベル(強さ)によって残留の期間(また受容の程度)が変化するんじゃないかと思うんだ。さっきも言ったけど、『霊の出る場所』っていう言葉があるからね。ずっと長い間『ノエシス』が残留しているいい例なのかもしれない。
あと、子供の心霊現象の目撃数が大人に比べると多いことから、『ノエマ』の働きは子供の時に、より強いんじゃないかと思う。加えて、男性より女性の方が霊感が強いといわれるように『ノエマ』の働きも女性の方が強いと考えられるよね。
ひとつ面白い事例があるんだけど、みんなもいつか他の人に話してごらん。
沖縄にユタと呼ばれるシャーマンの一種がいるんだ。これは予言者型のシャーマンと、基本的にはされていて、神懸りなどを行なうんだ。彼らは個人的な祈願や病気治療をしている。簡単にいうと、民間のカウンセラーのようなものなんだ。また、ユタと対となるノロという人たち――ノロはみんな女性なんだけど――がいる。彼女達は村の祭祀などを公的に行なっている。ノロはシャーマンでなく、プリーストと呼ばれるんだ。この話には関係ないけどね。
興味深いのは、ユタやノロがどのような経緯でその地位に就くかということなんだ。ノロは、これは完全に家系による継承。ノロの家柄というものがあるらしい。一方、ユタは違うんだ。召命<しょうめい/神に選ばれるということ>によって、個人がなるものなんだ。
どういうことかというと、霊感の強い子供がいる。その子供は成長すると、あるとき幻覚に襲われるという。夜も眠れず、様々なものを見る。これが、巫病<ふびょう>というものだ(現地では“神障<ざわ>り”というらしい)。この病におかされた者は、それを乗り越えるための修行をし、やがてユタとなって人々を救うんだ。
そこで、この巫病はもしかすると、『ノエマ』の過多として説明できるかもしれない。様々な『ノエシス』を大量に受容してしまう。きっと頭が割れる思いだろう。だから、修行をしてそれに対抗する精神力を養うんじゃないかな」
響は満足そうにいい終わると、ジュースを一気に飲み干した。彼は、本当はこの話をしたかったのかもしれない。しかし、僕には響の言わんとすることがなんとなく分かった。
霊、子供、『ノエマ』。彼はあの話に迫っているのだ。一体どう繋げていくのか。
寺田が欠伸と共に吐き出した言葉は、こうだった。
「やっと、ここまで来たか。早く本題に移ってくれよ。前置きが長すぎるんだよ」
岡嶋はまだ戻らない。多分死んでいるだろう。
寺田のしかめっ面が笑える。理解しがたいといった素振りで彼は何かを言おうとしていたが、響は慌てたように、
「ただ、その霊というのがどういうものなのか説明できそうなんだ」
「どういうものなのかって、霊は霊だろ」
しかめっ面のままの寺田に響はゆっくりと首を振ってみせる。岡嶋はいまだにトイレに篭りっきりだ。大丈夫だろうか。
「いや、そうじゃないんだ。なんていうのか……その、どういう原因であれが現れたのか、分かったような気がするんだ」
響はそこまで言ってから反応を確かめるように僕たちのほうを向いた。たっぷりと間をとって続ける。
「これは多分、宗教学だったり大脳生理学の範疇の問題なんだと思うんだけど、霊感っていうのはある事柄を原因とする意識の変容状態(ASC)における幻覚の認識だと説明されるんだ」
「つまり、霊なんていないってわけじゃねえか」
僕など今の話すら理解できなかったのに、寺田はさらっと言ってのける。
「……それはちょっと難しい問題なんだけど。いる・いないというのが、どのレベルの意味なのか決めないとややこしくなるんだよね。簡単に言うと、意識の中には存在するということかな。でも、本当に霊はいるのかもしれない。まあ、それは別の話だ。
ある事柄っていうのは色々とあって、薬物だったり踊りだったりする。更に面白いのは、それが場所だったりする」
「場所?」
響は僕を見て頷く。ついでにジュースを飲み干し、指で唇を拭う。
「テレビとかで、ここは昔ある人物が非業の死を遂げた場所です、とか言って霊能者を連れて行くのがあるでしょう。そこで霊能者は、ああ見えますとか言うわけだよ。そういう意味の、場所ね」
寺田は鼻で笑う。
「ありゃあ、インチキだろ」
「君と喋っているとどうも話が脱線するな。インチキかどうかではなくて、インチキだとしても何故その霊能者がそういったことを言うのかが問題になる、という話もある。
とにかく、その場所がASCを引き起こし、幻覚を見させるきっかけとなるんだよ。でもさ、なんの関連性もないじゃない。場所と、脳内の変化がどう繋がっているのか。何らかの要素が、そのコネクションを作っていると考えるほかはない。じゃあ、その要素とはなんだろうか」
響は半ば独りごとのようにぶつぶつと言っている。
そんなことより、あの“千切れた子供”はどうなったのか。ここで響は講義を始めるつもりらしいが、一体なんのつもりだろう。何の関係があるのか。
淡々と語る響。
はじめは難色を示していたが、もうにやにやと笑っている寺田。
二人のレベルにまで届きそうもない。だから、僕は口を挟むどころか、どう相槌を打てばいいのかさえ分からなかった。
響は少し恥ずかしそうに口の端を緩めると、グラスを見つめながら、まるでそれに話しかけるようにしていた。
「僕はさ、結構暇だからこういうことを考えたりするんだけど、新しい概念を作ってみようと思ったんだ」
「そりゃあ、たいそうなこった」
「これは昔辞書をひいていて偶然見つけた言葉なんだけど……。ノエシスとノエマなんだ」
寺田はどういうわけか、かーっ、とかいう奇怪な音を立てて天井を仰いだ。
「意味は、ノエシスは意識の作用面。ノエマは意識の対象面。……だったと思う。本当は多分もっと複雑な言葉なんだろうけど、辞書にはそういう風にあるんだ。
この言葉を借りて、新しい物質の概念を考えてみたんだ。
『ノエシス』は、意識の発生時に生じる物質。これは発生された意識を包含している。まあ、意識自体といってしまってもいいのかもしれないけど。個体差によるけれど、長期間残留するものと考えられる。
『ノエマ』は『ノエシス』に対する物質で、発生した『ノエシス』を受容する。この反応によってASCと幻覚が発現する」
もう何がなんだか分からない。寺田は寺田で、フッサールがどうとか、嫌な学問だとかしきりに呟いていた。
「分かりにくいと思うけど、例えば、Aという人がXという場所において意識aを生じるとする。その後、Bという人がXにやって来て、Bの『ノエマ』がa、すなわちAの『ノエシス』に反応する。それがBにASC及び幻覚を生じさせて霊感が発現する。幻覚の内容は『ノエシス』に包含されている意識情報だ。ASC時に意識情報が顕在化するんだと思う。だから、あまり場所は関係なくなっちゃうね。意識が発生された場所ということかな。と、こういった感じなんだけど……」
響は、迷子になってしまったような子供の表情で僕たちを見る。僕は、何とか追いつこうと必死に頭を働かせていたから、彼に応えることが出来た。
つまり、意識を何らかの物質として、それを受容するものがあるということなのだろう。それは所謂、
「なんだかテレパシーみたいな感じだね」
すると響は、ぱあっと明るい表情になり、叫ぶように言った。
「そう! そうなんだよ。この『ノエシス』『ノエマ』っていうのは神経伝達物質の人間間バージョンみたいなもので、こういう風に考えるとテレパシーもあながちあり得ないということにはならないんだよね。『ノエシス』を特定の人間の意識(ノエマ)に飛ばすことができるのかもしれない。『ノエシス』と『ノエマ』がリアルタイムで反応するのかもしれない。だから、僕は最近テレパシーは本当にあるんじゃないかって思ってきたよ」
「阿呆なこと言ってないで、先を続けろよ」
響はむっとした顔を一瞬寺田に向けたが、すぐに続けた。
「ええと、さっき僕は『ノエシス』は長期間残留すると言ったけど、これは時間の経過よりは意識のレベル(強さ)によって残留の期間(また受容の程度)が変化するんじゃないかと思うんだ。さっきも言ったけど、『霊の出る場所』っていう言葉があるからね。ずっと長い間『ノエシス』が残留しているいい例なのかもしれない。
あと、子供の心霊現象の目撃数が大人に比べると多いことから、『ノエマ』の働きは子供の時に、より強いんじゃないかと思う。加えて、男性より女性の方が霊感が強いといわれるように『ノエマ』の働きも女性の方が強いと考えられるよね。
ひとつ面白い事例があるんだけど、みんなもいつか他の人に話してごらん。
沖縄にユタと呼ばれるシャーマンの一種がいるんだ。これは予言者型のシャーマンと、基本的にはされていて、神懸りなどを行なうんだ。彼らは個人的な祈願や病気治療をしている。簡単にいうと、民間のカウンセラーのようなものなんだ。また、ユタと対となるノロという人たち――ノロはみんな女性なんだけど――がいる。彼女達は村の祭祀などを公的に行なっている。ノロはシャーマンでなく、プリーストと呼ばれるんだ。この話には関係ないけどね。
興味深いのは、ユタやノロがどのような経緯でその地位に就くかということなんだ。ノロは、これは完全に家系による継承。ノロの家柄というものがあるらしい。一方、ユタは違うんだ。召命<しょうめい/神に選ばれるということ>によって、個人がなるものなんだ。
どういうことかというと、霊感の強い子供がいる。その子供は成長すると、あるとき幻覚に襲われるという。夜も眠れず、様々なものを見る。これが、巫病<ふびょう>というものだ(現地では“神障<ざわ>り”というらしい)。この病におかされた者は、それを乗り越えるための修行をし、やがてユタとなって人々を救うんだ。
そこで、この巫病はもしかすると、『ノエマ』の過多として説明できるかもしれない。様々な『ノエシス』を大量に受容してしまう。きっと頭が割れる思いだろう。だから、修行をしてそれに対抗する精神力を養うんじゃないかな」
響は満足そうにいい終わると、ジュースを一気に飲み干した。彼は、本当はこの話をしたかったのかもしれない。しかし、僕には響の言わんとすることがなんとなく分かった。
霊、子供、『ノエマ』。彼はあの話に迫っているのだ。一体どう繋げていくのか。
寺田が欠伸と共に吐き出した言葉は、こうだった。
「やっと、ここまで来たか。早く本題に移ってくれよ。前置きが長すぎるんだよ」
岡嶋はまだ戻らない。多分死んでいるだろう。
3、『ノエシス』の解
「うん。本当に前置きが長くなっちゃって申し訳ないんだけど、今のがこれから話す説明の基礎になってるんだ。そして、本題なんだけど……。
“千切れた子供”における『ノエシス』とは一体なんなのか。これが一番の問題だ」
響は鼻の頭を擦った。疲れたのだろうか、少しの間沈黙が続く。
「岡ちゃん、大丈夫かな?」
「あ? 大丈夫だろ。死にゃあしないって。心配なら見て来いよ」
寺田はこちらを見ない。
響が話し始めていた。もはや彼は自説を披露することに全神経を集中しているようだった。
「僕たちがあれを見たということは、そこに意識が存在したからに他ならないけど、ここで受容側の意識も何らかの影響があるんじゃないかと思ったんだ。これは、僕は一応の結論を持っているから結果論になっちゃうんだけど、ある場所で『ノエシス』を受容したとき、意識情報の中からその場所にそぐわないものは除去、あるいは変形されるんじゃないかということなんだ。例えば、この居酒屋で『ノエシス』を受容したとき、その情報の中に“象”があったとする。でも、こんな場所に象なんているわけがないという受容側の意識によって、それは除去、あるいは変形されるということ。変形されるとするなら、象の色だけが抽出されたりするのかもしれない。牙が何か別のものになりすましているのかもしれない」
「つまり、あの“千切れた子供”もその意識情報の改変が行なわれているというのか」
すらすらと澱みなく言い切ると、寺田は先を促すように手で合図した。僕は、なんだか自分だけ取り残されたような疎外感を受けた。飲み込みが悪いのだから仕方がないにしても、これはあんまりではないか。
「そうなんだ。まず気になったのは、何故子供が千切れているのかということだった。『ノエシス』を発した人は、その光景を見たか何かして、とにかくそういうイメージを意識のうえで作り上げたことになる。すると、これは何らかの原因があって子供の体が千切れたということになる。じゃあ、その原因は一体なんなのか」
「そんな状況なんてないだろ」
寺田は我関せずといったような投げ遣りな言葉を返した。興味があるんだかないんだか分からない奴だ。それでいて、どこか達観したような雰囲気を持っているからますます分からなくなる。もしかすると、この寺田とかいう男はこうして見るよりも遥かに深い人間性を持っているのかもしれない。そう思うと、僕だけが成長していないような嫌な気持ちに襲われた。
それを紛らわすために、どういう原因が子供の体を引き千切ったか考えようとしたが、さっぱり考えは浮かばなかった。落ち込みかけて俯いていると、声が聞こえる。
「僕も、そこは一番難しいところだと思った。でも、意識情報の改変が行なわれたとして、どうにか説明をつけられるんじゃないかと思ったんだ。
あの子供の服装、覚えているよね? 白と灰色のボーダー。これが実に信じられないことを示唆しているんだ。
つまり、僕は、あの『ノエシス』を発したのが田原先生だと確信しているんだ」
まさか。
響は、本当にそう言おうとしているのか。
しかし、まさか。あれは本当に霊ではないのか?
寺田は全く納得が行かないといった様子である。
「何でいきなりそんな話になるんだよ?! 全然脈絡がないじゃねえか」
「いや、大ありだよ。
白と灰色。これが意識情報の改変の末に現れたものだとすると、その色の正体はなんなのか。ここで僕は思い出したんだ」
響は――きっと意図的にだろうが――ここでじりじりするくらいの間を取った。
辺りの話し声が耳に入る。大声、笑い声。どれも明るいものだった。あちこちでグラスや食器の触れ合う音がしていて、賑やかだった。
「田原先生は赤と緑の識別ができなかったんだよ」
「だから何なんだよ?!」
寺田の言う通りである。赤と緑の区別が出来ないことと、白と灰色の服に関係なんてこれっぽちもない。響は、落ち着いてと言わんばかりに両手を前に出した。
「つまり、田原先生は赤緑色盲だったんだよ」
それは分かっている。同じことを二度も言うなんて、響らしくなかった。いかにも、何かの思惑があると言わんばかりである。それは一体なんなのか。
寺田は、どうしたのか、ふーと深く息をついた。なにやら苦々しげな顔をしている。
「さて、だから、あの白と灰色は重大な、しかし複雑な示唆をもたらすんだ。赤緑色盲の人は赤と緑の色の区別が出来ない。どちらも灰色に見えてしまう。
あれは、あの灰色は、赤であり、緑だった。赤は血の色。そして緑は、というより、緑と白は……、
S電鉄の車体の色合いと一致しているんだ」
何ということだ!
しかし、しかし、確かにそうだった。
今、僕にもはっきりと理解できた。
響が先を続ける。
「そう、何故子供は千切れていたのか。多分電車の事故に巻き込まれた。事故に遭ったのは、田原先生の息子さんなんだ。それを、先生はあの場所で思い出していた。いや、その記憶に襲われたんだ」
響は翳りを見せたままの表情で俯いていた。本当は、僕からは彼の顔は見えなかったのだが、きっと暗い表情をしているに違いない。
言葉に詰まってしまった。これが本当だとして、なんと後味の悪い事実。紙の上の出来事のようだ。
“千切れた子供”における『ノエシス』とは一体なんなのか。これが一番の問題だ」
響は鼻の頭を擦った。疲れたのだろうか、少しの間沈黙が続く。
「岡ちゃん、大丈夫かな?」
「あ? 大丈夫だろ。死にゃあしないって。心配なら見て来いよ」
寺田はこちらを見ない。
響が話し始めていた。もはや彼は自説を披露することに全神経を集中しているようだった。
「僕たちがあれを見たということは、そこに意識が存在したからに他ならないけど、ここで受容側の意識も何らかの影響があるんじゃないかと思ったんだ。これは、僕は一応の結論を持っているから結果論になっちゃうんだけど、ある場所で『ノエシス』を受容したとき、意識情報の中からその場所にそぐわないものは除去、あるいは変形されるんじゃないかということなんだ。例えば、この居酒屋で『ノエシス』を受容したとき、その情報の中に“象”があったとする。でも、こんな場所に象なんているわけがないという受容側の意識によって、それは除去、あるいは変形されるということ。変形されるとするなら、象の色だけが抽出されたりするのかもしれない。牙が何か別のものになりすましているのかもしれない」
「つまり、あの“千切れた子供”もその意識情報の改変が行なわれているというのか」
すらすらと澱みなく言い切ると、寺田は先を促すように手で合図した。僕は、なんだか自分だけ取り残されたような疎外感を受けた。飲み込みが悪いのだから仕方がないにしても、これはあんまりではないか。
「そうなんだ。まず気になったのは、何故子供が千切れているのかということだった。『ノエシス』を発した人は、その光景を見たか何かして、とにかくそういうイメージを意識のうえで作り上げたことになる。すると、これは何らかの原因があって子供の体が千切れたということになる。じゃあ、その原因は一体なんなのか」
「そんな状況なんてないだろ」
寺田は我関せずといったような投げ遣りな言葉を返した。興味があるんだかないんだか分からない奴だ。それでいて、どこか達観したような雰囲気を持っているからますます分からなくなる。もしかすると、この寺田とかいう男はこうして見るよりも遥かに深い人間性を持っているのかもしれない。そう思うと、僕だけが成長していないような嫌な気持ちに襲われた。
それを紛らわすために、どういう原因が子供の体を引き千切ったか考えようとしたが、さっぱり考えは浮かばなかった。落ち込みかけて俯いていると、声が聞こえる。
「僕も、そこは一番難しいところだと思った。でも、意識情報の改変が行なわれたとして、どうにか説明をつけられるんじゃないかと思ったんだ。
あの子供の服装、覚えているよね? 白と灰色のボーダー。これが実に信じられないことを示唆しているんだ。
つまり、僕は、あの『ノエシス』を発したのが田原先生だと確信しているんだ」
まさか。
響は、本当にそう言おうとしているのか。
しかし、まさか。あれは本当に霊ではないのか?
寺田は全く納得が行かないといった様子である。
「何でいきなりそんな話になるんだよ?! 全然脈絡がないじゃねえか」
「いや、大ありだよ。
白と灰色。これが意識情報の改変の末に現れたものだとすると、その色の正体はなんなのか。ここで僕は思い出したんだ」
響は――きっと意図的にだろうが――ここでじりじりするくらいの間を取った。
辺りの話し声が耳に入る。大声、笑い声。どれも明るいものだった。あちこちでグラスや食器の触れ合う音がしていて、賑やかだった。
「田原先生は赤と緑の識別ができなかったんだよ」
「だから何なんだよ?!」
寺田の言う通りである。赤と緑の区別が出来ないことと、白と灰色の服に関係なんてこれっぽちもない。響は、落ち着いてと言わんばかりに両手を前に出した。
「つまり、田原先生は赤緑色盲だったんだよ」
それは分かっている。同じことを二度も言うなんて、響らしくなかった。いかにも、何かの思惑があると言わんばかりである。それは一体なんなのか。
寺田は、どうしたのか、ふーと深く息をついた。なにやら苦々しげな顔をしている。
「さて、だから、あの白と灰色は重大な、しかし複雑な示唆をもたらすんだ。赤緑色盲の人は赤と緑の色の区別が出来ない。どちらも灰色に見えてしまう。
あれは、あの灰色は、赤であり、緑だった。赤は血の色。そして緑は、というより、緑と白は……、
S電鉄の車体の色合いと一致しているんだ」
何ということだ!
しかし、しかし、確かにそうだった。
今、僕にもはっきりと理解できた。
響が先を続ける。
「そう、何故子供は千切れていたのか。多分電車の事故に巻き込まれた。事故に遭ったのは、田原先生の息子さんなんだ。それを、先生はあの場所で思い出していた。いや、その記憶に襲われたんだ」
響は翳りを見せたままの表情で俯いていた。本当は、僕からは彼の顔は見えなかったのだが、きっと暗い表情をしているに違いない。
言葉に詰まってしまった。これが本当だとして、なんと後味の悪い事実。紙の上の出来事のようだ。
と、そこへ岡嶋がやって来た。青白い顔で、千鳥足だ。危なっかしい足取りでこちらに近づいて来る。
「おいおい、大丈夫か? 顔色が馬鹿みたいに悪いぞ」
「うんにゃ、らいじょうぶ……。うああ……」
岡嶋はそう呻くと椅子に倒れこむようにして腰をおろした。きょろきょろと僕たちを順番に見つめている。
「そうそう……、この前さ、田原先生にさ、会ってさ、一緒に飲んだんだよ……」
「それはさっき聞いたって」
「先生の息子さんさ、S電鉄の電車の事故で亡くなったんだって……」
何ということだ!
「なんだって?!」
当の本人が一番驚いているようだった。目を丸くしてまたきょろきょろとしている。
そんな馬鹿な。
ならば、あの響の話は真実だったというのか。
一体なんなのだ!
この世は、そんなに単純なものなのだろうか。そういともあっさりとしたものなのだろうか。こんな超自然的なことが起こり得る世界。
足元がぐらついた。
そのままこの世界までもが崩れていくのではないだろうか。
――それは、きっと、あんな物質が作用していて……。だから、崩れて……。
「おいおい、大丈夫か? 顔色が馬鹿みたいに悪いぞ」
「うんにゃ、らいじょうぶ……。うああ……」
岡嶋はそう呻くと椅子に倒れこむようにして腰をおろした。きょろきょろと僕たちを順番に見つめている。
「そうそう……、この前さ、田原先生にさ、会ってさ、一緒に飲んだんだよ……」
「それはさっき聞いたって」
「先生の息子さんさ、S電鉄の電車の事故で亡くなったんだって……」
何ということだ!
「なんだって?!」
当の本人が一番驚いているようだった。目を丸くしてまたきょろきょろとしている。
そんな馬鹿な。
ならば、あの響の話は真実だったというのか。
一体なんなのだ!
この世は、そんなに単純なものなのだろうか。そういともあっさりとしたものなのだろうか。こんな超自然的なことが起こり得る世界。
足元がぐらついた。
そのままこの世界までもが崩れていくのではないだろうか。
――それは、きっと、あんな物質が作用していて……。だから、崩れて……。
幕間
それは、
一体どんな気持ちなのだろうか。
僕にはとうてい分からないだろう。自らの胎を痛め、生まれ出<いで>た命が、目の前で――。
それでも、田原先生はとても強かったのだと思う。あれだけのことがあって、学校へ来たのだ。それはとてつもない精神力。
彼女は何を思ったのだろうか。
息子の死を乗り越えようとしたのか。
しかし、田原先生は強くもあり、それゆえに弱かったのだ。
目の前を走りぬける児童達……。廊下を走っていっても注意だって出来ない。
そう、その子供たちには、足があって、命があったから。
そうして、思ったのだ。あの、歴代校長の肖像画みたいな“校長先生の影”の廊下で。
心に大きく開いた穴。虚ろで、それでいて懐かしくて。その穴は何があろうとも塞がることはない。いつまでも太陽のような目を開いて、ひとつの命の証を刻む。
トラウマなんて、生温い言葉では言い表すことなんて、出来ないだろう。
色のない死は、素知らぬ顔で牙を剥いたのだ。
一体どんな気持ちなのだろうか。
僕にはとうてい分からないだろう。自らの胎を痛め、生まれ出<いで>た命が、目の前で――。
それでも、田原先生はとても強かったのだと思う。あれだけのことがあって、学校へ来たのだ。それはとてつもない精神力。
彼女は何を思ったのだろうか。
息子の死を乗り越えようとしたのか。
しかし、田原先生は強くもあり、それゆえに弱かったのだ。
目の前を走りぬける児童達……。廊下を走っていっても注意だって出来ない。
そう、その子供たちには、足があって、命があったから。
そうして、思ったのだ。あの、歴代校長の肖像画みたいな“校長先生の影”の廊下で。
心に大きく開いた穴。虚ろで、それでいて懐かしくて。その穴は何があろうとも塞がることはない。いつまでも太陽のような目を開いて、ひとつの命の証を刻む。
トラウマなんて、生温い言葉では言い表すことなんて、出来ないだろう。
色のない死は、素知らぬ顔で牙を剥いたのだ。
4、夏の夜は短く
もう日にちは変わっていた。
この時間になるとさすがの夏の暑さも影を潜めてしまう。時折風が吹きぬけて行って、それが火照った体に心地よかった。
僕は三人を引き連れて歩いていた。僕の実家で泊まることになったのだ。もう親には話を通してあるから万事心配はない。寺田は困り果てた顔で岡嶋に肩を貸してやっていた。岡嶋の酔いつぶれた目はとろんとして今にもとろけだしそうである。無表情を決め込んだ響は眠気もないらしく、無機質な歩を進めていた。
どう驚くべきなのか。それとも、驚いてはならないことなのだろうか。
僕は、響が解明したあの話は真理に近づき過ぎたのではないかと思っている。なんだか、舞台裏や大宮殿の骨組みを見たような印象だ。
不思議なこととはなんだろうか。あの瞬間、急に世界から面白みが失せたような気がした。すべてに説明がつけられるのだと。
気が付くと響が僕の隣を歩いていた。何も話さないのも変だと思ったので、言った。
「すごい推理だったね。本当にすごいよ。やっぱりリュウは頭がいいよなあ……」
響は僕の言葉には反応を示さなかった。
――僕は、ここにいる、よな。
彼は思案していたようだった。その証拠に表情を保ったまま彼は話し出した。
「でも、なんだか今はおかしな気分だよ。
あの『ノエシス』『ノエマ』の概念を以ってしたとき、あの“校長先生の影”は現在見られる形に発現したことにおいて、とても整合性を持っているんだよね。でも、あんな噂に聞くような経緯なんて、あるはずがない。もしかしたら、もっと別のとても強い想いが込められているのかもしれないな」
響の言葉が終わったとき、また僕の中で新たな炎が光りだした。
そうなのだ。あの不思議な校長先生の影。一体どんな想いがあそこにはあるのだろう。
その意思はどこまでも深く、永遠に続くものなのかもしれない。その具現した姿を、今僕たちは見ることができる。
そのこと自体が、とても神秘的に思われた。
この時間になるとさすがの夏の暑さも影を潜めてしまう。時折風が吹きぬけて行って、それが火照った体に心地よかった。
僕は三人を引き連れて歩いていた。僕の実家で泊まることになったのだ。もう親には話を通してあるから万事心配はない。寺田は困り果てた顔で岡嶋に肩を貸してやっていた。岡嶋の酔いつぶれた目はとろんとして今にもとろけだしそうである。無表情を決め込んだ響は眠気もないらしく、無機質な歩を進めていた。
どう驚くべきなのか。それとも、驚いてはならないことなのだろうか。
僕は、響が解明したあの話は真理に近づき過ぎたのではないかと思っている。なんだか、舞台裏や大宮殿の骨組みを見たような印象だ。
不思議なこととはなんだろうか。あの瞬間、急に世界から面白みが失せたような気がした。すべてに説明がつけられるのだと。
気が付くと響が僕の隣を歩いていた。何も話さないのも変だと思ったので、言った。
「すごい推理だったね。本当にすごいよ。やっぱりリュウは頭がいいよなあ……」
響は僕の言葉には反応を示さなかった。
――僕は、ここにいる、よな。
彼は思案していたようだった。その証拠に表情を保ったまま彼は話し出した。
「でも、なんだか今はおかしな気分だよ。
あの『ノエシス』『ノエマ』の概念を以ってしたとき、あの“校長先生の影”は現在見られる形に発現したことにおいて、とても整合性を持っているんだよね。でも、あんな噂に聞くような経緯なんて、あるはずがない。もしかしたら、もっと別のとても強い想いが込められているのかもしれないな」
響の言葉が終わったとき、また僕の中で新たな炎が光りだした。
そうなのだ。あの不思議な校長先生の影。一体どんな想いがあそこにはあるのだろう。
その意思はどこまでも深く、永遠に続くものなのかもしれない。その具現した姿を、今僕たちは見ることができる。
そのこと自体が、とても神秘的に思われた。
{元になった実体験とは……!?
{作中と同じ時期に学校の廊下に同じように子供がいました。怖かったので、すぐに逃げましたが…(^^;)。学校の廊下の色や間取りも同じです。
土地の名前は実際の物のイニシャルです。また、土地の様子は実際のものです(描写なんてこれっぽちもないけれど)。
「校長先生の影」というのも実話です。これが本当に不思議なもので、作中にある通りです。噂も現実のものです。その人影というのが油で描いたような印象なんです。いやあ、怖いですよ。}
{作中と同じ時期に学校の廊下に同じように子供がいました。怖かったので、すぐに逃げましたが…(^^;)。学校の廊下の色や間取りも同じです。
土地の名前は実際の物のイニシャルです。また、土地の様子は実際のものです(描写なんてこれっぽちもないけれど)。
「校長先生の影」というのも実話です。これが本当に不思議なもので、作中にある通りです。噂も現実のものです。その人影というのが油で描いたような印象なんです。いやあ、怖いですよ。}