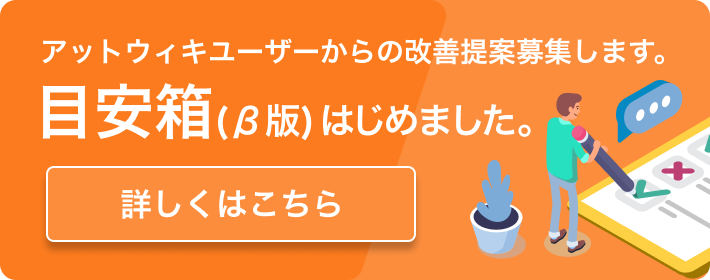CMWC NONEL COMPETITION
陰気な日曜の前に
最終更新:
cmwc
-
view
作:多田野 小五郎
始まりは、今月の十九日の月曜日。それは、鉛色の雲がどんよりと垂れ下がった実に不快な夕暮れ時のことだった。
僕は、都心から離れたある小さな町の小学校に教育実習で通っていて、下宿へ帰る電車を待つ間の三十分を潰すために、いつも駅前の本屋に立ち寄っていた。
そういう規則正しい生活を送るのも、あと二週間である。自堕落が染み付いた体がやっと時間に捕らわれることに慣れてきた頃、また、自堕落に戻る。取りあえずは、これも単位を取るためには仕方ない日々だと納得していた。
本屋の外観は古臭いが、最近内装を変えたらしく、新品の什器が並ぶ明るい雰囲気の店になっている。中は思ったよりも広い。客は常時七、八人は入っていて、少々の間なら立ち読みしていても目立つことはなかった。
その日、ふと奇妙な客に、注意を奪われた。
喪服のような黒いスーツを着た男で、彼が中に入ってくるなり、僕はなんだか空気が濁ったような息苦しさを感じて振り向いた。周りを明るくするような人物というのはいるが、そこだけ暗くしてしまうような男をはじめて見た。実際、晧晧と明るいはずの照明が、ろうそくの明かりのように仄かになり、男の全体を霞ます明度に落ちたように思えたのである。
何気なく観察していると、男は文庫本のコーナーに一直線に進み、一冊の本を本棚から抜き出した。本屋に足を運ぶ人は、本を選びに来るか、すでに選んだ本を買いに来るか、あるいは僕のように時間つぶしに来るか、おおむねその三つぐらいしかない。ところが、その男はどれでもなかった。すでに決めていたように躊躇なく一冊の本を手にとり、ぱらぱらとめくった後ですぐに棚に戻したのだ。買いに来たのではなく、選んだのでもない。そのまま踵を返すと、入ってきたのと同じと歩調ですっと外へ出ていってしまった。男が目の前から姿を消すと、とたんに店内がもとの明るさに戻ったような気がした。
おそらくその男の行動に気づいたのは、店内では僕しかいなかったに違いない。
男のいたところに何気なく近寄って、本棚を漠然と眺めた。男がどの本を手にしたのか、すぐにわかった。その本は背表紙が上下反対になって差し込まれていたからだ。僕は、自分の胸の動悸が急に早くなるのを感じた。
理由のわからない衝動に負け、思わずその本に手を伸ばした。すると、その手の先に、別の手が一瞬早く伸び、横から本を抜き取ってしまった。
驚いて振り向くと、高校生ぐらいの少女である。彼女は、僕の存在を無視するように、その場に佇み、無我夢中でページをめくった。彼女が先ほどの男と違っていたのは、その後すぐ困惑の表情を見せたことである。本を買うべきかどうかためらっているように見えた。が、それも僅かの間である。しばらくすると、その本をもとの棚に戻し、その後は振り返りもしないで本屋から出て行った。
残った僕はしばらく唖然としていた。再び先ほどの本を探したが、すでに他の在庫に紛れて見分けがつかない。せめて、題名だけでも覚えておくべきだったが、一連の出来事はあまりにも一瞬のことだった。
怪訝な気持ちを引き摺ったまま、その日は電車の時間が来てしまった。
僕は、都心から離れたある小さな町の小学校に教育実習で通っていて、下宿へ帰る電車を待つ間の三十分を潰すために、いつも駅前の本屋に立ち寄っていた。
そういう規則正しい生活を送るのも、あと二週間である。自堕落が染み付いた体がやっと時間に捕らわれることに慣れてきた頃、また、自堕落に戻る。取りあえずは、これも単位を取るためには仕方ない日々だと納得していた。
本屋の外観は古臭いが、最近内装を変えたらしく、新品の什器が並ぶ明るい雰囲気の店になっている。中は思ったよりも広い。客は常時七、八人は入っていて、少々の間なら立ち読みしていても目立つことはなかった。
その日、ふと奇妙な客に、注意を奪われた。
喪服のような黒いスーツを着た男で、彼が中に入ってくるなり、僕はなんだか空気が濁ったような息苦しさを感じて振り向いた。周りを明るくするような人物というのはいるが、そこだけ暗くしてしまうような男をはじめて見た。実際、晧晧と明るいはずの照明が、ろうそくの明かりのように仄かになり、男の全体を霞ます明度に落ちたように思えたのである。
何気なく観察していると、男は文庫本のコーナーに一直線に進み、一冊の本を本棚から抜き出した。本屋に足を運ぶ人は、本を選びに来るか、すでに選んだ本を買いに来るか、あるいは僕のように時間つぶしに来るか、おおむねその三つぐらいしかない。ところが、その男はどれでもなかった。すでに決めていたように躊躇なく一冊の本を手にとり、ぱらぱらとめくった後ですぐに棚に戻したのだ。買いに来たのではなく、選んだのでもない。そのまま踵を返すと、入ってきたのと同じと歩調ですっと外へ出ていってしまった。男が目の前から姿を消すと、とたんに店内がもとの明るさに戻ったような気がした。
おそらくその男の行動に気づいたのは、店内では僕しかいなかったに違いない。
男のいたところに何気なく近寄って、本棚を漠然と眺めた。男がどの本を手にしたのか、すぐにわかった。その本は背表紙が上下反対になって差し込まれていたからだ。僕は、自分の胸の動悸が急に早くなるのを感じた。
理由のわからない衝動に負け、思わずその本に手を伸ばした。すると、その手の先に、別の手が一瞬早く伸び、横から本を抜き取ってしまった。
驚いて振り向くと、高校生ぐらいの少女である。彼女は、僕の存在を無視するように、その場に佇み、無我夢中でページをめくった。彼女が先ほどの男と違っていたのは、その後すぐ困惑の表情を見せたことである。本を買うべきかどうかためらっているように見えた。が、それも僅かの間である。しばらくすると、その本をもとの棚に戻し、その後は振り返りもしないで本屋から出て行った。
残った僕はしばらく唖然としていた。再び先ほどの本を探したが、すでに他の在庫に紛れて見分けがつかない。せめて、題名だけでも覚えておくべきだったが、一連の出来事はあまりにも一瞬のことだった。
怪訝な気持ちを引き摺ったまま、その日は電車の時間が来てしまった。
次の日。同じ時間、同じ本屋にいた僕は、昨日の経験を鮮明に思い出していた。なぜなら、二日目も喪服のように黒い服を来た男が現れて、あのときとまったく同じ行動を繰り返したからである。
昨日の男とこの男が別人かどうか、それは僕にははっきりとは断言できない。確か、昨日は髭がなかったはずだが、今日の男は顔中にそれしかないほど髭を貯えていた。服装も色調は同じでも、スタイルが違う。その日はネクタイも細く、どちらかというとタイトな着こなしである。どっちにせよ、その男の周りも、やはり暗い照明を落としたような雰囲気が漂っていた。顔つき、表情は、おぼろげに霞んではっきりと見えない。
男の行動は、一冊の本をひっくり返すためだけにやって来たものだとしか思えなかった。その仕事を済ますと、消えるように去っていった。そのあと、本棚に駆け寄ると、上下逆さまに差してある本はすぐ目についた。さっそく抜き取ってみる。
「太宰治著 人間失格」
それが、題字だった。有名な純文学だという事はわかる。
「あの……」
ふいに後から声をかけられて驚き、手にした本を床に落とした。なぜか、密室で悪事を行っている最中に、突然ドアを開け放たれたような罪悪感が心に湧いた。鼻先に息がかかりそうなほど近くに、スーツ姿で、堅苦しいメガネをかけた若い女性が立っている。会社帰りのOLらしいが、その着こなしは妙に地味だった。
「その本、買いたいのですが……あなたも……」
彼女は怯えるような声で話しかけてきた。もちろん、僕には買うつもりなど、はなからない。「いいえ」といって拾い上げ、それを手渡した。彼女は頭を軽く下げ、あとは、一言も残さずに、そそくさと立ち去った。
三日目に現れた男も、前の二人の男とは別人のようだった。だが、全体から滲むダークな色調は同じだし、その行為も同じである。本を一冊引き抜いて、元に戻した。さすがに三回目となると、僕も落ち着いて観察できるようになった。遠目でも確認できたことがふたつある。本の銘柄が昨日と同じだということ。戻す場所がいつもばらばらだということ。戻した本が上下逆さまになっているということ。
それからすぐに別の女が来た。今度はジーンズをはいた学生風である。今度は、本をぺらぺらとめくり、元の本棚に戻して去った。
女がいなくなった後、僕は再びその本を手にした。女が本をめくったとき、何をしたのかわからなかった。何かを抜いたのか。だが、それもわからない。
昨日の男とこの男が別人かどうか、それは僕にははっきりとは断言できない。確か、昨日は髭がなかったはずだが、今日の男は顔中にそれしかないほど髭を貯えていた。服装も色調は同じでも、スタイルが違う。その日はネクタイも細く、どちらかというとタイトな着こなしである。どっちにせよ、その男の周りも、やはり暗い照明を落としたような雰囲気が漂っていた。顔つき、表情は、おぼろげに霞んではっきりと見えない。
男の行動は、一冊の本をひっくり返すためだけにやって来たものだとしか思えなかった。その仕事を済ますと、消えるように去っていった。そのあと、本棚に駆け寄ると、上下逆さまに差してある本はすぐ目についた。さっそく抜き取ってみる。
「太宰治著 人間失格」
それが、題字だった。有名な純文学だという事はわかる。
「あの……」
ふいに後から声をかけられて驚き、手にした本を床に落とした。なぜか、密室で悪事を行っている最中に、突然ドアを開け放たれたような罪悪感が心に湧いた。鼻先に息がかかりそうなほど近くに、スーツ姿で、堅苦しいメガネをかけた若い女性が立っている。会社帰りのOLらしいが、その着こなしは妙に地味だった。
「その本、買いたいのですが……あなたも……」
彼女は怯えるような声で話しかけてきた。もちろん、僕には買うつもりなど、はなからない。「いいえ」といって拾い上げ、それを手渡した。彼女は頭を軽く下げ、あとは、一言も残さずに、そそくさと立ち去った。
三日目に現れた男も、前の二人の男とは別人のようだった。だが、全体から滲むダークな色調は同じだし、その行為も同じである。本を一冊引き抜いて、元に戻した。さすがに三回目となると、僕も落ち着いて観察できるようになった。遠目でも確認できたことがふたつある。本の銘柄が昨日と同じだということ。戻す場所がいつもばらばらだということ。戻した本が上下逆さまになっているということ。
それからすぐに別の女が来た。今度はジーンズをはいた学生風である。今度は、本をぺらぺらとめくり、元の本棚に戻して去った。
女がいなくなった後、僕は再びその本を手にした。女が本をめくったとき、何をしたのかわからなかった。何かを抜いたのか。だが、それもわからない。
奇妙な男の意図は一体なんだろう。時間を置かずにやってくる女性たちに何かを伝えようとしているのかもしれない。が、本を逆さまに入れ直すことで何が伝わるのか、まったく想像もつかなかった。
結局、四日目を待たず、僕は友人の朝倉伊織を訪ねた。推理小説をこよなく愛する、本の虫である。彼はかつて、キャンパス内で起こった盗難事件を鮮やかな推理で解決したことがあり、その話は仲間内でも結構有名になっていた。将来の夢は、と聞けば「探偵」と答えるような変な男だった。
浅倉の下宿はいつ来ても雑然として、だらしなく散らかっている。暗い穴倉のような部屋で、日中でもそこに篭り、なにやらごそごそとやっている様子だった。交際範囲もきわめて狭い、いわゆるオタク野郎だが、それだけにこういう不思議な出来事についての解決能力は高いような気がした。
僕は、机の上のパソコンを睨んでいる朝倉の目の前で、この三日間の奇妙な体験のあらましをざっと話した。彼は最初気のないカラ返事をしていたのだが、いつの間にか、身を乗り出してきた。
「これがその本か?」
僕は三日目に手にした本を買ってきていた。朝倉は哲学者のように疑り深い目で、その本に視線を向けた。
「帰りの電車の中でざっと読んでみた。だが、何のヒントも見つけられなかったよ」
「全部読んだのか?」
「いや、四分の一。しおりを差しているところまでだ」
「しおりを移動したのか?」
朝倉の目に落胆の色が浮かんだ。
「しおりが関係あるってこと?」
「よく考えてみろ、そんな短時間に、この本だけで誰かに何かを伝えようとするなら、しおりを動かして何事かを示唆する方法ぐらいしか考えられないじゃないか」
「な、なるほど」
僕は目の前を塞いでいたベールが捲られたように、その意味を理解することが出来た。まだまだ頭は固くないつもりだ。
「明日は、しおりの挟んであるページに何か変わったことがないか確認して来てほしい。例えばページ数だ」
朝倉にそうアドバイスを受けたあくる日……四日目。
このとき初めて、奇妙な男がひっくり返した本を後で探しに来るのが、女性ばかりではないということがわかった。本を手にしたのは、痩せたサラリーマン風の男。残念なことに彼は、それをためらいもなく買っていってしまった。在庫は補充されていなかったようで、買われた本は「走れメロス」。有名な話だから、純文学に疎い僕でも知っていた。作者はやはり太宰である。
結局、五日目を待つことにした。
その日。やはり前の男たちとは違う風体の男が本を入れ替えた。が、今度は、今までとは違う展開になった。その本を手にしたのが、教育実習で同じ学校に配属された吉永順子という女性だったのである。
彼女は本の上下を直し、丁重にもとあった場所に戻して書店を出た。僕はその本を持って、レジで支払いを済ませるとポケットにねじ込み、慌てて彼女の後を追いかけた。相手はよく知っている女性だ。謎の理由を素直に聞いてしまえば話は早い。
駅の構内に入る手前で、なんとか追い付いた。
「吉永さん」と、僕は息を切らせて呼び止めた。「ちょっと聞きたいことがあるんですが……」
吉永順子は首を傾げて振り向いた。その目には、いつもの生気がない。
結局、四日目を待たず、僕は友人の朝倉伊織を訪ねた。推理小説をこよなく愛する、本の虫である。彼はかつて、キャンパス内で起こった盗難事件を鮮やかな推理で解決したことがあり、その話は仲間内でも結構有名になっていた。将来の夢は、と聞けば「探偵」と答えるような変な男だった。
浅倉の下宿はいつ来ても雑然として、だらしなく散らかっている。暗い穴倉のような部屋で、日中でもそこに篭り、なにやらごそごそとやっている様子だった。交際範囲もきわめて狭い、いわゆるオタク野郎だが、それだけにこういう不思議な出来事についての解決能力は高いような気がした。
僕は、机の上のパソコンを睨んでいる朝倉の目の前で、この三日間の奇妙な体験のあらましをざっと話した。彼は最初気のないカラ返事をしていたのだが、いつの間にか、身を乗り出してきた。
「これがその本か?」
僕は三日目に手にした本を買ってきていた。朝倉は哲学者のように疑り深い目で、その本に視線を向けた。
「帰りの電車の中でざっと読んでみた。だが、何のヒントも見つけられなかったよ」
「全部読んだのか?」
「いや、四分の一。しおりを差しているところまでだ」
「しおりを移動したのか?」
朝倉の目に落胆の色が浮かんだ。
「しおりが関係あるってこと?」
「よく考えてみろ、そんな短時間に、この本だけで誰かに何かを伝えようとするなら、しおりを動かして何事かを示唆する方法ぐらいしか考えられないじゃないか」
「な、なるほど」
僕は目の前を塞いでいたベールが捲られたように、その意味を理解することが出来た。まだまだ頭は固くないつもりだ。
「明日は、しおりの挟んであるページに何か変わったことがないか確認して来てほしい。例えばページ数だ」
朝倉にそうアドバイスを受けたあくる日……四日目。
このとき初めて、奇妙な男がひっくり返した本を後で探しに来るのが、女性ばかりではないということがわかった。本を手にしたのは、痩せたサラリーマン風の男。残念なことに彼は、それをためらいもなく買っていってしまった。在庫は補充されていなかったようで、買われた本は「走れメロス」。有名な話だから、純文学に疎い僕でも知っていた。作者はやはり太宰である。
結局、五日目を待つことにした。
その日。やはり前の男たちとは違う風体の男が本を入れ替えた。が、今度は、今までとは違う展開になった。その本を手にしたのが、教育実習で同じ学校に配属された吉永順子という女性だったのである。
彼女は本の上下を直し、丁重にもとあった場所に戻して書店を出た。僕はその本を持って、レジで支払いを済ませるとポケットにねじ込み、慌てて彼女の後を追いかけた。相手はよく知っている女性だ。謎の理由を素直に聞いてしまえば話は早い。
駅の構内に入る手前で、なんとか追い付いた。
「吉永さん」と、僕は息を切らせて呼び止めた。「ちょっと聞きたいことがあるんですが……」
吉永順子は首を傾げて振り向いた。その目には、いつもの生気がない。
「で、吉永女史は秘密を教えてくれたのか?」
「いや、ダメだ。黙って逃げていった。というか、何だか怒っていたよ。プライバシーを侵害したのかもしれない。完全に嫌われたってところだな」
「ふうむ」
暗く薄汚れた朝倉の部屋の中、彼は不似合いに明るくにこにこと笑っている。他の友人たちはみんな、彼を陰気な奴だというが、こういう笑顔を持っていることを知っているのだろうか。
「まあすわれ」と、パソコンの前に椅子をひとつ引き寄せて、朝倉が手招きした。
「お前は大変な手がかりをここへ持って来てくれた。実をいうと、この事件は俺がずっと追いかけていたものだ。お前には心から感謝しなければいけないようだ」
「事件?」
「ああ、これを見ろ」
朝倉が指差したパソコンの画面に「Gloomy Sunday」という横文字が並んでいる。彩度の鈍い、暗い色調が不気味な気配を醸し出していた。
「なんだこれ。陰気な……日曜?」
「このサイト名は、『暗い日曜日』、というシャンソンの曲名からきている。1930年代にハンガリーのピアノ弾きレッソ・セレシュという男が作曲した名曲だが、何よりも呪われた曲として有名なんだ」
呪い、などと、論理的思考の持ち主だと思っていた朝倉が口にするのは不可解だった。
「呪われた曲?」
「この曲を聞いて、今まで何百人もの人々が自殺を遂げているのさ。曲がヒットすると、たちまち、世界中で『自殺の聖歌』と呼ばれるようになり、事実、過去には発禁処分を受けたこともあった。物乞いの口ずさむのを耳にした少年が、有り金をすべて渡した後身投げしたとか、楽譜を握ったまま死んだ遺体が転がっていたとか、まあ、今でいう都市伝説のたぐいの話が数多く残っている。結局、作曲者セレシュ自信も自らの命を絶ってしまったようだ。この曲の秘密は、三連譜が連続して人の不安感を増長することらしいと、もっともらしい説明がされているが、それは完璧な理由だとは思えない。俺には呪われているとしか考えられないが、そういう曲の名を表紙にすること自体、ここがどういう主旨のサイトかわかるだろう?」
「まさか、自殺……クラブか? だが、そんなもの現実にあるのか」
「ある。『宝島』や『ジギルとハイド』で有名なスティブンソンが、『自殺クラブ』という小説で、過去にすでに定義を与えている。つまり、それこそ『世間に騒がれずに、わずらわしいこの世を去りたいと思ってる人たちのために存在するクラブだ』とね。自殺クラブは時代と国を超えて連綿と運営されている、人間の闇の部分に関わる活動なんだ」
朝倉はさらに続けた。
「いいか、ここ最近、ネットで出会ったというだけで一箇所に集まって自殺する事件が多発している。しかし、いったい彼らがどういうサイトで知り合い、モチベーションを高め、計画を練ったか、今だに特定されていないのが現状だ。あるいは、どういう経路で自殺用の毒薬を手に入れたのか、手段や段取りについて不明な自殺も数限りなくある。当局はすでに、その裏に何か不気味で大きな意思が存在していると、疑っているようだが、それ以上はお手上げ状態といっても過言じゃない。俺はその真相を掴むために、半年かけてこのサイトを探し当てた。毎日毎夜、ネットを徘徊し、ディスプレイとらめっこさ。それも実は、偶然の積み重ねの結果だったと、いった方がいい。しかし、このサイトを捕捉できるのも数週間だろう。その後は、アドレスを変え、また、どこかわからないところへ移動する。そうなれば、次に捕らえられる可能性はほとんどないんだ。そういうジレンマの中で手をこまねいていたときに、お前の情報を得た。これはもはや、沙漠で針を見つけるほどの幸運だよ。だが、こうなったら、この運を捕まえて絶対に離すわけにはいかない」
「待てよ、朝倉。その自殺クラブと本屋の謎はどう結びつくんだ?」
「自殺クラブ『暗い日曜日』の内部に潜入するには強力なコネクションが必要だ。俺は、それが何なのかずっとわからないでいた。恐らく、これから先もわかることはないだろう。だが、今月に入った十三日の仏滅の日、このサイトで突然告知があった。その日からきっかり十三日目の日曜日に、もちろんこの日も仏滅になっているはずだが、会員の中から選ばれた七人が自殺を決行するとね。決行日は、すでにあさってに迫っている。死ぬことは、彼らにとっては別世界への昇華だ。だが、その高みに上るためには、さらに秘密のドアを開かなければならない。その鍵が選ばれた奴らひとりひとりに贈られるパスワードだった」
「ということは、あの本屋の謎は、選ばれた会員にパスワードを渡す行為だったのか」
朝倉は頷いた。
「そういうことだ。見てみろ」
サイトのボタンをクリックすると、パスワードを入れるためのボックスが現れた。
「決行日は二十五日。パスワードは十八日からその日の前日までの七日間、日ごとに変わる。ひとりずつに与えられた別々のパスワードで、順番に秘密サイトにアクセスできるというわけだ。選ばれた会員はクラブに自らの行動と意思を示すことで、扉の鍵を得ることができる。その場所があの本屋だった」
「じゃあ、僕が買ってきたこの本に、今日のパスワードが示されているということだな」
見せてみろ、という言葉に促されて、僕は買ったばかりの本を朝倉に手渡した。太宰治「斜陽」である。朝倉はしおりの挟んであるページを丁寧に開いた。
「短時間でメッセージを残すにはしおりを利用するぐらいしか手はないはずだ。紙のようなものを挟んでしまうと、証拠を残す危険性が高くなるからね。逆さまにしたのは、本を特定するためでしかない。そのうえ、太宰だ。太宰という名を聞いて初めて、俺の中で『暗い日曜日』との関係が繋がった。彼はお前も知っている通り、自殺した芥川を尊敬し、また自らも、自殺未遂を繰り返して最後を遂げた作家だ。クラブが選ぶ本の著者としては、申し分ない資格を持っている。」
しおりを挟んであったのは、112ページと113ページ。
「このどちらかだな」
「しかし、このパスワードは四桁だぞ。それにここに『パスワードの入力ミスを三回すると、自動的にアクセスが拒絶されます』と書いている。あと一字を見つけるのは、勘じゃダメだ」
「わかっているさ、その一字はこうだ。逆さまにしてあったこの本を差していた棚はどこか思い出して欲しい。本屋の書棚は、作者別のあいうえお順にならんでいるはずだ。何日も通っていればわかるだろう。どの位置のどの作者の群れの中に差し込んであったか」
それは簡単ではない。が、人間の頭脳は不思議だ。必死で考えれば、思い出せないことなどないかのようである。すぐに思い出した。歴史小説の書庫。柴田錬三郎か、司馬遼太郎……だった。
「どのみち、『し』が頭だな。一字は、Sと特定してみよう。すると、Sを数字の上につけるか、下につけるかの二通りになる。数字の候補も二通りだから、全部で四通り。三回の失敗は許されるという符号にぴったり当てはまるじゃないか」
朝倉の指先がキーを叩くと、突然画面が暗転した。
「S112。これで、ビンゴだ」
暗い日曜日、のロゴがディスプレイいっぱいに浮き出してきた。同時に、なんともはかなく美しいメロディがスピーカーを通して流れ出してくる。
「これが、例の呪われた曲さ。あまり真剣に聞くと、死にたくなるかもしれないぜ」
朝倉は興奮していた。まるで恐れるという感情を無くしてしまったかのようだった。
「いや、ダメだ。黙って逃げていった。というか、何だか怒っていたよ。プライバシーを侵害したのかもしれない。完全に嫌われたってところだな」
「ふうむ」
暗く薄汚れた朝倉の部屋の中、彼は不似合いに明るくにこにこと笑っている。他の友人たちはみんな、彼を陰気な奴だというが、こういう笑顔を持っていることを知っているのだろうか。
「まあすわれ」と、パソコンの前に椅子をひとつ引き寄せて、朝倉が手招きした。
「お前は大変な手がかりをここへ持って来てくれた。実をいうと、この事件は俺がずっと追いかけていたものだ。お前には心から感謝しなければいけないようだ」
「事件?」
「ああ、これを見ろ」
朝倉が指差したパソコンの画面に「Gloomy Sunday」という横文字が並んでいる。彩度の鈍い、暗い色調が不気味な気配を醸し出していた。
「なんだこれ。陰気な……日曜?」
「このサイト名は、『暗い日曜日』、というシャンソンの曲名からきている。1930年代にハンガリーのピアノ弾きレッソ・セレシュという男が作曲した名曲だが、何よりも呪われた曲として有名なんだ」
呪い、などと、論理的思考の持ち主だと思っていた朝倉が口にするのは不可解だった。
「呪われた曲?」
「この曲を聞いて、今まで何百人もの人々が自殺を遂げているのさ。曲がヒットすると、たちまち、世界中で『自殺の聖歌』と呼ばれるようになり、事実、過去には発禁処分を受けたこともあった。物乞いの口ずさむのを耳にした少年が、有り金をすべて渡した後身投げしたとか、楽譜を握ったまま死んだ遺体が転がっていたとか、まあ、今でいう都市伝説のたぐいの話が数多く残っている。結局、作曲者セレシュ自信も自らの命を絶ってしまったようだ。この曲の秘密は、三連譜が連続して人の不安感を増長することらしいと、もっともらしい説明がされているが、それは完璧な理由だとは思えない。俺には呪われているとしか考えられないが、そういう曲の名を表紙にすること自体、ここがどういう主旨のサイトかわかるだろう?」
「まさか、自殺……クラブか? だが、そんなもの現実にあるのか」
「ある。『宝島』や『ジギルとハイド』で有名なスティブンソンが、『自殺クラブ』という小説で、過去にすでに定義を与えている。つまり、それこそ『世間に騒がれずに、わずらわしいこの世を去りたいと思ってる人たちのために存在するクラブだ』とね。自殺クラブは時代と国を超えて連綿と運営されている、人間の闇の部分に関わる活動なんだ」
朝倉はさらに続けた。
「いいか、ここ最近、ネットで出会ったというだけで一箇所に集まって自殺する事件が多発している。しかし、いったい彼らがどういうサイトで知り合い、モチベーションを高め、計画を練ったか、今だに特定されていないのが現状だ。あるいは、どういう経路で自殺用の毒薬を手に入れたのか、手段や段取りについて不明な自殺も数限りなくある。当局はすでに、その裏に何か不気味で大きな意思が存在していると、疑っているようだが、それ以上はお手上げ状態といっても過言じゃない。俺はその真相を掴むために、半年かけてこのサイトを探し当てた。毎日毎夜、ネットを徘徊し、ディスプレイとらめっこさ。それも実は、偶然の積み重ねの結果だったと、いった方がいい。しかし、このサイトを捕捉できるのも数週間だろう。その後は、アドレスを変え、また、どこかわからないところへ移動する。そうなれば、次に捕らえられる可能性はほとんどないんだ。そういうジレンマの中で手をこまねいていたときに、お前の情報を得た。これはもはや、沙漠で針を見つけるほどの幸運だよ。だが、こうなったら、この運を捕まえて絶対に離すわけにはいかない」
「待てよ、朝倉。その自殺クラブと本屋の謎はどう結びつくんだ?」
「自殺クラブ『暗い日曜日』の内部に潜入するには強力なコネクションが必要だ。俺は、それが何なのかずっとわからないでいた。恐らく、これから先もわかることはないだろう。だが、今月に入った十三日の仏滅の日、このサイトで突然告知があった。その日からきっかり十三日目の日曜日に、もちろんこの日も仏滅になっているはずだが、会員の中から選ばれた七人が自殺を決行するとね。決行日は、すでにあさってに迫っている。死ぬことは、彼らにとっては別世界への昇華だ。だが、その高みに上るためには、さらに秘密のドアを開かなければならない。その鍵が選ばれた奴らひとりひとりに贈られるパスワードだった」
「ということは、あの本屋の謎は、選ばれた会員にパスワードを渡す行為だったのか」
朝倉は頷いた。
「そういうことだ。見てみろ」
サイトのボタンをクリックすると、パスワードを入れるためのボックスが現れた。
「決行日は二十五日。パスワードは十八日からその日の前日までの七日間、日ごとに変わる。ひとりずつに与えられた別々のパスワードで、順番に秘密サイトにアクセスできるというわけだ。選ばれた会員はクラブに自らの行動と意思を示すことで、扉の鍵を得ることができる。その場所があの本屋だった」
「じゃあ、僕が買ってきたこの本に、今日のパスワードが示されているということだな」
見せてみろ、という言葉に促されて、僕は買ったばかりの本を朝倉に手渡した。太宰治「斜陽」である。朝倉はしおりの挟んであるページを丁寧に開いた。
「短時間でメッセージを残すにはしおりを利用するぐらいしか手はないはずだ。紙のようなものを挟んでしまうと、証拠を残す危険性が高くなるからね。逆さまにしたのは、本を特定するためでしかない。そのうえ、太宰だ。太宰という名を聞いて初めて、俺の中で『暗い日曜日』との関係が繋がった。彼はお前も知っている通り、自殺した芥川を尊敬し、また自らも、自殺未遂を繰り返して最後を遂げた作家だ。クラブが選ぶ本の著者としては、申し分ない資格を持っている。」
しおりを挟んであったのは、112ページと113ページ。
「このどちらかだな」
「しかし、このパスワードは四桁だぞ。それにここに『パスワードの入力ミスを三回すると、自動的にアクセスが拒絶されます』と書いている。あと一字を見つけるのは、勘じゃダメだ」
「わかっているさ、その一字はこうだ。逆さまにしてあったこの本を差していた棚はどこか思い出して欲しい。本屋の書棚は、作者別のあいうえお順にならんでいるはずだ。何日も通っていればわかるだろう。どの位置のどの作者の群れの中に差し込んであったか」
それは簡単ではない。が、人間の頭脳は不思議だ。必死で考えれば、思い出せないことなどないかのようである。すぐに思い出した。歴史小説の書庫。柴田錬三郎か、司馬遼太郎……だった。
「どのみち、『し』が頭だな。一字は、Sと特定してみよう。すると、Sを数字の上につけるか、下につけるかの二通りになる。数字の候補も二通りだから、全部で四通り。三回の失敗は許されるという符号にぴったり当てはまるじゃないか」
朝倉の指先がキーを叩くと、突然画面が暗転した。
「S112。これで、ビンゴだ」
暗い日曜日、のロゴがディスプレイいっぱいに浮き出してきた。同時に、なんともはかなく美しいメロディがスピーカーを通して流れ出してくる。
「これが、例の呪われた曲さ。あまり真剣に聞くと、死にたくなるかもしれないぜ」
朝倉は興奮していた。まるで恐れるという感情を無くしてしまったかのようだった。
画面を捲ろうとキーに延ばした指をふと止めて、朝倉が振り返った。
「お前はこれ以上関わらない方がいい。後は俺がなんとかする。だが、お前はまず、残りの一日、いつものようにあの本屋に行って、そこにくるはずの最後の人の命を救うんだ」
「命を救う?」
「そうだ、簡単なことだ。その人物がパスワードを確認する前に、しおりの位置を変えておくだけでいい。それから、当日の日曜日、吉永順子をぴったりとマークしろ。このパスワードは彼女のものだ。きっと彼女は自殺に向けて動き出すだろう。取り返しのつかない事態が起こる前に止めなければならない」
「吉永が自殺を考えていたなんて……」
僕は絶句した。学校ではあれだけ明るく振舞っていた美しい女性に、そんな心の悩みがあったとは……しかし……、
「しかし、すでにパスワードを知ってしまった五人はどうするんだ」
「それは俺の仕事だ。このパスワードで『暗い日曜日』の内部に入り込むことが出来る。彼らを救い、この恐ろしいクラブを潰すための方法を必ず見つけ出してやるさ」
僕にはそのとき、もうひとつの考えが浮かんでいた。
「本屋にやってきた謎の男の後を付けていったらどうだろう。クラブの在り処を見つけ出したら、すぐに警察に連絡できる」
「やめておいたほうがいい」
朝倉はあっさりと首を振った。「今度はお前の命が危なくなる。しかも、そういう危険を冒したとても、ある程度の確証を掴んでいなければ警察は動かない。お前を守ってくれはしないよ」
危険だ、という言葉にさらに僕は反応した。
「いったいあの謎の男は何者なんだろう。毎日来る男は同じ人物なのだろうかそれとも違うのか、それもわからない」
「奴は、死神だよ。死神はどんな姿にだってなれる。それ以上のことは俺にもさっぱりだ」
「おいおい、まさか本気で……」
「今はまだ、その化け物の正体は想像もつかない。このページを調べてみるまでは……。ただ普通の何かを越えたところにいる、普通ではない何か、とでもいうか……」
論理派の朝倉にしては実に歯切れが悪すぎる。
「とにかく、馬鹿げたことはもう終わりにしたい」
そういい残して下宿を後にしようとする僕の背中から、再び朝倉の呼び止める声がかかった。
「お前、本気で教師になるつもりか?」
いったい、その言葉はこの事件にどういう関係があるのか。一瞬混乱したが、結局僕は、ああ、とだけ答えてドアの外に出た。だが後に、朝倉のこの問いかけに、ある意味が隠されていることがわかるのである。
そして、この奇妙な一連の出来事は、二十五日の日曜日を迎えて唐突に、そして、驚くべき結果を迎えて終結することになる。
「お前はこれ以上関わらない方がいい。後は俺がなんとかする。だが、お前はまず、残りの一日、いつものようにあの本屋に行って、そこにくるはずの最後の人の命を救うんだ」
「命を救う?」
「そうだ、簡単なことだ。その人物がパスワードを確認する前に、しおりの位置を変えておくだけでいい。それから、当日の日曜日、吉永順子をぴったりとマークしろ。このパスワードは彼女のものだ。きっと彼女は自殺に向けて動き出すだろう。取り返しのつかない事態が起こる前に止めなければならない」
「吉永が自殺を考えていたなんて……」
僕は絶句した。学校ではあれだけ明るく振舞っていた美しい女性に、そんな心の悩みがあったとは……しかし……、
「しかし、すでにパスワードを知ってしまった五人はどうするんだ」
「それは俺の仕事だ。このパスワードで『暗い日曜日』の内部に入り込むことが出来る。彼らを救い、この恐ろしいクラブを潰すための方法を必ず見つけ出してやるさ」
僕にはそのとき、もうひとつの考えが浮かんでいた。
「本屋にやってきた謎の男の後を付けていったらどうだろう。クラブの在り処を見つけ出したら、すぐに警察に連絡できる」
「やめておいたほうがいい」
朝倉はあっさりと首を振った。「今度はお前の命が危なくなる。しかも、そういう危険を冒したとても、ある程度の確証を掴んでいなければ警察は動かない。お前を守ってくれはしないよ」
危険だ、という言葉にさらに僕は反応した。
「いったいあの謎の男は何者なんだろう。毎日来る男は同じ人物なのだろうかそれとも違うのか、それもわからない」
「奴は、死神だよ。死神はどんな姿にだってなれる。それ以上のことは俺にもさっぱりだ」
「おいおい、まさか本気で……」
「今はまだ、その化け物の正体は想像もつかない。このページを調べてみるまでは……。ただ普通の何かを越えたところにいる、普通ではない何か、とでもいうか……」
論理派の朝倉にしては実に歯切れが悪すぎる。
「とにかく、馬鹿げたことはもう終わりにしたい」
そういい残して下宿を後にしようとする僕の背中から、再び朝倉の呼び止める声がかかった。
「お前、本気で教師になるつもりか?」
いったい、その言葉はこの事件にどういう関係があるのか。一瞬混乱したが、結局僕は、ああ、とだけ答えてドアの外に出た。だが後に、朝倉のこの問いかけに、ある意味が隠されていることがわかるのである。
そして、この奇妙な一連の出来事は、二十五日の日曜日を迎えて唐突に、そして、驚くべき結果を迎えて終結することになる。
当日、朝倉の指示通り、吉永順子の後を追いかけた。
周囲に人がいない場所で、僕は、後ろからその手をしっかりと掴んだ。最初、吉永は、ありったけの悪意をぶつけてきた。だが、僕はひるまなかった。
「君は正気じゃなくなっている。どこへ行くつもりかわからないけど、もしこのまま行ってしまったら、二度と帰って来れなくなるんだぞ」
その語気の激しさに、緊張感が一気に崩れたのか、吉永は膝の力が抜けたようになって僕に倒れ掛かってきた。後はただ泣きじゃくるばかりだった。僕は、彼女を不思議そうに見守る両親の元に届けたあと、翌朝、その結果を報告するために、朝倉の下宿を尋ねた。
そこで僕は朝倉の第一発見者になった。
彼は毒を飲み、布団の中で眠るように死んでいたのである。
自殺を疑わない警察に対して、僕は始め、他殺の可能性を主張した。しかし、すでに朝倉のパソコンの中には手がかりはすべてなくなっていた。ただ、彼の遺書が見つかり、「探偵になろうだなんて、何にもならないのと同じことだ」と書かれてあったという。
結局僕の意見の方が間違っていた。
彼の悩みがどこにあったのか、今となってはわからない。だが朝倉は、この世から永久に消滅したいという望みのためにネットを果てしなく彷徨い、『暗い日曜日』を捜し続けていた。彼のその目的は、あの暗い日曜日、穏やかに遂げられた。
運命の日を過ぎた八日目以降、あの書店で、僕が見た奇妙な出来事は二度と起こらなかった。どこかまた、別の本屋で同じことが繰り返されているかもしれないが、それはもはや僕の知るところではない。
もちろん、朝倉の飲んだ毒薬についての入手ルートは、ついに解明されないままである。
周囲に人がいない場所で、僕は、後ろからその手をしっかりと掴んだ。最初、吉永は、ありったけの悪意をぶつけてきた。だが、僕はひるまなかった。
「君は正気じゃなくなっている。どこへ行くつもりかわからないけど、もしこのまま行ってしまったら、二度と帰って来れなくなるんだぞ」
その語気の激しさに、緊張感が一気に崩れたのか、吉永は膝の力が抜けたようになって僕に倒れ掛かってきた。後はただ泣きじゃくるばかりだった。僕は、彼女を不思議そうに見守る両親の元に届けたあと、翌朝、その結果を報告するために、朝倉の下宿を尋ねた。
そこで僕は朝倉の第一発見者になった。
彼は毒を飲み、布団の中で眠るように死んでいたのである。
自殺を疑わない警察に対して、僕は始め、他殺の可能性を主張した。しかし、すでに朝倉のパソコンの中には手がかりはすべてなくなっていた。ただ、彼の遺書が見つかり、「探偵になろうだなんて、何にもならないのと同じことだ」と書かれてあったという。
結局僕の意見の方が間違っていた。
彼の悩みがどこにあったのか、今となってはわからない。だが朝倉は、この世から永久に消滅したいという望みのためにネットを果てしなく彷徨い、『暗い日曜日』を捜し続けていた。彼のその目的は、あの暗い日曜日、穏やかに遂げられた。
運命の日を過ぎた八日目以降、あの書店で、僕が見た奇妙な出来事は二度と起こらなかった。どこかまた、別の本屋で同じことが繰り返されているかもしれないが、それはもはや僕の知るところではない。
もちろん、朝倉の飲んだ毒薬についての入手ルートは、ついに解明されないままである。
【了】
.
.
.
.
.