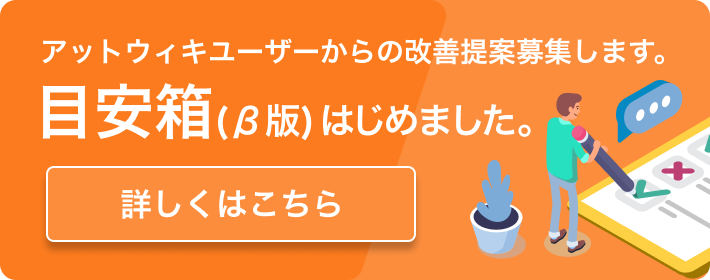「アンハッピー・エンド」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「アンハッピー・エンド」(2009/02/09 (月) 19:07:45) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
*CMWC NONEL COMPETITION6
**アンハッピー・エンド
#right(){作:江沢 稽}
「窮」の章
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
穴の底に取り残された。
穴居純子(あない・じゅんこ)は右脚の痛みに顔をしかめながら、どうしようと頭をかきむしった。長くてきれいな自慢の黒髪はもうぼさぼさだ。手も痛い。きっとさっきの衝撃で痛めたのだ。
この薄暗く冷たい空間にもう半日もいる。穴の底から見上げる空は能天気に青い。天窓のような丸く切り取られた空に向かい、助けを呼ぶ台詞を叫び続けているが誰も来ない。もうとっくに声は枯れてハスキーになっている。カラオケを歌いすぎたときのようにのどが熱い。熱いのはのどだけではない。折れた脚は醜いほどに腫れているし、かなり熱を持っている。買い換えたばかりの携帯電話も見事にぽっきりと折れてしまっている。
それにしても、助けを呼びにいったあいつはなにをしているんだ。
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
助けを呼びにいくはずが自分まで穴に落ちるとは。
下部久(しもべ・ひさし)は穴の底で泣きそうになっていた。穴に落ちている穴居を見つけ、助けを呼ぼうと慌てて駆け出したところ、心臓の発作が起きて、自分まで穴に落ちてしまうなんて。あぁ、こんなことなら携帯電話を持っておくのだった。そうすれば、その場で一一九番できたのに……いや、そもそも心臓ペースメーカーを使っているから、携帯電話は持っていないのだった。
流れ落ちそうになる涙をこらえた。泣くだけでも激痛に襲われそうで、その恐怖が涙腺をぎゅっとおさえつけていた。
折れた骨が臓器を傷つけているので身動き一つできないし、声を出して助けを求めることもできない。助けを求める声が隣の穴からも聞こえる。だが、その声に応えることもできない。自分のみならず穴井さんも姿を見せないことを社長は不思議に思わないのだろうか。
社長はなにをしているのだろうか。
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
賊に撃たれた。
金成満(かねなり・みつる)は胸に手をあてた。息をするだけでも苦しい。胸がつぶれそうだ。賊の奴、まず太ももを撃ってから、動けなくなったところを無慈悲にも心臓を狙い撃ちしてきた。商売柄、うらみを買うこともあるかもしれないとは覚悟はしていたが、まさか本当にこんなことになるとは。まずい。寒いし、それに意識が遠くなってきた。
こんなことならば、占い師のいうことを信じていればよかった。このところ、ことごとくお告げが外れるので、次、外れたらクビにしてやる、と宣告したせいでこんな目に遭っているのかもしれない。
あの占い師、今頃、どこでなにをしているのだろう。
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
人生で二度目のクビにリーチがかかった。
ミエルノ未来(みえるの・みらい)は大地が崩れていくかのような感覚に襲われていた。セクハラされたことを訴えたところ、会社から解雇を言い渡された。再就職はなかなか決まらず、明日の食べ物に困ったときに出会ったのが占いだった。駅前に座っていた謎の占い師は金も取らずに手相を見ると、お前には予言の力があると告げた。その言葉に導かれるようにやけでやってみた占い稼業があたった。
評判が評判を呼び、ついにはメディアを賑わす青年実業家、金成満のお抱え占い師にまで成り上がった。ところが最近なかなか予言が当たらない。ついには「遠からず銃撃される。幸運の鍵は煎餅屋」というお告げがあったことを知らせると腹を立てた金成に「いい加減なことをぬかしやがって。次、外れたらクビにしてやる」と怒鳴られてしまったのだ。
一応、駅前の煎餅屋を呼び出したがなんの変化もなかった。
あのちょっと珍しい煎餅屋の男は幸運を運んできてくれるのだろうか。
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
大事な「あれ」を失くした。
ベナンチョ・ム・ポームトは必死に冷静さを取り戻そうとしていた。煎餅にカモフラージュするという発想がまさかこんな事態を招くとは。留学生を装って日本に秘密工作員として潜入しての三年間で最大の危機だ。日本各地の和菓子屋で働きながら、ひそかに手がけてきた《どう見ても和菓子にしか見えない軍事品シリーズ》。第一弾は《どう見ても豆大福にしか見えない爆弾》だった。これは失敗作だった。反省を重ね、つい先日、第二弾の試作品が完成した。ところが煎餅にカムフラージュしたその試作品がどこを探しても見当たらない。
さんざん記憶をたどった末に一つの可能性に気がついた。先日、金成という青年実業家の屋敷に挨拶と称してスパイ活動に入った際に紛失したのだ。怪しいのは恥じらいもなく実業家の腕に抱かれていた奴だ。秘密に気付かれる前に「あれ」を取り戻すか、処分するかしないと。
リンダとかいったあいつは今頃、秘密に気がついてしまっただろうか。
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
どうやって助けを呼べばいいのだろう。
リンダは途方に暮れた。私は言葉がしゃべれないのだ。ようやくのことで銃を持って押し入ってきた賊から逃げてきたのに。とりあえず、前を歩いている人に追いつこう。
あの人がいい人だといいのだけれど。
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
チンパンジーが追いかけてくる。
法螺貝ふき江(ほらがい・ふきえ)は駆け出した。このところ変なものばかり見る。地底人と仲のよいアリスの白ウサギ、いや、黒ウサギ。そして、ガーナとインドを狙う地底人。
そうだ、あれもチンパンジーなどではなく、秘密の地下世界の存在を知ってしまった私を亡き者にせんとする地下帝国から仕向けられた刺客なのだ。
とにかく、あの有名な先生ならば、なにもかもなんとかしてくれるはずだ。
「求」の章
加寿内中(かずうち・あたる)との長年にわたるつき合いのなかで、私はさまざまな奇妙な事件とかかわることができた。そんな数々の調査のなかでも、のちに穴掘り青年実業家事件と呼ぶことになるこの一件ほど、ツキのあったものはない。
それは京佐久ホテル爆破予告事件とゲロン島消失事件との間に起こった出来事だったから、××年の秋のことだったはずだ。異常気象のせいというわけではないだろうが、あの年はとりわけ奇妙な事件が多かった。煎餅で有名なS県S市にある煎餅屋が軒を連ねる通称、米菓街にある加寿内の事務所を訪れた依頼人の数も半端ではなかった。同じ年の夏に大量発生したセミのごとく、たくさんの悩める人々が事務所のあるオンボロ雑居ビルの階段をすり減らした。加寿内が解決した事件も例年になく多かった。
「退屈だねぇ」
わが友にして、私立探偵の加寿内は古ぼけた椅子をキイキイと鳴らしながら、そうこぼした。独り言なのか、私に向かって呼びかけたのかはわからない。
「退屈だ。あぁ、退屈だ。理屈が退く、と書いて退屈。なるほど、うまくいったものだ。確かに最近、ボクにはこねくりまわす理屈がない」
理屈が退くうんぬんも理屈こねくりまわしているじゃないか、と私は思ったが口には出さずにおいた。
ふと加寿内のほうに目をやると、彼はけだるそうに天井を眺めていた。事件とあれば、依頼人のために全力を傾け、猟犬さながらに精力的に謎を追う加寿内であるが、打ち込む事件もなく、気力を失っているときはまるで重病人のようだ。まさに今のこの状態がそうだった。魂が抜け出てしまったかのようにうつろな瞳をしている。
このままではよくない。気晴らしに芝居か野球にでも連れていこう、と声をかけようとしたそのときだった。加寿内の表情がそれまでと一変した。くわっと目を見開き、人差し指一本を立てた右手をあごの下あたりに持ってくる。思考に集中しているときのお決まりのポーズの一つだ。どうやらなにかを嗅ぎつけたらしい。探偵独特のセンサーを持たない私にもそれくらいのことはわかる。私は探偵ではないが、加寿内のよき友人で数少ない理解者だ。少なくともそう自負している。
「どうやら事件のようだよ。それも尋常でない事件らしい」
椅子に腰掛けたまま、加寿内がいった。不謹慎だが、このとき私は事件が起きてよかった、これで加寿内も元気になるだろう、と思ってしまった。
「加寿内、どうしてそんなことがわかるんだい?」
「簡単なことさ、君。このオンボロ物件の雑居ビルのエレベーターには顕著な特徴が二つある。一つは、非常に昇降がゆっくりで、呼び出しをしてもその階に到着するまで時間がかかること。二つ、エレベーターが動くとこのビル自体が振動すること」
確かにこのビルは古い。前の道路を大型トラックが通過しただけでも建物が揺れる。あまりに頻繁にゆらゆらぐらぐらするので、もう私などは気にもしなくなってしまっている。
「ついさきほどから生じている揺れはエレベーターによるものだ。鈍感で観察力の低い君には判別がつかないだろうが、ボクはビルの揺れ具合から、道路を通過した揺れなのか、風によるものなのか、あるいはエレベーターの作動に伴うものか、地震なのか、揺れの原因を特定できる。つけ加えるならば、車の通過による揺れならば車種も、エレベーターによるものならば、何階から何階へ向かっているのか、今、どのあたりを箱が通過しているのかまで八割がた当てることができる。ちなみに今は六階から一階へ向かう途中で三階にさしかかったあたりだね」
疑うことを知らない素直な、いささか素直すぎるくらいお人よしな読者のために私は書いておかなければならない。エレベーターの位置を推理するなんて、いくらなんでもそんな芸当は無理だ。もちろん、ときたま加寿内の推理が当たることはある。だが、これは確率の問題だ。下手な鉄砲も、強引で無茶苦茶な推理も、数撃ちゃ当たるのだ。だから、さきほどの加寿内の発言は話半分で聞いてもらいたい。わが友、加寿内が幾つかの不思議な謎を解明したことも、警察に先んじて難解な事件を解決したことも事実だ。しかし、そんな成功事例の二倍、三倍、いや、何十倍もの手ひどい間違いをしていることもまた忘れてはならない事実なのだ。
「今、エレベーターを呼び出した一階の誰かさんは、待つことにしびれを切らして階段を上り始めた。ほら足音が聞こえるだろう。しかも、その足音は三段目のところだけ大きくなった。これは三段目が少し低くなっていることを知らない人間が、予想していたところに段がなかったために踏み外すような感じで思い切り体重をかけてしまったことで起きた現象だ。このビルの階段を日常的に使う人間ならば、二階へ向かう階段の三段目が低いことは知っている。段を踏み外しかけるなどという恥ずかしい真似はしない。つまり、今、階段を上ってきている人物はこのビルを訪れるのは始めての人間だ。しかも、到着の遅いエレベーターを待つのをあきらめて階段を使うことを選択している。これはこの人物の目的の階がそれほど上でないことを示している。上の階だったら、待ってでもエレベーターを使うだろうからね。多くの人間は三階以上ならエレベーターを使うだろう。だから、この人物の目的の階は二階だ。二階にはボクの事務所しかない。探偵事務所に来る人間には集金の人やらなんやら
いろいろいるが、初めて来るのは、まぁ依頼人とみて間違いはないだろう」
「なるほどね」
「しかも、プライドの高いある程度、高齢の人だな。小さいお孫さん、それもかなり運動神経のすぐれた身のこなしの軽いちびっこを連れてきている」
「どうしてそんなことまで!」
「これだけボクたちが話をしているにもかかわらず、依頼人はまだ二階の事務所にたどり着いていない。これは足腰が弱いからだろう。並みの体力を持った人なら、とっくに階段を上りきっているだろうからね」
「二階に来たはいいが迷っているのでは?」
「迷う? どうやって? 絶望的な方向音痴の君にだってそんなことはできないね。さっきもいっただろ。この階にはこの事務所しかない。あとのテナントは空いている」
私は人気のない寒々としたやたらと自分の足音が響く廊下を思い浮かべて納得した。
「でも、加寿内、足腰が弱いのはなにも高齢者とは限らないじゃないか。たとえば、そうだな、足を怪我しているとか」
「いや、それはないね。足音をよく聞けばわかる。あの足音は左右の足で大きく違わない。片足だけを怪我しているのではなく、両方の足がバランスよく弱っている。だから、年齢によるものだ」
「プライドが高い、というのはさすがにあてずっぽうだろう?」
「おやおや、まったく困ったものだね。実に明確な根拠があるじゃないか。足が弱っているにもかかわらず、エレベーターを待たなかったんだよ。かなりプライドにこだわるたちとみたね。これも高齢者であることの傍証さ」
この発言は人生の先輩方にとっていささか礼を失しているのではないか、と思ったが口には出さずにおいた。どうせ名探偵は聞く耳を持ってはいないだろう。
「お孫さんを連れているというのは?」
「足音だ。もう一つ別の足音がしているのに気がつかなかったのかい?」
気がつかない。気がつくわけがない。もう一つも何も足音など聞き取れない。
「まぁ、無理もない。ごく小さな足音だからね。そう、小さな足音。だから、その人物の体重も軽い。察するに子どもか猿のたぐいだ。もう一人の人物の年齢が高いことから考えて、彼あるいは彼女のお孫さんというのが妥当だろう。まさかペットの猿を連れてきたわけではあるまい」
「運動神経がいい、というのはなぜわかる?」
「おちびの足音の回数はもう一つの足音の半分だ。これがどういうことだかわかるかい?」
質問に対して質問で返された。いくら考えても私にはわからないとは思ったが、一応、貧弱な脳みそを働かせてみる。しかし、その作業をすぐに断念した。
「降参だ、加寿内。どういうことなんだい?」
「簡単なことじゃないか。一段抜かしだよ。君も子どものころやらなかったかい?」
「そんな小さな子どもに一段抜かしができるかな。猿のように小さな体なんだろう?」
「おいおい、じゃあ君は猿がついてきたっていうのかい? まぁ、そんな疑問もすぐに解決するさ。なぜなら、すぐそこに依頼人がいるんだからね、ノックは無用です、カギはあいてますから、どうぞ!」
ギイと嫌な音をたててゆっくりと事務所のドアが開き、、驚きの表情をした老婆が姿を見せた。
「どうしてあたしが来たことがわかったんですか?」
毒々しいほどに紫に染めたもじゃもじゃの髪を揺らして依頼人は尋ねた。
「探偵の能力を使えばこれくらい簡単なことですよ。そんなことよりこちらのソファにどうぞ、お孫さんも一緒に」
椅子に深く腰掛けて、依頼人とは正反対のほうを向いたまま告げた加寿内の言葉に、老婆の顔がこわばった。
「孫! どうして?」
「簡単なことですよ、探偵の訓練を積んだものにとっては……」
そのとき私はあることに気がついて加寿内の言葉をさえぎった。それは多少、探偵としての加寿内のプライドを傷つけることになったかもしれないが、私はそうせずにはいられなかったのだ。
「猿だよ、加寿内」
「なんだって? 聞こえなかったが」
「猿だ」
「さる?」
「猿」
「サル?」
「猿」
「猿!」
名探偵らしからぬ素っ頓狂な声がして、なにかが倒れる音が続いた。私は喧騒を背中で聞いた。振り返ることができなかったのだ。
依頼人の後ろにいたのは子ども、ではなく、猿。高齢の依頼人の顔はしわくちゃで、猿のような雰囲気はあるが、人間であることは間違いない。
猿と依頼人とを交互に見やる。そうしているうちに猿のほうもどこか困ったような顔をしていることに気がついた。気のせいだろうか。
「あんたが有名な探偵の先生かね」
見た目の割にはしっかりとした口調で依頼人の女性が私に尋ねた。
「いえ、私は手伝いをしている者で、加寿内はあちらです」
ようやくここで私は振り返り、加寿内を指し示した。思ったとおり、椅子は倒れていたが、加寿内はいつもの表情だった。わずかの時間に冷静さを取り戻したのだろう。切りかえの早いところがわが探偵の売りの一つだ。
「さぁさぁ、どうぞなかへ。いったい、どんな調査をご依頼ですか? 尾行? 暗号解読? なんでもお任せください」
調子よく語りかけながら、加寿内は依頼人をソファに座らせた。開けっ放しの扉のわきで私と猿は仲良く並んで立ちつくしている。
「なにをしているんだ、ぼぉっと突っ立ってないでドアを閉めろよ」
「あ、いや、加寿内、でも、この猿は……」
「失礼ですが奥様、あちらのホ乳類とのご関係は?」
ふん、と依頼人が鼻を鳴らした。
「そいつはね、あたしの命を狙ってたんだよ。でも、もう安心だ。逃げられりゃしない。もっとも、もう観念して逃げるのはあきらめたらしいがね」
「お猿さんとはずいぶんと変わった暗殺者ですね。もっとも、ミス……失礼、まだ、お名前をうかがっていませんでしたね」
「あたしかい? あたしゃ、法螺貝ふき江ってんだよ。いっとくけど、嘘でも下手な冗談でもないからね。町の連中は寄ってたかってあたしのことを嘘つきババアだなんだってひどいこというけどね。そんなことは信じないでくださいよ」
思い出した。このご婦人はあのふき江婆さんだ。
「あなたが嘘つき? まったくひどいことをいう奴らもいるんですね」
そういいながら、加寿内がちらりと私に目配せをした。その意味はわかる。鵜呑みにするな、ということだろう。
この依頼人はとんでもないほら話をして、町を騒がせている有名人なのだ。町で評判の留学生ベナンチョ・ム・ポームト君は実は某国のスパイで、駅前の煎餅屋で働きながら、煎餅を使って暗号をやり取りしている、という話もふき江婆さんの仕業だった。最近では、この町に住む青年実業家、金成満が実は巷を騒がす怪盗ラット・キッドその人である、なんて話も吹聴していた。
ベナンチョ君やラット・キッドのように明らかに嘘だとわかる荒唐無稽な話ならば、まだいい。困るのは真偽のほどがはっきりしないような話、嘘かもしれないけれど万が一に本当だった場合、一大事となるケースだ。先日、過激な政治団体の連中により町長の秘書が監禁されている、と大声でふき江婆さんが触れ回るという事件があった。政治団体うんぬんといういかにもふき江婆さん好みの派手な部分は聞き流されたが、監禁の部分は無視できなかった。
それというのもちょうどそのとき、件の秘書が失踪していたからだ。警察と町長一派はふき江婆さんとともに監禁場所だという山小屋へ向かった。結局、この大騒ぎは空騒ぎに終わる。まさにこれから山小屋に踏み込もうというその矢先に、当の秘書から町長の携帯電話へ「夏休み、楽しかったです。今からお土産を持ってまいります」という能天気な連絡が入ったからだ。
後から聞くところによると、秘書の申請した休暇願はしっかりと町長のハンコを押されて、書類の山に埋まっていたそうだ。なお、この情報源はふき江婆さんではない。
「それで法螺貝さん、どんなご依頼で? その暗殺者を仕向けた連中の正体を探れ、ということですか?」
きめの整ったきれいな顔で加寿内は法螺貝に尋ねる。
「それは大体、見当がついているんだ」
また始まったぞ、という顔をした私に気がついたのか、ちらと制すような視線を送ってよこしたあとで加寿内は厄介な依頼人に尋ねた。
「ほう、それはそれは。いったい、どこのどいつです?」
「地底人さ」
「地底人!」
あきれて言葉を失う私とは対照的に、加寿内は心の底から驚嘆したように大きな声を出した。そんな加寿内の姿に満足したのか、得意そうに法螺貝は続ける。
「あんた、地球のなかってどうなっていると思う?」
質問を投げかけたが、問いかけるという意思は微塵もないようだった。こちらの答えを待たず、答える間も考える間も与えず、ふき江婆さんは続けた。
「地球のなかはマグマがどろどろしている、とかみんな信じているけどね、ありゃ、嘘さ。うーそ。ほんとはね、地底人が住んでいるんだよ。地底人がね、地下帝国を築いているんだよ。地球人の文明を利用して、人間以上に高度な文明を創りあげているのさ」
「ほう、地下帝国。最近の異常気象も彼らの仕業なんですかね?」
「そうさ、そうに違いない。さすがあんた探偵だね。そうなんだよ、あいつらのせいなのさ。いよいよあいつら地底人が地球人から地球を乗っ取ろうと動き始めたんだよ、怖いねぇ」
ちっとも怖くなさそうに依頼人はいう。そのとき、狭いうえに乱雑な事務所にものの倒れる音が響いた。
「俺のことを忘れてもらっちゃ困るぜ、ということですかね」
加寿内が物音の原因をつくった主に向かっていった。犯人は猿だった。猿が机の上に山積みになっていた書類やら灰皿やら、よくわからない小物やらをひっくり返したのだった。あわてて片づけようとした私を手で制し、加寿内が口を開いた。
「ところで法螺貝さん、その猿が地下帝国の仕向けた刺客だというのは、どういうことなんでしょうか」
「ここに来てすぐにいわなかったかい? ずっと追いかけられているんだよ、そいつにさ」
「おっしゃっていましたね、そういえば」
「あれから、ずーっとさ」
「といいますと?」
「あたしねぇ、見ちゃったんだよぉ」
迷惑な依頼人が語り始めたのは、実に奇妙な話だった。
「Q」の章
こほんと一つ、軽いからぜきをして、ふき江婆さんはしゃべりだした。
「あたしが初めて異変に気づいたのは、一ヶ月くらい前のことだったね。あたしはアリスのウサギを見つけたのさ」
「アリスの、というと、あれですか。『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』。作者はルイス・キャロルでしたっけ」
「そうだよ、あの話に出てくるだろう。しょっちゅう懐中時計を取り出しては時間を気にしてバタバタしているウサギが。あのウサギがいたんだよ、本当に」
「どこにいたのですか?」
目を輝かせて質問をする加寿内とは反対に、私はふき江婆さんのほら話にはそれほど興味はなく、テーブルの上のかた焼き煎餅に手を伸ばした。
「聞いて驚かないでくださいよ、探偵さん。アリスのウサギはね、夜毎、金成の屋敷に出てくるのさ」
「金成、あの青年実業家の金成満さんですか」
「そうだよ、あの成金め。やっぱり後ろ暗いことをやってたんだね。あの金は地底人との秘密の取引で稼いだんだよ。あいつの無駄にどでかい屋敷の庭に地下帝国の入り口があるんだ」
「地下帝国の入り口ですか」
「そうさ。そうでなきゃ、どうしてあんなとこにでっかい穴が開いているんだってんだ」
「あな? あぁ、穴ですか、占いの」
金成邸の広大な庭の片隅にある穴のことなら私も知っていた。もちろん、加寿内も。この街の人間なら、ほとんどが知っていることだろう。
多くの経営者と同じように金成は重要な決断をときに占いに頼ることがあった。そのせいでしばしば金成も奇妙な行いをすることがあった。金成邸にある穴も占いの産物といえるだろう。
半年ほど前、金成はある企業の株式の買占めを画策していた。そのタイミングが適切かどうか悩んだ金成はお抱えの占い師ミエルノ未来に相談を持ちかけた。ミエルノは庭に二つの穴を掘り、そのなかで瞑想して金成自身が決断するのが最良であると告げた。若き実業家はさっそく庭の一角に自身で大きな穴を掘り、お告げに従い、四日間、穴の底で瞑想にふけった。その結果、買占めを見送ることにした。驚くべきことにこの判断は正しかったことがのちに明らかになる。買収をもくろんでいた企業の粉飾決算の事実とセクハラ騒動がほどなく報道され、この会社は倒産。このエピソードは金成のカリスマ性をいっそう強く世間にアピールすることとなった。
「占い? そういわれちゃいるがほんとのとこは違うのさ。あれは地底人の仕組んだ陰謀さ。あたしは見つけちまったんだよ。あれは一ヶ月くらい前のことさ。あたしはたまたまあの屋敷のあたりを歩いてたんだ。なにかぴんとくるものがあってね。そしたらさ、あの屋敷の庭をなにかが走ってたんだ。そりゃ、すごい速さでね。よく見ると、月明かりに映し出されたそいつの頭からは長いなにかが生えてるみたいだった。なんだろうと考えたら、わかったんだ。ありゃ、ウサギだ、ウサギの耳だってね」
法螺貝の婆さんはやせ衰えた歯茎を見せつけるよう笑った。
「それもただのウサギじゃないよ。人間くらいある大きさだ。なんだろうと思ってあたしはこっそり監視することにした。そうしたら、ウサギの奴、急に止まったんだ。あんた、そのあとでなにが起こったと思う?」
「なんでしょう?」
鼻の穴を膨らませ、興味津々といった様子で加寿内が尋ねた。そんな相棒とは反対に私はこんな馬鹿馬鹿しい話にこれ以上つき合っていられない、と冷めていた。もとから散らかっていた部屋をさらにひどい状態にしている猿と、この惨状を片づけなければならないということのほうに興味は大きく傾いていた。
「ウサギの奴、胸のあたりから何かを取り出すようにしたんだ。そう、懐中時計だよ。首にかけた懐中時計を胸元から取り出して時間を見たんだ。そして、なにかロープみたいなものを放り投げると地面にもぐっていったんだ。地面に穴が開いていて、そこが地下帝国の入り口になっているんだね。ロープみたいに見えたのは縄梯子だったんだろうよ」
「面白い! それで?」
「しばらくして出てきたよ。出てくるやいなや、縄梯子をくるくるっとまとめてポケットに突っ込むと、また懐中時計をいじって屋敷のほうへ猛然と駆け出したんだ。千切れるんじゃないかってくらい耳をぶらぶらさせてさ。いや、実際のところ、耳は片方しかなかったんだ。一本は千切れちまったんだよ、きっと」
「片耳のアリスの白ウサギ!」
「白じゃないんだ、黒だよ。月明かりくらいではっきり見えなかったけど、黒だったね」
「その黒ウサギの正体を知りたいというわけですね」
「そうじゃないんだよ、探偵さん。正体はわかっているんだ。あのウサギこそ地底人なんだよ。だってさ、そいつはしばらくするとまた入り口に戻ってきて、時計を見て縄梯子を投げ込むと地下帝国にもぐりこんだ。すぐまた出てくると縄梯子を回収して時計を気にして、また屋敷のほうへ大慌てで駆け出す。これを何回も何回もくり返したんだよ」
「実に興味深い。法螺貝さん、あなたは素晴らしい人だ。よく観察を続けました。その忍耐力といい、好奇心の強さといい、あなたには脱帽ですよ」
加寿内の言葉に気をよくしたのだろう。ふき江婆さんは得意満面といった表情を浮かべている。
「それだけじゃないんだよ。ウサギはその奇妙な行動を次の夜も、その次の夜も同じようにやり続けたんだ。この一週間ずっとさ」
もしこの話が作り話ではないのなら、毎晩、飽きもせずに観察をしていたその根性は確かにすさまじいものだ。
「一週間、監視をやって気づいたことがもう一つあるんだ。あの金成のところの書生は地底人とつながっているスパイだよ。あの若造、毎晩、九時半ごろにあの穴をのぞきこんで懐中電灯でなにか合図を送っているんだ。ちょっと見には戸締りの確認をしながら見回りをしているようにしか見えないけど、あれは地底人へ暗号を送っているんだよ」
「書生と黒ウサギは接触しないのですかね」
「その点もさすがだよ。あいつらは地球人に気づかれないように慎重にやっている。書生がサインを送っている姿をウサギの奴は遠くからこっそり眺めているだけなんだ。地表では決して接触しない」
「なるほど、狡猾ですね」
「そうなんだよ、だから、夕べのことも罠なんじゃないかと思ってさ。それであんたのところに来ることにしたんだよ」
ようやく、訪問の目的が明らかになるようだ。もっとも私はこの婆さんの話をもう信用してはおらず、加寿内がどうやって追い返すのかが気になってばかりいた。一応、相談にのったという形をとるために私は初めて依頼人に質問をした。
「夕べ、なにかあったんですね? それを簡単に話してもらえますか?」
「昨日の夜もあたしは地下帝国への入り口の見える監視ポイントにいったんだ。夕べはいつもと違っていたんだよ。毎晩、八時過ぎには出てくるウサギの奴がなかなか姿を見せないんだ。そのへんから、今日はなんかあるなと勘づいたね。ウサギの奴が出てきたのは九時過ぎだった。いつもと違うのはしばらく地下帝国にいたことだ。九時半ごろ、いつものようにスパイ野郎がやってきて穴をのぞいた。すると、あの若造はなにか驚いたようにしゃがんで穴に向かってよくわからないことを叫んだ。地底人語だね。急に立ち上がると外国の名前を叫ぶんだ。『火とガーナ』とか『二、インド』とか。たぶん、地底人との秘密の暗号だね」
「火とガーナ、二、インド……」
ごにょごにょとくり返す加寿内に気づかずに法螺貝の婆さんは続ける。
「何回か叫んだ後、懐中電灯を放り出して駆け出したんだ。そして、消えちまったんだ」
「消えた!」
「正確にいうならば、もう一つの地下帝国の入り口に飛び込んだんだ。吸い込まれるようにね」
「もう一つの穴にですか」
「あぁ、そうさ。ウサギの奴がいつも使っている穴とは別にあの屋敷にはもう一つ穴がある。ウサギの穴とは五メートルくらい離れているかな。あたしはあれはカモフラージュのためのダミーの穴だと思っていたが、両方とも地下帝国につながっているんだね」
「それでそのあとはどうなりました?」
「スパイ野郎がいなくなるとすぐにウサギが出てきた」
「それはどちらの穴から?」
「いつもの穴さ。出てきて縄橋子をまとめるところまでは一緒だった。夕べはなぜかまるめた縄梯子を穴に投げ込んだんだ。そして、時計も見ずに屋敷のほうへ駆け出してった。しばらくすると走って戻ってきて、そのまま穴へぴょいっと飛び込んだんだ」
「いつもの穴にですね」
確認する加寿内にうなづく依頼人。
「うーん、これはすごいことが起こっているようだよ」
目を血走らせて加寿内が私に告げる。
「だろう? だからさ、なにが起きているか確かめに一緒にいってほしいんだよ」
依頼人の頼みをなんのかんのとうまく断るのかと思っていたが、なんと加寿内はこう答えたのだ。
「わかりました。あなたに頼まれなくてもそうしますよ。これは一大事です。一刻も早く救い出さないと。さぁ、出かけよう。準備は五分でできるね?」
そう問いかけてきた加寿内に私はこう返すのが精一杯だった。
「猿はどうする?」
しばらく困ったように眉をしかめた後で探偵は歌うようにいった。
「大家さんに預かってもらうことにしよう。法螺貝さん、すこしだけお時間をいただきますよ」
「休」の章
米菓街にある煎餅屋で店番をしていたベナンチョ・ム・ポームトは不思議な光景を目撃した。大家が猿を連れて歩いているのだ。
「オーヤサン、コンチーワ、ゴキゲンヨウカ? デデデノデ」
ベナンチョは実は日本語は漢字の読み書きも含め完璧にできる。「憂鬱」も「薔薇」も漢字で書けるし、小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』も夢野久作の『ドグラ・マグラ』も読んで理解していた。それに九ヶ国語をも自由に操れるのだが、わけあって片言の日本語しかできないように装っている。
「あぁ、ベナンチョ君。バイト? 大変だねぇ」
「ソレ、ドウシタデスカ?」
「ん? あぁ、このお猿さん? うちの店子の探偵さんからしばらく預かってくれって頼まれてねぇ。それで散歩させてるんだよ」
「ソイツハ、テェーヘンダ、オヤブン」
「どうしたの? 時代劇にでもはまったのかい」
「コドモンコロガ、メニ、ハイカラカ」
右手で印籠を突き出すような仕草をしながら、すばやく左手で煎餅を裏返した。愉快そうに笑う大家は、道の反対で携帯電話をいじるふりをしながら、ひっくり返された煎餅に油断なく目をやる男の存在には気がついていない。
「ソーダ、コレ、モッテッテクンナマシ」
「お、なにかもらえるのかい?」
しめしめと顔をほころばせる大家に、ベナンチョは煎餅の入った箱を手渡した。
「ボクガ、ハチュメイ、シマシタ。スゴイヤロ」
「はちゅめい? あぁ、発明ね。そう、ベナンチョ君、新製品の開発もやってるんだ」
「コレ、チョー、カタイヨ。ボクノ、キック、デモ、ワレナイ」
「本当? だってベナンチョ君、ムエタイのチャンピオンだったんでしょ。それでも割れないの? そんなの食べられないよ。おいしいの?」
「カナリノシャチョーサン。オイシイ、イッテタ」
「かなりの……あぁ、金成社長ね。へぇ、やっぱりあの人も変わった人だねぇ」
「救」の章
タクシーを飛ばすこと、十数分。私たち三人は金成邸の前に降り立った。
「おい、加寿内。ここは屋敷の裏側じゃないか。どうしてこんなところで……」
「玄関から入るのが紳士のやり方だということは承知しているよ。だが、今回は急を要する。柵を乗り越えて庭に入ることを許してもらおう。さぁ、いくぞ。法螺貝さんに手を貸すんだ」
しぶしぶ、私は同意し、なんとかふき江婆さんに柵を越えさせることに成功した。
「法螺貝さん、穴というのはあれですか?」
「そうだよ。でも、あんた、危なくないのかい? 地底人にさらわれたりなんてことは……」
「ご心配なく、そのときは私が全力をもってあなたをお守りします。もっとも……」
「なんだい?」
「地底人も地下帝国も存在しませんがね」
加寿内の言葉に早足で歩いていた依頼人が足を止める。
「なんだいなんだい! あんたまであたしを嘘つき扱いかい。あんただけは信じてくれたと思ったのに……それなら、なんでこんなところまであたしを。ひどいじゃないか」
「信じてますよ。あなたは嘘をついていない。あなたが見たことは本当にあったことです。だが、あなたの解釈は間違いです」
「なにをいうんだい。一緒じゃないか」
「一緒じゃありませんね。まったく違います。あなたはすばらしい観察者だ。既成概念にとらわれることがない。信じがたい光景を目にしてもそれを常識で考えてありそうにないことだからと見なかったことにしようとはしない立派なかたです。いいですか、あなたがいなければ救えない人が生まれてしまうところだったんですよ」
「わけがわからないよ!」
「わかるようにしてさしあげましょう! さぁ、一緒に来るんです。あなたのおかげで救われる人のもとへ」
その言葉は偏屈な依頼人の心を動かしたようだ。法螺貝の婆さんはゆっくりとだが、再び歩き始めた。歩き出すとすぐに二つの穴が見えてきた。
加寿内にうながされる形で、依頼人と私は穴のなかをそっとのぞきこんだ。
「地下帝国はありません。地底人はいません。あるのは深い穴と、その底にいる哀れな人間です」
名探偵の言葉どおり、深い穴の底には一人の女性がぐったりと倒れていた。
「大丈夫ですか」
加寿内の問いかけに女性はゆっくりと首を縦に動かした。
「早く、救急車を」
慌てて携帯電話を取り出して、私は救急車を要請した。しどろもどろになりながらようやく通報を終えたところで加寿内が耳打ちをしてきた。
「もう一つの穴も見てきてごらん」
第二の穴にもさらなる衝撃の光景が待ち受けていた。そこにも一人、人間がいたのだ。
「大丈夫ですか。今、救急車を呼びましたから」
穴の底で男が何度も何度もうなづく。そのとき、後ろではっと息を飲む気配があった。慌てて振り向くと、そこにはふき江婆さんが驚愕の表情で固まっていた。
「どうしたんです? 法螺貝さん」
あまりの形相に思わず尋ねてしまう。
「あ、あいつはあのスパイの若造じゃないか」
「スパイ? あぁ、金成さんの書生さんなんですね」
無言で二度、依頼人はうなづいた。
「ご安心ください、法螺貝さん」
陽気な声をかけながら、加寿内が私たちのほうに歩み寄ってきた。歩きながら加寿内は語り始める。
「その人はスパイではなくただの書生です。そして、あなたが夕べ見た書生さんのあれこれもただの事故。もし、あなたが見ていなかったら、そして、私のところに来なかったならば、かわいそうにこの青年はもうしばらく穴の底で痛みに耐えていたことでしょう」
地底人のスパイが消えたなんてありそうもない話はやはりなかった話で、本当にあったことといえば、ただの事故。つまりはそういうことだったのだ。
「法螺貝さんが聞いたという謎の言葉。ガーナとかインドとかいうのは、こうだったんですよ。『人が穴にいるぞ』ってね」
「なるほどね。でも、なぜ二人とも携帯電話で助けを呼ばなかったんだ」
「そうだね、二人とも携帯電話を持っていないとか、壊れてしまったとか、なにか事情があったのだろうよ。そんなことよりもね、これでボクの推理が正しかったことが判明した。この推理が正しければ、まだ救い出さねばならない人がいる。もう手遅れかもしれないが、ボクはいくよ」
「待てよ、一緒に……」
「いや、君はここにいてくれ。そして、救急隊が到着したら、ケータイに電話をくれ。きっとだよ。そして、もう一つ、怪我人から、特にあの長い髪の女性から決して目を離すんじゃないぞ。わかったね」
真剣な表情に押し切られるように私は黙って何度もうなづいた。加寿内の残した言葉の意味を考えながら、私は法螺貝さんとともに救急車の到着を待った。五分も経たずにサイレンが聞こえてきた。私は依頼人を穴のそばに残し、もう一度、柵を越えると、道路に出て救急車を待った。白い車から飛び出してきた隊員を穴まで案内したところでいいつけどおり私は加寿内に電話をかけた。相棒は救急隊の人とかわれ、とだけ告げ、私の気になっていることなど少しも話してくれない。いい加減もう慣れたことだが、身勝手な人間だ。
電話をかわった隊員はしばらくすると顔色を変えて、部下らしき若い男になにかを指示した。すぐに部下のほうがなにかの機材を持ってくると、二人して屋敷のほうへと駆け出していく。
「いったい、なにがあったんだろうね」
私の胸のなかにある疑問を依頼人が口に出した。この状況を把握しているのはわが名探偵だけだろう。いまだ謎のままのアリスの黒ウサギをはじめ、まだまだ知りたいことが山積みだ。
それらの謎がすべて究明されたのは、金成邸の庭ではなく、病院だった。
[[アンハッピー・エンド2]] へ
*CMWC NONEL COMPETITION6
**アンハッピー・エンド(前編)
#right(){作:江沢 稽}
「窮」の章
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
穴の底に取り残された。
穴居純子(あない・じゅんこ)は右脚の痛みに顔をしかめながら、どうしようと頭をかきむしった。長くてきれいな自慢の黒髪はもうぼさぼさだ。手も痛い。きっとさっきの衝撃で痛めたのだ。
この薄暗く冷たい空間にもう半日もいる。穴の底から見上げる空は能天気に青い。天窓のような丸く切り取られた空に向かい、助けを呼ぶ台詞を叫び続けているが誰も来ない。もうとっくに声は枯れてハスキーになっている。カラオケを歌いすぎたときのようにのどが熱い。熱いのはのどだけではない。折れた脚は醜いほどに腫れているし、かなり熱を持っている。買い換えたばかりの携帯電話も見事にぽっきりと折れてしまっている。
それにしても、助けを呼びにいったあいつはなにをしているんだ。
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
助けを呼びにいくはずが自分まで穴に落ちるとは。
下部久(しもべ・ひさし)は穴の底で泣きそうになっていた。穴に落ちている穴居を見つけ、助けを呼ぼうと慌てて駆け出したところ、心臓の発作が起きて、自分まで穴に落ちてしまうなんて。あぁ、こんなことなら携帯電話を持っておくのだった。そうすれば、その場で一一九番できたのに……いや、そもそも心臓ペースメーカーを使っているから、携帯電話は持っていないのだった。
流れ落ちそうになる涙をこらえた。泣くだけでも激痛に襲われそうで、その恐怖が涙腺をぎゅっとおさえつけていた。
折れた骨が臓器を傷つけているので身動き一つできないし、声を出して助けを求めることもできない。助けを求める声が隣の穴からも聞こえる。だが、その声に応えることもできない。自分のみならず穴井さんも姿を見せないことを社長は不思議に思わないのだろうか。
社長はなにをしているのだろうか。
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
賊に撃たれた。
金成満(かねなり・みつる)は胸に手をあてた。息をするだけでも苦しい。胸がつぶれそうだ。賊の奴、まず太ももを撃ってから、動けなくなったところを無慈悲にも心臓を狙い撃ちしてきた。商売柄、うらみを買うこともあるかもしれないとは覚悟はしていたが、まさか本当にこんなことになるとは。まずい。寒いし、それに意識が遠くなってきた。
こんなことならば、占い師のいうことを信じていればよかった。このところ、ことごとくお告げが外れるので、次、外れたらクビにしてやる、と宣告したせいでこんな目に遭っているのかもしれない。
あの占い師、今頃、どこでなにをしているのだろう。
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
人生で二度目のクビにリーチがかかった。
ミエルノ未来(みえるの・みらい)は大地が崩れていくかのような感覚に襲われていた。セクハラされたことを訴えたところ、会社から解雇を言い渡された。再就職はなかなか決まらず、明日の食べ物に困ったときに出会ったのが占いだった。駅前に座っていた謎の占い師は金も取らずに手相を見ると、お前には予言の力があると告げた。その言葉に導かれるようにやけでやってみた占い稼業があたった。
評判が評判を呼び、ついにはメディアを賑わす青年実業家、金成満のお抱え占い師にまで成り上がった。ところが最近なかなか予言が当たらない。ついには「遠からず銃撃される。幸運の鍵は煎餅屋」というお告げがあったことを知らせると腹を立てた金成に「いい加減なことをぬかしやがって。次、外れたらクビにしてやる」と怒鳴られてしまったのだ。
一応、駅前の煎餅屋を呼び出したがなんの変化もなかった。
あのちょっと珍しい煎餅屋の男は幸運を運んできてくれるのだろうか。
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
大事な「あれ」を失くした。
ベナンチョ・ム・ポームトは必死に冷静さを取り戻そうとしていた。煎餅にカモフラージュするという発想がまさかこんな事態を招くとは。留学生を装って日本に秘密工作員として潜入しての三年間で最大の危機だ。日本各地の和菓子屋で働きながら、ひそかに手がけてきた《どう見ても和菓子にしか見えない軍事品シリーズ》。第一弾は《どう見ても豆大福にしか見えない爆弾》だった。これは失敗作だった。反省を重ね、つい先日、第二弾の試作品が完成した。ところが煎餅にカムフラージュしたその試作品がどこを探しても見当たらない。
さんざん記憶をたどった末に一つの可能性に気がついた。先日、金成という青年実業家の屋敷に挨拶と称してスパイ活動に入った際に紛失したのだ。怪しいのは恥じらいもなく実業家の腕に抱かれていた奴だ。秘密に気付かれる前に「あれ」を取り戻すか、処分するかしないと。
リンダとかいったあいつは今頃、秘密に気がついてしまっただろうか。
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
どうやって助けを呼べばいいのだろう。
リンダは途方に暮れた。私は言葉がしゃべれないのだ。ようやくのことで銃を持って押し入ってきた賊から逃げてきたのに。とりあえず、前を歩いている人に追いつこう。
あの人がいい人だといいのだけれど。
窮地だ! まさかこんなことになるとは。
チンパンジーが追いかけてくる。
法螺貝ふき江(ほらがい・ふきえ)は駆け出した。このところ変なものばかり見る。地底人と仲のよいアリスの白ウサギ、いや、黒ウサギ。そして、ガーナとインドを狙う地底人。
そうだ、あれもチンパンジーなどではなく、秘密の地下世界の存在を知ってしまった私を亡き者にせんとする地下帝国から仕向けられた刺客なのだ。
とにかく、あの有名な先生ならば、なにもかもなんとかしてくれるはずだ。
「求」の章
加寿内中(かずうち・あたる)との長年にわたるつき合いのなかで、私はさまざまな奇妙な事件とかかわることができた。そんな数々の調査のなかでも、のちに穴掘り青年実業家事件と呼ぶことになるこの一件ほど、ツキのあったものはない。
それは京佐久ホテル爆破予告事件とゲロン島消失事件との間に起こった出来事だったから、××年の秋のことだったはずだ。異常気象のせいというわけではないだろうが、あの年はとりわけ奇妙な事件が多かった。煎餅で有名なS県S市にある煎餅屋が軒を連ねる通称、米菓街にある加寿内の事務所を訪れた依頼人の数も半端ではなかった。同じ年の夏に大量発生したセミのごとく、たくさんの悩める人々が事務所のあるオンボロ雑居ビルの階段をすり減らした。加寿内が解決した事件も例年になく多かった。
「退屈だねぇ」
わが友にして、私立探偵の加寿内は古ぼけた椅子をキイキイと鳴らしながら、そうこぼした。独り言なのか、私に向かって呼びかけたのかはわからない。
「退屈だ。あぁ、退屈だ。理屈が退く、と書いて退屈。なるほど、うまくいったものだ。確かに最近、ボクにはこねくりまわす理屈がない」
理屈が退くうんぬんも理屈こねくりまわしているじゃないか、と私は思ったが口には出さずにおいた。
ふと加寿内のほうに目をやると、彼はけだるそうに天井を眺めていた。事件とあれば、依頼人のために全力を傾け、猟犬さながらに精力的に謎を追う加寿内であるが、打ち込む事件もなく、気力を失っているときはまるで重病人のようだ。まさに今のこの状態がそうだった。魂が抜け出てしまったかのようにうつろな瞳をしている。
このままではよくない。気晴らしに芝居か野球にでも連れていこう、と声をかけようとしたそのときだった。加寿内の表情がそれまでと一変した。くわっと目を見開き、人差し指一本を立てた右手をあごの下あたりに持ってくる。思考に集中しているときのお決まりのポーズの一つだ。どうやらなにかを嗅ぎつけたらしい。探偵独特のセンサーを持たない私にもそれくらいのことはわかる。私は探偵ではないが、加寿内のよき友人で数少ない理解者だ。少なくともそう自負している。
「どうやら事件のようだよ。それも尋常でない事件らしい」
椅子に腰掛けたまま、加寿内がいった。不謹慎だが、このとき私は事件が起きてよかった、これで加寿内も元気になるだろう、と思ってしまった。
「加寿内、どうしてそんなことがわかるんだい?」
「簡単なことさ、君。このオンボロ物件の雑居ビルのエレベーターには顕著な特徴が二つある。一つは、非常に昇降がゆっくりで、呼び出しをしてもその階に到着するまで時間がかかること。二つ、エレベーターが動くとこのビル自体が振動すること」
確かにこのビルは古い。前の道路を大型トラックが通過しただけでも建物が揺れる。あまりに頻繁にゆらゆらぐらぐらするので、もう私などは気にもしなくなってしまっている。
「ついさきほどから生じている揺れはエレベーターによるものだ。鈍感で観察力の低い君には判別がつかないだろうが、ボクはビルの揺れ具合から、道路を通過した揺れなのか、風によるものなのか、あるいはエレベーターの作動に伴うものか、地震なのか、揺れの原因を特定できる。つけ加えるならば、車の通過による揺れならば車種も、エレベーターによるものならば、何階から何階へ向かっているのか、今、どのあたりを箱が通過しているのかまで八割がた当てることができる。ちなみに今は六階から一階へ向かう途中で三階にさしかかったあたりだね」
疑うことを知らない素直な、いささか素直すぎるくらいお人よしな読者のために私は書いておかなければならない。エレベーターの位置を推理するなんて、いくらなんでもそんな芸当は無理だ。もちろん、ときたま加寿内の推理が当たることはある。だが、これは確率の問題だ。下手な鉄砲も、強引で無茶苦茶な推理も、数撃ちゃ当たるのだ。だから、さきほどの加寿内の発言は話半分で聞いてもらいたい。わが友、加寿内が幾つかの不思議な謎を解明したことも、警察に先んじて難解な事件を解決したことも事実だ。しかし、そんな成功事例の二倍、三倍、いや、何十倍もの手ひどい間違いをしていることもまた忘れてはならない事実なのだ。
「今、エレベーターを呼び出した一階の誰かさんは、待つことにしびれを切らして階段を上り始めた。ほら足音が聞こえるだろう。しかも、その足音は三段目のところだけ大きくなった。これは三段目が少し低くなっていることを知らない人間が、予想していたところに段がなかったために踏み外すような感じで思い切り体重をかけてしまったことで起きた現象だ。このビルの階段を日常的に使う人間ならば、二階へ向かう階段の三段目が低いことは知っている。段を踏み外しかけるなどという恥ずかしい真似はしない。つまり、今、階段を上ってきている人物はこのビルを訪れるのは始めての人間だ。しかも、到着の遅いエレベーターを待つのをあきらめて階段を使うことを選択している。これはこの人物の目的の階がそれほど上でないことを示している。上の階だったら、待ってでもエレベーターを使うだろうからね。多くの人間は三階以上ならエレベーターを使うだろう。だから、この人物の目的の階は二階だ。二階にはボクの事務所しかない。探偵事務所に来る人間には集金の人やらなんやら
いろいろいるが、初めて来るのは、まぁ依頼人とみて間違いはないだろう」
「なるほどね」
「しかも、プライドの高いある程度、高齢の人だな。小さいお孫さん、それもかなり運動神経のすぐれた身のこなしの軽いちびっこを連れてきている」
「どうしてそんなことまで!」
「これだけボクたちが話をしているにもかかわらず、依頼人はまだ二階の事務所にたどり着いていない。これは足腰が弱いからだろう。並みの体力を持った人なら、とっくに階段を上りきっているだろうからね」
「二階に来たはいいが迷っているのでは?」
「迷う? どうやって? 絶望的な方向音痴の君にだってそんなことはできないね。さっきもいっただろ。この階にはこの事務所しかない。あとのテナントは空いている」
私は人気のない寒々としたやたらと自分の足音が響く廊下を思い浮かべて納得した。
「でも、加寿内、足腰が弱いのはなにも高齢者とは限らないじゃないか。たとえば、そうだな、足を怪我しているとか」
「いや、それはないね。足音をよく聞けばわかる。あの足音は左右の足で大きく違わない。片足だけを怪我しているのではなく、両方の足がバランスよく弱っている。だから、年齢によるものだ」
「プライドが高い、というのはさすがにあてずっぽうだろう?」
「おやおや、まったく困ったものだね。実に明確な根拠があるじゃないか。足が弱っているにもかかわらず、エレベーターを待たなかったんだよ。かなりプライドにこだわるたちとみたね。これも高齢者であることの傍証さ」
この発言は人生の先輩方にとっていささか礼を失しているのではないか、と思ったが口には出さずにおいた。どうせ名探偵は聞く耳を持ってはいないだろう。
「お孫さんを連れているというのは?」
「足音だ。もう一つ別の足音がしているのに気がつかなかったのかい?」
気がつかない。気がつくわけがない。もう一つも何も足音など聞き取れない。
「まぁ、無理もない。ごく小さな足音だからね。そう、小さな足音。だから、その人物の体重も軽い。察するに子どもか猿のたぐいだ。もう一人の人物の年齢が高いことから考えて、彼あるいは彼女のお孫さんというのが妥当だろう。まさかペットの猿を連れてきたわけではあるまい」
「運動神経がいい、というのはなぜわかる?」
「おちびの足音の回数はもう一つの足音の半分だ。これがどういうことだかわかるかい?」
質問に対して質問で返された。いくら考えても私にはわからないとは思ったが、一応、貧弱な脳みそを働かせてみる。しかし、その作業をすぐに断念した。
「降参だ、加寿内。どういうことなんだい?」
「簡単なことじゃないか。一段抜かしだよ。君も子どものころやらなかったかい?」
「そんな小さな子どもに一段抜かしができるかな。猿のように小さな体なんだろう?」
「おいおい、じゃあ君は猿がついてきたっていうのかい? まぁ、そんな疑問もすぐに解決するさ。なぜなら、すぐそこに依頼人がいるんだからね、ノックは無用です、カギはあいてますから、どうぞ!」
ギイと嫌な音をたててゆっくりと事務所のドアが開き、、驚きの表情をした老婆が姿を見せた。
「どうしてあたしが来たことがわかったんですか?」
毒々しいほどに紫に染めたもじゃもじゃの髪を揺らして依頼人は尋ねた。
「探偵の能力を使えばこれくらい簡単なことですよ。そんなことよりこちらのソファにどうぞ、お孫さんも一緒に」
椅子に深く腰掛けて、依頼人とは正反対のほうを向いたまま告げた加寿内の言葉に、老婆の顔がこわばった。
「孫! どうして?」
「簡単なことですよ、探偵の訓練を積んだものにとっては……」
そのとき私はあることに気がついて加寿内の言葉をさえぎった。それは多少、探偵としての加寿内のプライドを傷つけることになったかもしれないが、私はそうせずにはいられなかったのだ。
「猿だよ、加寿内」
「なんだって? 聞こえなかったが」
「猿だ」
「さる?」
「猿」
「サル?」
「猿」
「猿!」
名探偵らしからぬ素っ頓狂な声がして、なにかが倒れる音が続いた。私は喧騒を背中で聞いた。振り返ることができなかったのだ。
依頼人の後ろにいたのは子ども、ではなく、猿。高齢の依頼人の顔はしわくちゃで、猿のような雰囲気はあるが、人間であることは間違いない。
猿と依頼人とを交互に見やる。そうしているうちに猿のほうもどこか困ったような顔をしていることに気がついた。気のせいだろうか。
「あんたが有名な探偵の先生かね」
見た目の割にはしっかりとした口調で依頼人の女性が私に尋ねた。
「いえ、私は手伝いをしている者で、加寿内はあちらです」
ようやくここで私は振り返り、加寿内を指し示した。思ったとおり、椅子は倒れていたが、加寿内はいつもの表情だった。わずかの時間に冷静さを取り戻したのだろう。切りかえの早いところがわが探偵の売りの一つだ。
「さぁさぁ、どうぞなかへ。いったい、どんな調査をご依頼ですか? 尾行? 暗号解読? なんでもお任せください」
調子よく語りかけながら、加寿内は依頼人をソファに座らせた。開けっ放しの扉のわきで私と猿は仲良く並んで立ちつくしている。
「なにをしているんだ、ぼぉっと突っ立ってないでドアを閉めろよ」
「あ、いや、加寿内、でも、この猿は……」
「失礼ですが奥様、あちらのホ乳類とのご関係は?」
ふん、と依頼人が鼻を鳴らした。
「そいつはね、あたしの命を狙ってたんだよ。でも、もう安心だ。逃げられりゃしない。もっとも、もう観念して逃げるのはあきらめたらしいがね」
「お猿さんとはずいぶんと変わった暗殺者ですね。もっとも、ミス……失礼、まだ、お名前をうかがっていませんでしたね」
「あたしかい? あたしゃ、法螺貝ふき江ってんだよ。いっとくけど、嘘でも下手な冗談でもないからね。町の連中は寄ってたかってあたしのことを嘘つきババアだなんだってひどいこというけどね。そんなことは信じないでくださいよ」
思い出した。このご婦人はあのふき江婆さんだ。
「あなたが嘘つき? まったくひどいことをいう奴らもいるんですね」
そういいながら、加寿内がちらりと私に目配せをした。その意味はわかる。鵜呑みにするな、ということだろう。
この依頼人はとんでもないほら話をして、町を騒がせている有名人なのだ。町で評判の留学生ベナンチョ・ム・ポームト君は実は某国のスパイで、駅前の煎餅屋で働きながら、煎餅を使って暗号をやり取りしている、という話もふき江婆さんの仕業だった。最近では、この町に住む青年実業家、金成満が実は巷を騒がす怪盗ラット・キッドその人である、なんて話も吹聴していた。
ベナンチョ君やラット・キッドのように明らかに嘘だとわかる荒唐無稽な話ならば、まだいい。困るのは真偽のほどがはっきりしないような話、嘘かもしれないけれど万が一に本当だった場合、一大事となるケースだ。先日、過激な政治団体の連中により町長の秘書が監禁されている、と大声でふき江婆さんが触れ回るという事件があった。政治団体うんぬんといういかにもふき江婆さん好みの派手な部分は聞き流されたが、監禁の部分は無視できなかった。
それというのもちょうどそのとき、件の秘書が失踪していたからだ。警察と町長一派はふき江婆さんとともに監禁場所だという山小屋へ向かった。結局、この大騒ぎは空騒ぎに終わる。まさにこれから山小屋に踏み込もうというその矢先に、当の秘書から町長の携帯電話へ「夏休み、楽しかったです。今からお土産を持ってまいります」という能天気な連絡が入ったからだ。
後から聞くところによると、秘書の申請した休暇願はしっかりと町長のハンコを押されて、書類の山に埋まっていたそうだ。なお、この情報源はふき江婆さんではない。
「それで法螺貝さん、どんなご依頼で? その暗殺者を仕向けた連中の正体を探れ、ということですか?」
きめの整ったきれいな顔で加寿内は法螺貝に尋ねる。
「それは大体、見当がついているんだ」
また始まったぞ、という顔をした私に気がついたのか、ちらと制すような視線を送ってよこしたあとで加寿内は厄介な依頼人に尋ねた。
「ほう、それはそれは。いったい、どこのどいつです?」
「地底人さ」
「地底人!」
あきれて言葉を失う私とは対照的に、加寿内は心の底から驚嘆したように大きな声を出した。そんな加寿内の姿に満足したのか、得意そうに法螺貝は続ける。
「あんた、地球のなかってどうなっていると思う?」
質問を投げかけたが、問いかけるという意思は微塵もないようだった。こちらの答えを待たず、答える間も考える間も与えず、ふき江婆さんは続けた。
「地球のなかはマグマがどろどろしている、とかみんな信じているけどね、ありゃ、嘘さ。うーそ。ほんとはね、地底人が住んでいるんだよ。地底人がね、地下帝国を築いているんだよ。地球人の文明を利用して、人間以上に高度な文明を創りあげているのさ」
「ほう、地下帝国。最近の異常気象も彼らの仕業なんですかね?」
「そうさ、そうに違いない。さすがあんた探偵だね。そうなんだよ、あいつらのせいなのさ。いよいよあいつら地底人が地球人から地球を乗っ取ろうと動き始めたんだよ、怖いねぇ」
ちっとも怖くなさそうに依頼人はいう。そのとき、狭いうえに乱雑な事務所にものの倒れる音が響いた。
「俺のことを忘れてもらっちゃ困るぜ、ということですかね」
加寿内が物音の原因をつくった主に向かっていった。犯人は猿だった。猿が机の上に山積みになっていた書類やら灰皿やら、よくわからない小物やらをひっくり返したのだった。あわてて片づけようとした私を手で制し、加寿内が口を開いた。
「ところで法螺貝さん、その猿が地下帝国の仕向けた刺客だというのは、どういうことなんでしょうか」
「ここに来てすぐにいわなかったかい? ずっと追いかけられているんだよ、そいつにさ」
「おっしゃっていましたね、そういえば」
「あれから、ずーっとさ」
「といいますと?」
「あたしねぇ、見ちゃったんだよぉ」
迷惑な依頼人が語り始めたのは、実に奇妙な話だった。
「Q」の章
こほんと一つ、軽いからぜきをして、ふき江婆さんはしゃべりだした。
「あたしが初めて異変に気づいたのは、一ヶ月くらい前のことだったね。あたしはアリスのウサギを見つけたのさ」
「アリスの、というと、あれですか。『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』。作者はルイス・キャロルでしたっけ」
「そうだよ、あの話に出てくるだろう。しょっちゅう懐中時計を取り出しては時間を気にしてバタバタしているウサギが。あのウサギがいたんだよ、本当に」
「どこにいたのですか?」
目を輝かせて質問をする加寿内とは反対に、私はふき江婆さんのほら話にはそれほど興味はなく、テーブルの上のかた焼き煎餅に手を伸ばした。
「聞いて驚かないでくださいよ、探偵さん。アリスのウサギはね、夜毎、金成の屋敷に出てくるのさ」
「金成、あの青年実業家の金成満さんですか」
「そうだよ、あの成金め。やっぱり後ろ暗いことをやってたんだね。あの金は地底人との秘密の取引で稼いだんだよ。あいつの無駄にどでかい屋敷の庭に地下帝国の入り口があるんだ」
「地下帝国の入り口ですか」
「そうさ。そうでなきゃ、どうしてあんなとこにでっかい穴が開いているんだってんだ」
「あな? あぁ、穴ですか、占いの」
金成邸の広大な庭の片隅にある穴のことなら私も知っていた。もちろん、加寿内も。この街の人間なら、ほとんどが知っていることだろう。
多くの経営者と同じように金成は重要な決断をときに占いに頼ることがあった。そのせいでしばしば金成も奇妙な行いをすることがあった。金成邸にある穴も占いの産物といえるだろう。
半年ほど前、金成はある企業の株式の買占めを画策していた。そのタイミングが適切かどうか悩んだ金成はお抱えの占い師ミエルノ未来に相談を持ちかけた。ミエルノは庭に二つの穴を掘り、そのなかで瞑想して金成自身が決断するのが最良であると告げた。若き実業家はさっそく庭の一角に自身で大きな穴を掘り、お告げに従い、四日間、穴の底で瞑想にふけった。その結果、買占めを見送ることにした。驚くべきことにこの判断は正しかったことがのちに明らかになる。買収をもくろんでいた企業の粉飾決算の事実とセクハラ騒動がほどなく報道され、この会社は倒産。このエピソードは金成のカリスマ性をいっそう強く世間にアピールすることとなった。
「占い? そういわれちゃいるがほんとのとこは違うのさ。あれは地底人の仕組んだ陰謀さ。あたしは見つけちまったんだよ。あれは一ヶ月くらい前のことさ。あたしはたまたまあの屋敷のあたりを歩いてたんだ。なにかぴんとくるものがあってね。そしたらさ、あの屋敷の庭をなにかが走ってたんだ。そりゃ、すごい速さでね。よく見ると、月明かりに映し出されたそいつの頭からは長いなにかが生えてるみたいだった。なんだろうと考えたら、わかったんだ。ありゃ、ウサギだ、ウサギの耳だってね」
法螺貝の婆さんはやせ衰えた歯茎を見せつけるよう笑った。
「それもただのウサギじゃないよ。人間くらいある大きさだ。なんだろうと思ってあたしはこっそり監視することにした。そうしたら、ウサギの奴、急に止まったんだ。あんた、そのあとでなにが起こったと思う?」
「なんでしょう?」
鼻の穴を膨らませ、興味津々といった様子で加寿内が尋ねた。そんな相棒とは反対に私はこんな馬鹿馬鹿しい話にこれ以上つき合っていられない、と冷めていた。もとから散らかっていた部屋をさらにひどい状態にしている猿と、この惨状を片づけなければならないということのほうに興味は大きく傾いていた。
「ウサギの奴、胸のあたりから何かを取り出すようにしたんだ。そう、懐中時計だよ。首にかけた懐中時計を胸元から取り出して時間を見たんだ。そして、なにかロープみたいなものを放り投げると地面にもぐっていったんだ。地面に穴が開いていて、そこが地下帝国の入り口になっているんだね。ロープみたいに見えたのは縄梯子だったんだろうよ」
「面白い! それで?」
「しばらくして出てきたよ。出てくるやいなや、縄梯子をくるくるっとまとめてポケットに突っ込むと、また懐中時計をいじって屋敷のほうへ猛然と駆け出したんだ。千切れるんじゃないかってくらい耳をぶらぶらさせてさ。いや、実際のところ、耳は片方しかなかったんだ。一本は千切れちまったんだよ、きっと」
「片耳のアリスの白ウサギ!」
「白じゃないんだ、黒だよ。月明かりくらいではっきり見えなかったけど、黒だったね」
「その黒ウサギの正体を知りたいというわけですね」
「そうじゃないんだよ、探偵さん。正体はわかっているんだ。あのウサギこそ地底人なんだよ。だってさ、そいつはしばらくするとまた入り口に戻ってきて、時計を見て縄梯子を投げ込むと地下帝国にもぐりこんだ。すぐまた出てくると縄梯子を回収して時計を気にして、また屋敷のほうへ大慌てで駆け出す。これを何回も何回もくり返したんだよ」
「実に興味深い。法螺貝さん、あなたは素晴らしい人だ。よく観察を続けました。その忍耐力といい、好奇心の強さといい、あなたには脱帽ですよ」
加寿内の言葉に気をよくしたのだろう。ふき江婆さんは得意満面といった表情を浮かべている。
「それだけじゃないんだよ。ウサギはその奇妙な行動を次の夜も、その次の夜も同じようにやり続けたんだ。この一週間ずっとさ」
もしこの話が作り話ではないのなら、毎晩、飽きもせずに観察をしていたその根性は確かにすさまじいものだ。
「一週間、監視をやって気づいたことがもう一つあるんだ。あの金成のところの書生は地底人とつながっているスパイだよ。あの若造、毎晩、九時半ごろにあの穴をのぞきこんで懐中電灯でなにか合図を送っているんだ。ちょっと見には戸締りの確認をしながら見回りをしているようにしか見えないけど、あれは地底人へ暗号を送っているんだよ」
「書生と黒ウサギは接触しないのですかね」
「その点もさすがだよ。あいつらは地球人に気づかれないように慎重にやっている。書生がサインを送っている姿をウサギの奴は遠くからこっそり眺めているだけなんだ。地表では決して接触しない」
「なるほど、狡猾ですね」
「そうなんだよ、だから、夕べのことも罠なんじゃないかと思ってさ。それであんたのところに来ることにしたんだよ」
ようやく、訪問の目的が明らかになるようだ。もっとも私はこの婆さんの話をもう信用してはおらず、加寿内がどうやって追い返すのかが気になってばかりいた。一応、相談にのったという形をとるために私は初めて依頼人に質問をした。
「夕べ、なにかあったんですね? それを簡単に話してもらえますか?」
「昨日の夜もあたしは地下帝国への入り口の見える監視ポイントにいったんだ。夕べはいつもと違っていたんだよ。毎晩、八時過ぎには出てくるウサギの奴がなかなか姿を見せないんだ。そのへんから、今日はなんかあるなと勘づいたね。ウサギの奴が出てきたのは九時過ぎだった。いつもと違うのはしばらく地下帝国にいたことだ。九時半ごろ、いつものようにスパイ野郎がやってきて穴をのぞいた。すると、あの若造はなにか驚いたようにしゃがんで穴に向かってよくわからないことを叫んだ。地底人語だね。急に立ち上がると外国の名前を叫ぶんだ。『火とガーナ』とか『二、インド』とか。たぶん、地底人との秘密の暗号だね」
「火とガーナ、二、インド……」
ごにょごにょとくり返す加寿内に気づかずに法螺貝の婆さんは続ける。
「何回か叫んだ後、懐中電灯を放り出して駆け出したんだ。そして、消えちまったんだ」
「消えた!」
「正確にいうならば、もう一つの地下帝国の入り口に飛び込んだんだ。吸い込まれるようにね」
「もう一つの穴にですか」
「あぁ、そうさ。ウサギの奴がいつも使っている穴とは別にあの屋敷にはもう一つ穴がある。ウサギの穴とは五メートルくらい離れているかな。あたしはあれはカモフラージュのためのダミーの穴だと思っていたが、両方とも地下帝国につながっているんだね」
「それでそのあとはどうなりました?」
「スパイ野郎がいなくなるとすぐにウサギが出てきた」
「それはどちらの穴から?」
「いつもの穴さ。出てきて縄橋子をまとめるところまでは一緒だった。夕べはなぜかまるめた縄梯子を穴に投げ込んだんだ。そして、時計も見ずに屋敷のほうへ駆け出してった。しばらくすると走って戻ってきて、そのまま穴へぴょいっと飛び込んだんだ」
「いつもの穴にですね」
確認する加寿内にうなづく依頼人。
「うーん、これはすごいことが起こっているようだよ」
目を血走らせて加寿内が私に告げる。
「だろう? だからさ、なにが起きているか確かめに一緒にいってほしいんだよ」
依頼人の頼みをなんのかんのとうまく断るのかと思っていたが、なんと加寿内はこう答えたのだ。
「わかりました。あなたに頼まれなくてもそうしますよ。これは一大事です。一刻も早く救い出さないと。さぁ、出かけよう。準備は五分でできるね?」
そう問いかけてきた加寿内に私はこう返すのが精一杯だった。
「猿はどうする?」
しばらく困ったように眉をしかめた後で探偵は歌うようにいった。
「大家さんに預かってもらうことにしよう。法螺貝さん、すこしだけお時間をいただきますよ」
「休」の章
米菓街にある煎餅屋で店番をしていたベナンチョ・ム・ポームトは不思議な光景を目撃した。大家が猿を連れて歩いているのだ。
「オーヤサン、コンチーワ、ゴキゲンヨウカ? デデデノデ」
ベナンチョは実は日本語は漢字の読み書きも含め完璧にできる。「憂鬱」も「薔薇」も漢字で書けるし、小栗虫太郎の『黒死館殺人事件』も夢野久作の『ドグラ・マグラ』も読んで理解していた。それに九ヶ国語をも自由に操れるのだが、わけあって片言の日本語しかできないように装っている。
「あぁ、ベナンチョ君。バイト? 大変だねぇ」
「ソレ、ドウシタデスカ?」
「ん? あぁ、このお猿さん? うちの店子の探偵さんからしばらく預かってくれって頼まれてねぇ。それで散歩させてるんだよ」
「ソイツハ、テェーヘンダ、オヤブン」
「どうしたの? 時代劇にでもはまったのかい」
「コドモンコロガ、メニ、ハイカラカ」
右手で印籠を突き出すような仕草をしながら、すばやく左手で煎餅を裏返した。愉快そうに笑う大家は、道の反対で携帯電話をいじるふりをしながら、ひっくり返された煎餅に油断なく目をやる男の存在には気がついていない。
「ソーダ、コレ、モッテッテクンナマシ」
「お、なにかもらえるのかい?」
しめしめと顔をほころばせる大家に、ベナンチョは煎餅の入った箱を手渡した。
「ボクガ、ハチュメイ、シマシタ。スゴイヤロ」
「はちゅめい? あぁ、発明ね。そう、ベナンチョ君、新製品の開発もやってるんだ」
「コレ、チョー、カタイヨ。ボクノ、キック、デモ、ワレナイ」
「本当? だってベナンチョ君、ムエタイのチャンピオンだったんでしょ。それでも割れないの? そんなの食べられないよ。おいしいの?」
「カナリノシャチョーサン。オイシイ、イッテタ」
「かなりの……あぁ、金成社長ね。へぇ、やっぱりあの人も変わった人だねぇ」
「救」の章
タクシーを飛ばすこと、十数分。私たち三人は金成邸の前に降り立った。
「おい、加寿内。ここは屋敷の裏側じゃないか。どうしてこんなところで……」
「玄関から入るのが紳士のやり方だということは承知しているよ。だが、今回は急を要する。柵を乗り越えて庭に入ることを許してもらおう。さぁ、いくぞ。法螺貝さんに手を貸すんだ」
しぶしぶ、私は同意し、なんとかふき江婆さんに柵を越えさせることに成功した。
「法螺貝さん、穴というのはあれですか?」
「そうだよ。でも、あんた、危なくないのかい? 地底人にさらわれたりなんてことは……」
「ご心配なく、そのときは私が全力をもってあなたをお守りします。もっとも……」
「なんだい?」
「地底人も地下帝国も存在しませんがね」
加寿内の言葉に早足で歩いていた依頼人が足を止める。
「なんだいなんだい! あんたまであたしを嘘つき扱いかい。あんただけは信じてくれたと思ったのに……それなら、なんでこんなところまであたしを。ひどいじゃないか」
「信じてますよ。あなたは嘘をついていない。あなたが見たことは本当にあったことです。だが、あなたの解釈は間違いです」
「なにをいうんだい。一緒じゃないか」
「一緒じゃありませんね。まったく違います。あなたはすばらしい観察者だ。既成概念にとらわれることがない。信じがたい光景を目にしてもそれを常識で考えてありそうにないことだからと見なかったことにしようとはしない立派なかたです。いいですか、あなたがいなければ救えない人が生まれてしまうところだったんですよ」
「わけがわからないよ!」
「わかるようにしてさしあげましょう! さぁ、一緒に来るんです。あなたのおかげで救われる人のもとへ」
その言葉は偏屈な依頼人の心を動かしたようだ。法螺貝の婆さんはゆっくりとだが、再び歩き始めた。歩き出すとすぐに二つの穴が見えてきた。
加寿内にうながされる形で、依頼人と私は穴のなかをそっとのぞきこんだ。
「地下帝国はありません。地底人はいません。あるのは深い穴と、その底にいる哀れな人間です」
名探偵の言葉どおり、深い穴の底には一人の女性がぐったりと倒れていた。
「大丈夫ですか」
加寿内の問いかけに女性はゆっくりと首を縦に動かした。
「早く、救急車を」
慌てて携帯電話を取り出して、私は救急車を要請した。しどろもどろになりながらようやく通報を終えたところで加寿内が耳打ちをしてきた。
「もう一つの穴も見てきてごらん」
第二の穴にもさらなる衝撃の光景が待ち受けていた。そこにも一人、人間がいたのだ。
「大丈夫ですか。今、救急車を呼びましたから」
穴の底で男が何度も何度もうなづく。そのとき、後ろではっと息を飲む気配があった。慌てて振り向くと、そこにはふき江婆さんが驚愕の表情で固まっていた。
「どうしたんです? 法螺貝さん」
あまりの形相に思わず尋ねてしまう。
「あ、あいつはあのスパイの若造じゃないか」
「スパイ? あぁ、金成さんの書生さんなんですね」
無言で二度、依頼人はうなづいた。
「ご安心ください、法螺貝さん」
陽気な声をかけながら、加寿内が私たちのほうに歩み寄ってきた。歩きながら加寿内は語り始める。
「その人はスパイではなくただの書生です。そして、あなたが夕べ見た書生さんのあれこれもただの事故。もし、あなたが見ていなかったら、そして、私のところに来なかったならば、かわいそうにこの青年はもうしばらく穴の底で痛みに耐えていたことでしょう」
地底人のスパイが消えたなんてありそうもない話はやはりなかった話で、本当にあったことといえば、ただの事故。つまりはそういうことだったのだ。
「法螺貝さんが聞いたという謎の言葉。ガーナとかインドとかいうのは、こうだったんですよ。『人が穴にいるぞ』ってね」
「なるほどね。でも、なぜ二人とも携帯電話で助けを呼ばなかったんだ」
「そうだね、二人とも携帯電話を持っていないとか、壊れてしまったとか、なにか事情があったのだろうよ。そんなことよりもね、これでボクの推理が正しかったことが判明した。この推理が正しければ、まだ救い出さねばならない人がいる。もう手遅れかもしれないが、ボクはいくよ」
「待てよ、一緒に……」
「いや、君はここにいてくれ。そして、救急隊が到着したら、ケータイに電話をくれ。きっとだよ。そして、もう一つ、怪我人から、特にあの長い髪の女性から決して目を離すんじゃないぞ。わかったね」
真剣な表情に押し切られるように私は黙って何度もうなづいた。加寿内の残した言葉の意味を考えながら、私は法螺貝さんとともに救急車の到着を待った。五分も経たずにサイレンが聞こえてきた。私は依頼人を穴のそばに残し、もう一度、柵を越えると、道路に出て救急車を待った。白い車から飛び出してきた隊員を穴まで案内したところでいいつけどおり私は加寿内に電話をかけた。相棒は救急隊の人とかわれ、とだけ告げ、私の気になっていることなど少しも話してくれない。いい加減もう慣れたことだが、身勝手な人間だ。
電話をかわった隊員はしばらくすると顔色を変えて、部下らしき若い男になにかを指示した。すぐに部下のほうがなにかの機材を持ってくると、二人して屋敷のほうへと駆け出していく。
「いったい、なにがあったんだろうね」
私の胸のなかにある疑問を依頼人が口に出した。この状況を把握しているのはわが名探偵だけだろう。いまだ謎のままのアリスの黒ウサギをはじめ、まだまだ知りたいことが山積みだ。
それらの謎がすべて究明されたのは、金成邸の庭ではなく、病院だった。
後編[[アンハッピー・エンド2]] へ
.
.
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: