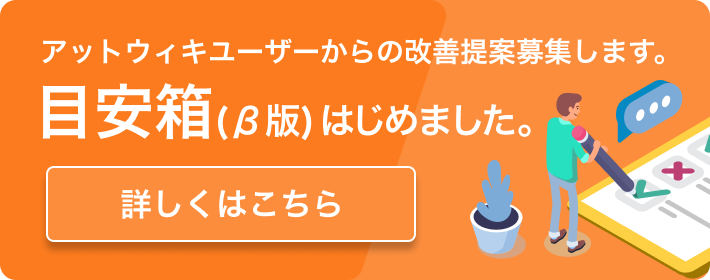『第一章 敵の誘いと闇の真実』
1961年4月12日、旧ソビエトのユーリイ・ガガーリンは人類史上初の
有人宇宙飛行を行った。1時間50分弱の短い旅だったが、
それは宇宙開発の第一歩だった。
その後人類はまさに日進月歩の早さで技術を向上させていった。
1969年7月20日、アポロ計画により人は初めて月の地を踏む。
増えすぎた人口。人々は新天地を求めた。それは宇宙。
そして、人類は完全に宇宙の進出を果たした。大規模コロニーを建築し、
宇宙で自給自足の生活が行えようになったのである。
コロニー建築には小惑星を使用した。宇宙で使うものを地球で造るのではなく
宇宙で使うものを宇宙で作ることに成功したのだ。
それに使用した人型汎用機体。人と同じ動きをし、繊細な作業も出来るそれは、
軍事兵器として開発されていった。現在、人はそれをMS(モビルスーツ)と呼ぶ。
有人宇宙飛行を行った。1時間50分弱の短い旅だったが、
それは宇宙開発の第一歩だった。
その後人類はまさに日進月歩の早さで技術を向上させていった。
1969年7月20日、アポロ計画により人は初めて月の地を踏む。
増えすぎた人口。人々は新天地を求めた。それは宇宙。
そして、人類は完全に宇宙の進出を果たした。大規模コロニーを建築し、
宇宙で自給自足の生活が行えようになったのである。
コロニー建築には小惑星を使用した。宇宙で使うものを地球で造るのではなく
宇宙で使うものを宇宙で作ることに成功したのだ。
それに使用した人型汎用機体。人と同じ動きをし、繊細な作業も出来るそれは、
軍事兵器として開発されていった。現在、人はそれをMS(モビルスーツ)と呼ぶ。
『現代MSの効率的動作のための考察』という研究レポートの導入部分だ。
こんなもの、MSの設計者やメカニックでなければ読まないというのに。彼女の性格を思い知らされる気持ちだ。
青年はレポートを閉じた。黒いショートヘアーに紫色の瞳。身長は175㎝強と19歳の年齢からすると高くも低くもない。
眉は細く、痩せ型。名は裕紀。
裕紀はレポートを机の上に叩きつけるように置く。ふと横を向き口から出てしまった、この部屋の『元』持ち主の名前。
「六歌仙」
が、彼女はもう横にいない。裕紀はあのことがまだ信じられない。自分の甘さは分かっている。
しかし信じたくない。六歌仙が敵になったなんて。
こんなもの、MSの設計者やメカニックでなければ読まないというのに。彼女の性格を思い知らされる気持ちだ。
青年はレポートを閉じた。黒いショートヘアーに紫色の瞳。身長は175㎝強と19歳の年齢からすると高くも低くもない。
眉は細く、痩せ型。名は裕紀。
裕紀はレポートを机の上に叩きつけるように置く。ふと横を向き口から出てしまった、この部屋の『元』持ち主の名前。
「六歌仙」
が、彼女はもう横にいない。裕紀はあのことがまだ信じられない。自分の甘さは分かっている。
しかし信じたくない。六歌仙が敵になったなんて。
今日は特別な日。若手ということもあり、大舞台に立てなかった彼らの記念すべき日だ。
今度結成されたエースパイロット隊への就任が決まったのだ。
初めての大舞台に裕紀は喜びを隠せない。
「こ、こんなの初めてだから緊張するね・・・」と巴が言った。
紫色の髪を指で触り、垂れた黄色の瞳はどこか焦点があっていない。
口下手な彼女だが、今日はいつもにまして口を開かない。
巴は体から声まで完全に緊張しているようだった。
「そう緊張するな。堂々としていればいい」
ポニーテールに束ねた薄オレンジ色の髪をなびかせ六歌仙は答えた。
釣りあがった緑の瞳が巴の瞳を覗き込む。彼女は相変わらずだ。
緊張の欠片も見せず、いたって落ち着いているようだった。
「そうだよ、巴。緊張することないって」
裕紀は優しく巴に声をかける。巴もそれに自信なさそうに頷いた。
裕紀も緊張していないわけではない。しかしいつもと同じ緊張感のない会話が体をほぐしてくれた。
今度結成されたエースパイロット隊への就任が決まったのだ。
初めての大舞台に裕紀は喜びを隠せない。
「こ、こんなの初めてだから緊張するね・・・」と巴が言った。
紫色の髪を指で触り、垂れた黄色の瞳はどこか焦点があっていない。
口下手な彼女だが、今日はいつもにまして口を開かない。
巴は体から声まで完全に緊張しているようだった。
「そう緊張するな。堂々としていればいい」
ポニーテールに束ねた薄オレンジ色の髪をなびかせ六歌仙は答えた。
釣りあがった緑の瞳が巴の瞳を覗き込む。彼女は相変わらずだ。
緊張の欠片も見せず、いたって落ち着いているようだった。
「そうだよ、巴。緊張することないって」
裕紀は優しく巴に声をかける。巴もそれに自信なさそうに頷いた。
裕紀も緊張していないわけではない。しかしいつもと同じ緊張感のない会話が体をほぐしてくれた。
「では、隊員諸君の入場です」
司会の声が会場に響き渡る。同時に沸き起こる盛大な拍手。
合図されたわけでもなく、次々に列を成し中へ入っていく。
会場内はもの凄い人で溢れていた。
壁は紅白の垂れ幕に飾られ、奥の艦には花の帯が掛けられていた。
規則正しく並ぶ椅子には名前を挙げれば老若男女問わず、誰でも名前を知っているような連邦軍の英雄達が座っている。
重役も大勢いるようだ。彼らの存在が隊の重要性を物語っているようだった。
司会の声が会場に響き渡る。同時に沸き起こる盛大な拍手。
合図されたわけでもなく、次々に列を成し中へ入っていく。
会場内はもの凄い人で溢れていた。
壁は紅白の垂れ幕に飾られ、奥の艦には花の帯が掛けられていた。
規則正しく並ぶ椅子には名前を挙げれば老若男女問わず、誰でも名前を知っているような連邦軍の英雄達が座っている。
重役も大勢いるようだ。彼らの存在が隊の重要性を物語っているようだった。
入場した隊員たちが各自席の位置につくのを司会が確認すると軍歌斉唱が始まった。
会場一同が一斉に起立し連邦軍軍歌の「戦友」を歌い上げる。
連邦軍の軍歌の内容は実に陳腐なものだ。
男が友と出会い、連邦軍のため共に敵と戦うが友は戦死してしまうのだ。
そんな死んだ友との思い出を男が亡き友に向けて語るというものである。
だが裕紀はこの曲が好きだった。この曲調はどことなく懐かしさを覚えるのだ。
どこか温かみがあるこのリズム。デジャブというのだろうか。この曲を小学校で習う以前から知っていた気してならない。
会場一同が一斉に起立し連邦軍軍歌の「戦友」を歌い上げる。
連邦軍の軍歌の内容は実に陳腐なものだ。
男が友と出会い、連邦軍のため共に敵と戦うが友は戦死してしまうのだ。
そんな死んだ友との思い出を男が亡き友に向けて語るというものである。
だが裕紀はこの曲が好きだった。この曲調はどことなく懐かしさを覚えるのだ。
どこか温かみがあるこのリズム。デジャブというのだろうか。この曲を小学校で習う以前から知っていた気してならない。
軍歌が歌い終わると司会は隊員以外の者の着席を命じ、次のプログラムへと移る。
「ではテツ大将のお言葉です」
司会がそういうと中央の白い演説台に向かって一人の中年男性が歩き出す。テツ大将である。
連邦軍の最高司令官であり、今回この新隊結成を決定したのも彼だ。
テツ大将は鼻下の白い髭に触れ形を整えると演説台のマイクの位置を軽く調整し、話し始めた。
「去る5月29日。カジノ街として有名な夜のないコロニーとまで謳われたラスベガスコロニーが過激派組織の手により
たった一日でスペースデブリと化しました。死者123,746名。当日視察に向かっていたハグロ大佐までもお亡くなりになられました。
今この場で犠牲者全員の追悼の意を込め名前を読み上げたいところですが、誠に残念ながら時間が限られておりますので
省略させていただきたいと思います。
のちの声明により犯人はレジスタンス『BLACK LOG』であることがわかりました。
これは武力攻撃であり、罪もない一般市民を巻き込んだことは許しがたいことです。憤慨を感じざるを得ません。
彼らはデータに載っていない新組織でありました。我々は次ぐ6月1日にBLACK LOG掃討作戦を発動したのです。
我が連邦軍兵士は全身全霊をかけ戦いましたが、よい結果を残すことは出来ませんでした」
六歌仙は鼻で笑うと正面を向いたまま裕紀と巴に小声で話しかけてきた。
「まったく。マスコミもいないのだから正直に話せばいいものを。BLACK LOG掃討作戦で連邦軍は旧式MS相手に全滅したと。
敵からの通信妨害の影響で戦闘記録が一切残らなかったこともここにいる全員が知っているというのに」
裕紀も巴も前を向いたまま口を開けることはなかった。六歌仙は続けてぼそりと言う。
「この道化師が」
裕紀が六歌仙の顔を横目で窺うと、六歌仙は眉間に皺を寄せているようだった。
テツ大将は話を続ける。
「このまま奴らを野放しにするわけにはいきません。また散って逝った兵士達のためにも彼らを叩く必要があります。
地球連邦政府の平和と秩序を守るため我々軍があるのです。
そしてこの新部隊『アレス』は対BLACK LOGの特別部隊であります。
MSパイロットとして実力の高い精鋭パイロット9名を年齢・性別・階級関係無しにここに召集しました。
アレスはギリシャ神話の軍神です。まさにこの隊の名として相応しいことでありましょう。
彼らの母艦となるこの『アシュタルテ』や新型MSもBLACK LOGを倒すための新たな矛となるでしょう。」
テツ将軍は少々間を空けると声高らかに言い放った。
「ではBLACK LOG壊滅に向け、特別部隊アレスの結成をここに宣言します」
会場はテツ大将のアレス結成宣言とともに最高潮に達し、今までになく大きな拍手に包まれた。
テツ大将は一礼した後、にこやかに手を振りつつ席へと戻った。
「ではテツ大将のお言葉です」
司会がそういうと中央の白い演説台に向かって一人の中年男性が歩き出す。テツ大将である。
連邦軍の最高司令官であり、今回この新隊結成を決定したのも彼だ。
テツ大将は鼻下の白い髭に触れ形を整えると演説台のマイクの位置を軽く調整し、話し始めた。
「去る5月29日。カジノ街として有名な夜のないコロニーとまで謳われたラスベガスコロニーが過激派組織の手により
たった一日でスペースデブリと化しました。死者123,746名。当日視察に向かっていたハグロ大佐までもお亡くなりになられました。
今この場で犠牲者全員の追悼の意を込め名前を読み上げたいところですが、誠に残念ながら時間が限られておりますので
省略させていただきたいと思います。
のちの声明により犯人はレジスタンス『BLACK LOG』であることがわかりました。
これは武力攻撃であり、罪もない一般市民を巻き込んだことは許しがたいことです。憤慨を感じざるを得ません。
彼らはデータに載っていない新組織でありました。我々は次ぐ6月1日にBLACK LOG掃討作戦を発動したのです。
我が連邦軍兵士は全身全霊をかけ戦いましたが、よい結果を残すことは出来ませんでした」
六歌仙は鼻で笑うと正面を向いたまま裕紀と巴に小声で話しかけてきた。
「まったく。マスコミもいないのだから正直に話せばいいものを。BLACK LOG掃討作戦で連邦軍は旧式MS相手に全滅したと。
敵からの通信妨害の影響で戦闘記録が一切残らなかったこともここにいる全員が知っているというのに」
裕紀も巴も前を向いたまま口を開けることはなかった。六歌仙は続けてぼそりと言う。
「この道化師が」
裕紀が六歌仙の顔を横目で窺うと、六歌仙は眉間に皺を寄せているようだった。
テツ大将は話を続ける。
「このまま奴らを野放しにするわけにはいきません。また散って逝った兵士達のためにも彼らを叩く必要があります。
地球連邦政府の平和と秩序を守るため我々軍があるのです。
そしてこの新部隊『アレス』は対BLACK LOGの特別部隊であります。
MSパイロットとして実力の高い精鋭パイロット9名を年齢・性別・階級関係無しにここに召集しました。
アレスはギリシャ神話の軍神です。まさにこの隊の名として相応しいことでありましょう。
彼らの母艦となるこの『アシュタルテ』や新型MSもBLACK LOGを倒すための新たな矛となるでしょう。」
テツ将軍は少々間を空けると声高らかに言い放った。
「ではBLACK LOG壊滅に向け、特別部隊アレスの結成をここに宣言します」
会場はテツ大将のアレス結成宣言とともに最高潮に達し、今までになく大きな拍手に包まれた。
テツ大将は一礼した後、にこやかに手を振りつつ席へと戻った。
その後も式は連邦軍幹部のさまざまな挨拶を経て、アシュタルテの出港となった。
乗組員が全員搭乗し終わると会場に残った全員が艦に向け敬礼を捧げた。
それは艦が彼らの視界から消えるまで終わることはなかった。
艦内では厳正な式に疲れた乗組員達がダラけていた。
既にアシュタルテに搭乗している者は全員顔合わせをしているので親しくないわけではない。
各々がグループを作り親しげに話していた。
裕紀はそんな気にもなれず、ふらりとMS格納庫へと立ち寄った。
自分の愛機となるストライクは連邦の新型MS、G兵器と呼ばれるものの一つだ。
G兵器はフェイズシフト装甲を標準採用し、電力消費と引き換えに実弾兵器を無効化できるため
実弾兵器中心のBLACK LOGに対しては圧倒的防御力を誇る。
また、新型の低電力高出力ジェネレーターの実用化によって小型化されたビーム兵器を搭載しており、
標準装備で既に艦船をも撃沈する攻撃力を有している。
このストライクはストライカーパックと呼ばれる独自の装備換装機構によって多様な戦場に適応可能な汎用性を発揮する。
さらに各々のパックが独立したバッテリーユニットを持ち、同時に装着機の補助電源の役割も兼ねているため、
他のG機体に比べ機体稼働時間の大幅な延長を実現している。
が、非常に複雑なシステムを有する兵器のため現在装備しているエールストライカー以外はまだ開発中である。
本戦で使用するエールストライカーは機動性に優れ、近距離ではビームサーベル、中距離ではビームライフルとバランスも良く、
対MS戦に最も適しているためにいち早く完成されたストライカーパックである。
今まで自分の機体といえば量産機の個人改造型しかなかった彼にとって、
オリジナルが貰えるなんて夢にも思わなかった。人に認めてもらうというのは気分がいい。
コクピット内部を見てみようと階段を上がると、なにやらカタカタ音がする。
どうやら自分以外にも何か用があるのか、ここまで上がって来ている者がいるようだ。
音の方向へ足を運ぶと六歌仙がコクピット内にいた。
「なんだ。裕紀だったのか。てっきり整備班の奴が来たのかと思った」
六歌仙は来訪者の顔を確認するとまた元の作業に戻る。
なにやらコクピットに備え付けられているキーボードを使い何かしているようだ。
「で、何してんだよ」
裕紀は単刀直入に尋ねる。
「何って自分のMSの調整。いつ戦闘になるかわからないし。今までシュミレーションはこなしたけど
この機体が自分に合うかわからない。だからブリッツが自分に合うように調整してるわけ」
六歌仙が与えられたのは同じG兵器の一つであるブリッツだ。巴にもデュエルが与えられている。
「なるほどねー。でも中尉にもなって自分でやるか。整備班にまかせりゃいいじゃんか」
アレス入隊に際し隊員9名は全員階級が上がり、ほぼ全員が尉官に就いていた。
今裕紀達3人は共に中尉に身を置いている。
「整備班に任せたい奴は任せればいい。私は好きでやっているんだ」
「そうか。でも当面は戦闘に入ることはなさそうだし、焦らなくてもいいんじゃないか。
アレスの最終的な目標はBLACK LOGの壊滅だけど、連邦の準備もまだ完全じゃない。
連邦軍が完全な臨戦態勢になるまでの準備期間中は連邦の勢力化ラインを回り続けるだけの簡単な任務だしさ。
敵もそういきなり襲っては来ないだろ。」
「連邦も大変なのさ。貴重な戦力を早々失いたくは無いが、使わずにはいられないという状況なんだろうな。
じゃなかったらG兵器の開発を早めたり、アレスなんて特別部隊を作ったりはしない」
「ごもっとも」
そのまま会話は途切れた。ストライクのコクピットに乗るという当初の目的も忘れ、以後はただなんとなく彼女の作業を見つめていた。
彼女も集中しているようで一言も話しかけては来なかった。
それからどれほどの時間がたっただろうか。長いようで短く、短いようで長い時間が過ぎた。
六歌仙の調整も終盤かという時、ふと裕紀は六歌仙にある質問を投げかけた。
「BLACK LOGってどう思う?」
六歌仙の手がはたと止まる。裕紀は話を続ける。
「その・・・。はっきり言って勝てるかどうか不安なんだ。機体は相手は旧式だけどこっちは新型。
自分の腕もそこそこ自信はある。でも連邦の第5独立部隊を全滅させた連中だ。
いつものように勝てると思いつつも、心のどこかで負けそうな気持ちもあるんだ。
・・・って変な話しちゃったな。ごめん。忘れてくれ」
「そうか。なら忘れよう」
そう言うと六歌仙はまたキーボードを叩き出す。
時計を見ると思わずしてここに長居してしまったようだ。
部屋に戻るため階段へと向け歩く。
すると六歌仙は部屋へと戻ろうとする裕紀の背中に向け、こう告げる。
「私だって不安がないわけじゃない」
乗組員が全員搭乗し終わると会場に残った全員が艦に向け敬礼を捧げた。
それは艦が彼らの視界から消えるまで終わることはなかった。
艦内では厳正な式に疲れた乗組員達がダラけていた。
既にアシュタルテに搭乗している者は全員顔合わせをしているので親しくないわけではない。
各々がグループを作り親しげに話していた。
裕紀はそんな気にもなれず、ふらりとMS格納庫へと立ち寄った。
自分の愛機となるストライクは連邦の新型MS、G兵器と呼ばれるものの一つだ。
G兵器はフェイズシフト装甲を標準採用し、電力消費と引き換えに実弾兵器を無効化できるため
実弾兵器中心のBLACK LOGに対しては圧倒的防御力を誇る。
また、新型の低電力高出力ジェネレーターの実用化によって小型化されたビーム兵器を搭載しており、
標準装備で既に艦船をも撃沈する攻撃力を有している。
このストライクはストライカーパックと呼ばれる独自の装備換装機構によって多様な戦場に適応可能な汎用性を発揮する。
さらに各々のパックが独立したバッテリーユニットを持ち、同時に装着機の補助電源の役割も兼ねているため、
他のG機体に比べ機体稼働時間の大幅な延長を実現している。
が、非常に複雑なシステムを有する兵器のため現在装備しているエールストライカー以外はまだ開発中である。
本戦で使用するエールストライカーは機動性に優れ、近距離ではビームサーベル、中距離ではビームライフルとバランスも良く、
対MS戦に最も適しているためにいち早く完成されたストライカーパックである。
今まで自分の機体といえば量産機の個人改造型しかなかった彼にとって、
オリジナルが貰えるなんて夢にも思わなかった。人に認めてもらうというのは気分がいい。
コクピット内部を見てみようと階段を上がると、なにやらカタカタ音がする。
どうやら自分以外にも何か用があるのか、ここまで上がって来ている者がいるようだ。
音の方向へ足を運ぶと六歌仙がコクピット内にいた。
「なんだ。裕紀だったのか。てっきり整備班の奴が来たのかと思った」
六歌仙は来訪者の顔を確認するとまた元の作業に戻る。
なにやらコクピットに備え付けられているキーボードを使い何かしているようだ。
「で、何してんだよ」
裕紀は単刀直入に尋ねる。
「何って自分のMSの調整。いつ戦闘になるかわからないし。今までシュミレーションはこなしたけど
この機体が自分に合うかわからない。だからブリッツが自分に合うように調整してるわけ」
六歌仙が与えられたのは同じG兵器の一つであるブリッツだ。巴にもデュエルが与えられている。
「なるほどねー。でも中尉にもなって自分でやるか。整備班にまかせりゃいいじゃんか」
アレス入隊に際し隊員9名は全員階級が上がり、ほぼ全員が尉官に就いていた。
今裕紀達3人は共に中尉に身を置いている。
「整備班に任せたい奴は任せればいい。私は好きでやっているんだ」
「そうか。でも当面は戦闘に入ることはなさそうだし、焦らなくてもいいんじゃないか。
アレスの最終的な目標はBLACK LOGの壊滅だけど、連邦の準備もまだ完全じゃない。
連邦軍が完全な臨戦態勢になるまでの準備期間中は連邦の勢力化ラインを回り続けるだけの簡単な任務だしさ。
敵もそういきなり襲っては来ないだろ。」
「連邦も大変なのさ。貴重な戦力を早々失いたくは無いが、使わずにはいられないという状況なんだろうな。
じゃなかったらG兵器の開発を早めたり、アレスなんて特別部隊を作ったりはしない」
「ごもっとも」
そのまま会話は途切れた。ストライクのコクピットに乗るという当初の目的も忘れ、以後はただなんとなく彼女の作業を見つめていた。
彼女も集中しているようで一言も話しかけては来なかった。
それからどれほどの時間がたっただろうか。長いようで短く、短いようで長い時間が過ぎた。
六歌仙の調整も終盤かという時、ふと裕紀は六歌仙にある質問を投げかけた。
「BLACK LOGってどう思う?」
六歌仙の手がはたと止まる。裕紀は話を続ける。
「その・・・。はっきり言って勝てるかどうか不安なんだ。機体は相手は旧式だけどこっちは新型。
自分の腕もそこそこ自信はある。でも連邦の第5独立部隊を全滅させた連中だ。
いつものように勝てると思いつつも、心のどこかで負けそうな気持ちもあるんだ。
・・・って変な話しちゃったな。ごめん。忘れてくれ」
「そうか。なら忘れよう」
そう言うと六歌仙はまたキーボードを叩き出す。
時計を見ると思わずしてここに長居してしまったようだ。
部屋に戻るため階段へと向け歩く。
すると六歌仙は部屋へと戻ろうとする裕紀の背中に向け、こう告げる。
「私だって不安がないわけじゃない」
そして連邦軍本部を離れて半日ほど経った、宇宙時間22:48。
順調だった進展に影が差す。事件は起こった。
激しい衝撃と共に警報が鳴り響く。
近くに熱源はなく、敵襲とは考えられなかった。
ブリッツの紛失、六歌仙の失踪、さらに彼女の部屋にあった置手紙。
証拠はこれだけで十分だった。
追尾を試みるがブリッツにミラージュコロイドを展開され追うことは出来なかった。
ミラージュコロイドは、可視光線を歪曲させレーダー波を吸収する特殊なコロイド状の微粒子を利用した最新のステルス機能である。
コロイドを磁場で物体表面に定着させる事で、その物体に対し電磁的・光学的にほぼ完璧な迷彩を施す事が可能なのだ。
例外として赤外線は通してしまうが宇宙内の慣性飛行を使えば熱を発さないで済む。
僅かに残るスラスター熱も大型カバーで防がれてしまった。
順調だった進展に影が差す。事件は起こった。
激しい衝撃と共に警報が鳴り響く。
近くに熱源はなく、敵襲とは考えられなかった。
ブリッツの紛失、六歌仙の失踪、さらに彼女の部屋にあった置手紙。
証拠はこれだけで十分だった。
追尾を試みるがブリッツにミラージュコロイドを展開され追うことは出来なかった。
ミラージュコロイドは、可視光線を歪曲させレーダー波を吸収する特殊なコロイド状の微粒子を利用した最新のステルス機能である。
コロイドを磁場で物体表面に定着させる事で、その物体に対し電磁的・光学的にほぼ完璧な迷彩を施す事が可能なのだ。
例外として赤外線は通してしまうが宇宙内の慣性飛行を使えば熱を発さないで済む。
僅かに残るスラスター熱も大型カバーで防がれてしまった。
裕紀は眠れなかった。六歌仙、巴、裕紀は士官アカデミーからの友人だった。
同期、成績上位者同士という事もあり、親しくなるのにそう時間はかからなかった。
六歌仙は普段無口でこういうのもなんだが可愛げのない女だった。が、口に出さずともお互い分かり合えていたつもりだった。
それはただの一方的な勘違いだったのか。
そんな自分の不甲斐なさ、そして友といつか命をかけて戦わねばならぬと思うと眠れるわけがなかった。
自分より六歌仙は頭がいい。間違ってると思ったことはしない奴だ。
そんな六歌仙が出した答えだ。何か理由がある。
それにあいつ自身が決めたことなんだ。自分が反論する権利はないだろ。
でも一言、自分に話して欲しかった。行く前に一言でいいから何か言って欲しかった。
せめて・・・さようならを言ってから・・・。
悩んでも悩んでも答えは出ず、後悔は湧き上がってくる。
何で気付けなかったんだろう。何であの時俺は声をかけなかったんだろう。
悔しさのあまり何度も叩いた机は何も語らずそれを受け止めたが、机に乗っていたペンは
いつの間にか床へと落ちていた。
暗い部屋の中を外の星々だけが照らしていた。時計はカチカチと音を立てながら時を刻む。
同期、成績上位者同士という事もあり、親しくなるのにそう時間はかからなかった。
六歌仙は普段無口でこういうのもなんだが可愛げのない女だった。が、口に出さずともお互い分かり合えていたつもりだった。
それはただの一方的な勘違いだったのか。
そんな自分の不甲斐なさ、そして友といつか命をかけて戦わねばならぬと思うと眠れるわけがなかった。
自分より六歌仙は頭がいい。間違ってると思ったことはしない奴だ。
そんな六歌仙が出した答えだ。何か理由がある。
それにあいつ自身が決めたことなんだ。自分が反論する権利はないだろ。
でも一言、自分に話して欲しかった。行く前に一言でいいから何か言って欲しかった。
せめて・・・さようならを言ってから・・・。
悩んでも悩んでも答えは出ず、後悔は湧き上がってくる。
何で気付けなかったんだろう。何であの時俺は声をかけなかったんだろう。
悔しさのあまり何度も叩いた机は何も語らずそれを受け止めたが、机に乗っていたペンは
いつの間にか床へと落ちていた。
暗い部屋の中を外の星々だけが照らしていた。時計はカチカチと音を立てながら時を刻む。
朝になっても宇宙には何の変化もない。
気分転換にシャワーでも浴びようと風呂場へと向かう。
部屋の脱衣所と洗面台は一緒になっていて、服を脱いでいると自分の裸体が嫌でも目に入る。
裕紀は自分の体はあまり好きではない。痩せ型ということは自覚しているが
こう目の前で見てると何とも言えない。
全て脱ぎ終わり、浴室に入る。すぐに湯の蛇口をひねる。
出始めの湯は温まってはおらず、水そのものだったが裕紀は気にも留めなかった。
裕紀はシャワーを浴びている間、動かなかった。体の汗をただ流した。
体を洗う気力も無い。
3分ほどで浴室を出た。気が乗らない。
いつものように軍服に着替える。今日は何故か、軍服が大きく感じた。
気分転換にシャワーでも浴びようと風呂場へと向かう。
部屋の脱衣所と洗面台は一緒になっていて、服を脱いでいると自分の裸体が嫌でも目に入る。
裕紀は自分の体はあまり好きではない。痩せ型ということは自覚しているが
こう目の前で見てると何とも言えない。
全て脱ぎ終わり、浴室に入る。すぐに湯の蛇口をひねる。
出始めの湯は温まってはおらず、水そのものだったが裕紀は気にも留めなかった。
裕紀はシャワーを浴びている間、動かなかった。体の汗をただ流した。
体を洗う気力も無い。
3分ほどで浴室を出た。気が乗らない。
いつものように軍服に着替える。今日は何故か、軍服が大きく感じた。
部屋から出る。この艦は連邦の新型艦と言っても、今までの艦とほとんど変わらない。
壊れてもすぐに修理できるよう、既存のものを多く使っている。
武装は最新式のものを使ってはいるが仕組みは簡易化されており、損傷があったとしてもすぐに代用品に変えられる。
正に戦闘艦として相応しい。
通路を歩いていると1人の女と目が合った。巴がそこにいた。
巴は泣いていたのか、目が赤く染まっていた。
彼女も裕紀に気がついたようで、「あっ・・・」と少しばかり声にならない声を上げるが
すぐに口を閉じ、目をそらす。
2人とも何から話せばいいのかわからない。この状況をまだ夢だと思い込んでいたいから。
だが、その沈黙を裕紀が破る。
「巴・・・・・・」
決意にも似た声は通路にこだまする。巴は裕紀の目をただただ見ていた。
「六歌仙の部屋に行かないか・・・?」
巴は何も言わずに頷く。2人は2度と帰らぬ主の帰りを待つ部屋へと歩き出す。
壊れてもすぐに修理できるよう、既存のものを多く使っている。
武装は最新式のものを使ってはいるが仕組みは簡易化されており、損傷があったとしてもすぐに代用品に変えられる。
正に戦闘艦として相応しい。
通路を歩いていると1人の女と目が合った。巴がそこにいた。
巴は泣いていたのか、目が赤く染まっていた。
彼女も裕紀に気がついたようで、「あっ・・・」と少しばかり声にならない声を上げるが
すぐに口を閉じ、目をそらす。
2人とも何から話せばいいのかわからない。この状況をまだ夢だと思い込んでいたいから。
だが、その沈黙を裕紀が破る。
「巴・・・・・・」
決意にも似た声は通路にこだまする。巴は裕紀の目をただただ見ていた。
「六歌仙の部屋に行かないか・・・?」
巴は何も言わずに頷く。2人は2度と帰らぬ主の帰りを待つ部屋へと歩き出す。
部屋は相変わらず綺麗にまとまっているが、本棚にある書籍はすべてなくなっていた。
六歌仙が連邦の機密書類などを持って行った可能性があるため
捜索隊が六歌仙の部屋を調べたからだ。結局のところ六歌仙が持って行ったのは自分の心とブリッツのみらしい。
それでも十分脅威なのだが。もっとも、彼女のことだから重要書類のほとんどは頭に入っているから関係ないだろう。
裕紀はベッドに腰掛ける。巴はそのすぐそばにあった四足の椅子に座り込んだ。
部屋を見渡すが本類がないというだけで他に変わったところはほとんどない。
彼らからすれば、それはいつ六歌仙が帰ってきてもおかしくないということを意味していた。
その気持ちを裕紀は素直に口に出した。
「なぁ、まだ信じられないんだ。六歌仙が俺らを裏切ったなんて・・・」
巴は何も言わなかった。無言の同意、という奴だろうか。
「こうやって待ってれば急に顔を出して、「私の部屋をたまり場にするなと何度言ったらわかるんだ」なんて言いそうでさ・・・」
裕紀の声は虚しく部屋に響くのみ。ふと机の上を見ると写真ケースが倒されている。そして横にある首飾り。
裕紀はそっと写真ケースを起こす。
それは3人が仕官アカデミーを卒業したときの記念写真だった。
桜並木の中をみな笑顔で写っている。巴は恥ずかしそうに右端で顔を赤くし、裕紀は子供のように桜を楽しんでいる。
六歌仙はそんな2人を見つつ微笑んでいた。
さらにその横の首飾りはよく見れば、卒業式のときに3人そろって買ったものだ。
裕紀は3人一緒でいた、いや、いるのが当たり前だと思っていたあの頃を思い出し黙り込む。
静かな裕紀を不思議に思い、巴は裕紀に近寄りそのわけを知った。
巴からは枯れたはずの涙が零れ落ちた。
彼らは六歌仙の決意を知ったのだった。
六歌仙が連邦の機密書類などを持って行った可能性があるため
捜索隊が六歌仙の部屋を調べたからだ。結局のところ六歌仙が持って行ったのは自分の心とブリッツのみらしい。
それでも十分脅威なのだが。もっとも、彼女のことだから重要書類のほとんどは頭に入っているから関係ないだろう。
裕紀はベッドに腰掛ける。巴はそのすぐそばにあった四足の椅子に座り込んだ。
部屋を見渡すが本類がないというだけで他に変わったところはほとんどない。
彼らからすれば、それはいつ六歌仙が帰ってきてもおかしくないということを意味していた。
その気持ちを裕紀は素直に口に出した。
「なぁ、まだ信じられないんだ。六歌仙が俺らを裏切ったなんて・・・」
巴は何も言わなかった。無言の同意、という奴だろうか。
「こうやって待ってれば急に顔を出して、「私の部屋をたまり場にするなと何度言ったらわかるんだ」なんて言いそうでさ・・・」
裕紀の声は虚しく部屋に響くのみ。ふと机の上を見ると写真ケースが倒されている。そして横にある首飾り。
裕紀はそっと写真ケースを起こす。
それは3人が仕官アカデミーを卒業したときの記念写真だった。
桜並木の中をみな笑顔で写っている。巴は恥ずかしそうに右端で顔を赤くし、裕紀は子供のように桜を楽しんでいる。
六歌仙はそんな2人を見つつ微笑んでいた。
さらにその横の首飾りはよく見れば、卒業式のときに3人そろって買ったものだ。
裕紀は3人一緒でいた、いや、いるのが当たり前だと思っていたあの頃を思い出し黙り込む。
静かな裕紀を不思議に思い、巴は裕紀に近寄りそのわけを知った。
巴からは枯れたはずの涙が零れ落ちた。
彼らは六歌仙の決意を知ったのだった。
厳重にロックされた扉が開き、中が見える。
長い。距離にして5mもないがそれはとても長く感じられた。
明るく光る天井の蛍光灯。そしてその光を吸収する黒ずくめの兵士達。
無限に広がる空間と並列する柱の数々。その中央を走る絨毯。
そして一番奥にあるソファーに男がマントを被り、足を組みつつ腰掛けている。
「止まれ」
兵士の命令で足を止める。自分の周りの4人の兵士がさっきから突撃銃を構えているが
彼らは黒いマントをかぶっており、見えるのは顔の下半分と手足のみという状態だ。
相手の姿が見えないということに少し恐怖を覚えた。
奥の男は口をゆっくりと開いた。
「君がそうか・・・。連邦の脱走兵というのは・・・。済まないね。マントを被ったままで。
しかし信用できる者でない限り、いきなり顔を晒し出すわけにはいかないのでね」
男の声は意外と低い。
「貴公はどなたで?」
あくまで強気の態度を崩すつもりはなかった。
男はその屈しない態度に感心の声を漏らしつつ、答える。
「自己紹介が遅れたな。私はオルトロス。BLACK LOGのリーダーを務めている」
少し驚いた。重役と対面することは予想していたが、まさかリーダーと話せるとは思っていなかった。
想定外の展開だったが、逆に話は早い。
「そうでしたか。お目にかかれて光栄です。私は・・・」
「口にする必要はない。その緑の瞳にポニーテールの若手女性仕官兼パイロットと言ったら、連邦軍には1人しかいないよ」
急な発言に少し戸惑うが顔には出さない。
「そうだろ?六歌仙君」
「・・・御名答」
「君は我々を倒すための特別部隊アレスに所属していたそうじゃないか」
その言葉を聞き六歌仙は驚き焦った。
「何故それを・・・!それは連邦の機密情報のはず・・・」
「戦うためにはまず敵を知ることから始めないといけないだろう?
戦いの基本じゃないか。にしても、冷静沈着と有名な君も取り乱すことはあるんだな。意外だよ」
「馬鹿な!連邦には既にBLACK LOGのスパイがいるというのか!?」
連邦の情報管理体制に不備があったとは思えなかった。しかしBLACK LOGが連邦の情報を掴んでいるのは事実。
どこかにパイプがあるに違いなかった。が、今の自分には関係ないことだと考え直し、いまだ連邦の兵士である自分を叱る。
「まぁ落ち着きたまえ。その点に関してはご想像にお任せしよう・・・。そんなことより聞きたいことがあるのだが、よろしいかな?」
「・・・なんでしょう」
オルトロスはしばらく間を置き、話し始める。
「何故君は我がBLACK LOGに投降したんだ?
あの機体は連邦の新型MSと聞いている。詳細は知らないが・・・。
それを持ってすれば我々の旧式MSなど敵ではないはずだ」
「貴方もご察しでしょう・・・。私は投降しに来たのではありません。入隊志願に来たのです」
「理由は?」
「あなた方の思想に共感したからです。軍人としても、いち戦争孤児としても。
そして私がいるべきところは連邦ではない。そう思ったからです。
元々連邦軍に所属していたのもただ単に生きるためですから。特にこだわりもないので切り捨てました」
そう。そう心から思っている。もっとも敵である彼らにそれを事実として受け止めてもらえるなど思ってはいない。
「それで1人で来たのか」
「ええ。私が現在所属している部隊はあなたの仰ったようにBLACK LOGを倒すための特別部隊ですので
一緒にBLACK LOGに脱走しようなどと言っても相手にされませんから」
すると彼は意外な質問を返してくるのだった。
「本当に切り捨てることが出来たのかね」
彼はいたって普通の口調だったが、真実を体から引き出されるような気迫があった。
「は、はい・・・」
そうだ。連邦軍の自分は捨てた。妙な枷を背負う必要もない・・・。
その答えを聞き、オルトロスは少し悩むとすぐに決断した。
「そうか。分った。君にはさっそく前線部隊を仕切ってもらおう」
「なっ・・・。信用されると仰るのですか?」
「あぁ。もちろんだ。せっかく来てくれたんだからな」
意外な対応に六歌仙は驚いた。もっと警戒されると踏んでいたのに、まるで拍子抜けだ。
「いいのですか?もしかしたら私が裏切る可能性というのも・・・」
「その時はその時で考えるさ」
オルトロスはソファーから立ち上がりこちらに向かって歩いて来るとマントのフードを下ろした。
初めてオルトロスの顔を見る。さっきまでは確認できなかったが、今ははっきりと見える。
身長は185㎝ほどあるだろうか思ったより高い。足も長く、身長の半分近くを占めている。
同じように腕も長かった。髪は白く、肩までかかるロングだった。鼻は高いほうで彫りは深かった。
顎は鋭く、蒼く細い目は人を惹きつける感じがする。歳は30を超えているだろう。目の周りには少ししわが見える。
「それに、本当に裏切る奴ならそんなことは言い出さないよ」
そう言うと彼は六歌仙の肩に両手を乗せた。
「頑張ってくれよ。君には期待している」
「・・・尽力します」
オルトロスは六歌仙の肩から手を下ろした。
「君はさっき真実を知った、と言ったね?」
「はい」
「実は君が知った真実は全てではないんだ」
長い。距離にして5mもないがそれはとても長く感じられた。
明るく光る天井の蛍光灯。そしてその光を吸収する黒ずくめの兵士達。
無限に広がる空間と並列する柱の数々。その中央を走る絨毯。
そして一番奥にあるソファーに男がマントを被り、足を組みつつ腰掛けている。
「止まれ」
兵士の命令で足を止める。自分の周りの4人の兵士がさっきから突撃銃を構えているが
彼らは黒いマントをかぶっており、見えるのは顔の下半分と手足のみという状態だ。
相手の姿が見えないということに少し恐怖を覚えた。
奥の男は口をゆっくりと開いた。
「君がそうか・・・。連邦の脱走兵というのは・・・。済まないね。マントを被ったままで。
しかし信用できる者でない限り、いきなり顔を晒し出すわけにはいかないのでね」
男の声は意外と低い。
「貴公はどなたで?」
あくまで強気の態度を崩すつもりはなかった。
男はその屈しない態度に感心の声を漏らしつつ、答える。
「自己紹介が遅れたな。私はオルトロス。BLACK LOGのリーダーを務めている」
少し驚いた。重役と対面することは予想していたが、まさかリーダーと話せるとは思っていなかった。
想定外の展開だったが、逆に話は早い。
「そうでしたか。お目にかかれて光栄です。私は・・・」
「口にする必要はない。その緑の瞳にポニーテールの若手女性仕官兼パイロットと言ったら、連邦軍には1人しかいないよ」
急な発言に少し戸惑うが顔には出さない。
「そうだろ?六歌仙君」
「・・・御名答」
「君は我々を倒すための特別部隊アレスに所属していたそうじゃないか」
その言葉を聞き六歌仙は驚き焦った。
「何故それを・・・!それは連邦の機密情報のはず・・・」
「戦うためにはまず敵を知ることから始めないといけないだろう?
戦いの基本じゃないか。にしても、冷静沈着と有名な君も取り乱すことはあるんだな。意外だよ」
「馬鹿な!連邦には既にBLACK LOGのスパイがいるというのか!?」
連邦の情報管理体制に不備があったとは思えなかった。しかしBLACK LOGが連邦の情報を掴んでいるのは事実。
どこかにパイプがあるに違いなかった。が、今の自分には関係ないことだと考え直し、いまだ連邦の兵士である自分を叱る。
「まぁ落ち着きたまえ。その点に関してはご想像にお任せしよう・・・。そんなことより聞きたいことがあるのだが、よろしいかな?」
「・・・なんでしょう」
オルトロスはしばらく間を置き、話し始める。
「何故君は我がBLACK LOGに投降したんだ?
あの機体は連邦の新型MSと聞いている。詳細は知らないが・・・。
それを持ってすれば我々の旧式MSなど敵ではないはずだ」
「貴方もご察しでしょう・・・。私は投降しに来たのではありません。入隊志願に来たのです」
「理由は?」
「あなた方の思想に共感したからです。軍人としても、いち戦争孤児としても。
そして私がいるべきところは連邦ではない。そう思ったからです。
元々連邦軍に所属していたのもただ単に生きるためですから。特にこだわりもないので切り捨てました」
そう。そう心から思っている。もっとも敵である彼らにそれを事実として受け止めてもらえるなど思ってはいない。
「それで1人で来たのか」
「ええ。私が現在所属している部隊はあなたの仰ったようにBLACK LOGを倒すための特別部隊ですので
一緒にBLACK LOGに脱走しようなどと言っても相手にされませんから」
すると彼は意外な質問を返してくるのだった。
「本当に切り捨てることが出来たのかね」
彼はいたって普通の口調だったが、真実を体から引き出されるような気迫があった。
「は、はい・・・」
そうだ。連邦軍の自分は捨てた。妙な枷を背負う必要もない・・・。
その答えを聞き、オルトロスは少し悩むとすぐに決断した。
「そうか。分った。君にはさっそく前線部隊を仕切ってもらおう」
「なっ・・・。信用されると仰るのですか?」
「あぁ。もちろんだ。せっかく来てくれたんだからな」
意外な対応に六歌仙は驚いた。もっと警戒されると踏んでいたのに、まるで拍子抜けだ。
「いいのですか?もしかしたら私が裏切る可能性というのも・・・」
「その時はその時で考えるさ」
オルトロスはソファーから立ち上がりこちらに向かって歩いて来るとマントのフードを下ろした。
初めてオルトロスの顔を見る。さっきまでは確認できなかったが、今ははっきりと見える。
身長は185㎝ほどあるだろうか思ったより高い。足も長く、身長の半分近くを占めている。
同じように腕も長かった。髪は白く、肩までかかるロングだった。鼻は高いほうで彫りは深かった。
顎は鋭く、蒼く細い目は人を惹きつける感じがする。歳は30を超えているだろう。目の周りには少ししわが見える。
「それに、本当に裏切る奴ならそんなことは言い出さないよ」
そう言うと彼は六歌仙の肩に両手を乗せた。
「頑張ってくれよ。君には期待している」
「・・・尽力します」
オルトロスは六歌仙の肩から手を下ろした。
「君はさっき真実を知った、と言ったね?」
「はい」
「実は君が知った真実は全てではないんだ」
悲しみにくれている裕紀達を時間は許さない。艦内に警報が鳴り響く。
それはあの事を彼らに思い出させた。さらにブリッジからの指令が聞こえる。
「総員第一種戦闘配備!繰り返す、総員第一種戦闘配備!」
それはあの事を彼らに思い出させた。さらにブリッジからの指令が聞こえる。
「総員第一種戦闘配備!繰り返す、総員第一種戦闘配備!」
ブリッジには緊迫した空気が流れていた。
後方X456-Y478-Z474より熱源を感知。数は20。多い。
味方からの連絡はなく明らかに敵のものだったが、まだ断定は出来ない。特定するには遠すぎる。
X-Y-Z全ての値が300を切らないと断定は出来ないからだ。そのため第一種戦闘配備にしたが、おそらくすぐに
MS隊の出撃、対MS砲撃用意の命令を下すことになるだろう。敵はBLACK LOGであることは間違いない。
しかし奴らには六歌仙が付いている。油断は出来ない。しかも六歌仙の機体、ブリッツは奇襲を目的に作られた機体。
艦を奇襲されたらひとたまりもない。不安のあまり通信兵が声を上げた。
「ルピス司令官・・・」
ルピスは唇をかんだ。
容姿は刈り上げの灰色髪に、鼻は低く少し大きい。太い眉と少量の顎鬚が凛々しさをかもし出している。
歳も50前半というところだろうか。しかし今は顔色も悪く、焦りが目に見える。歳ももっと多く見える。
「六歌仙め・・・」
まだブリッツが奪われて間もなく、また補給・輸送艦も到着していない。最も近い連邦基地までまだある。
簡単な任務だったはずが裏目に出てしまった。
叩けるうちにに叩くということか・・・。
「いいか、熱源が敵機体と確定した時点でMS隊の出撃、対MS砲撃がいつでも出来るようにしておけ。
バルーン射出準備急げ。フレアの用意も今のうちにするんだ」
後方X456-Y478-Z474より熱源を感知。数は20。多い。
味方からの連絡はなく明らかに敵のものだったが、まだ断定は出来ない。特定するには遠すぎる。
X-Y-Z全ての値が300を切らないと断定は出来ないからだ。そのため第一種戦闘配備にしたが、おそらくすぐに
MS隊の出撃、対MS砲撃用意の命令を下すことになるだろう。敵はBLACK LOGであることは間違いない。
しかし奴らには六歌仙が付いている。油断は出来ない。しかも六歌仙の機体、ブリッツは奇襲を目的に作られた機体。
艦を奇襲されたらひとたまりもない。不安のあまり通信兵が声を上げた。
「ルピス司令官・・・」
ルピスは唇をかんだ。
容姿は刈り上げの灰色髪に、鼻は低く少し大きい。太い眉と少量の顎鬚が凛々しさをかもし出している。
歳も50前半というところだろうか。しかし今は顔色も悪く、焦りが目に見える。歳ももっと多く見える。
「六歌仙め・・・」
まだブリッツが奪われて間もなく、また補給・輸送艦も到着していない。最も近い連邦基地までまだある。
簡単な任務だったはずが裏目に出てしまった。
叩けるうちにに叩くということか・・・。
「いいか、熱源が敵機体と確定した時点でMS隊の出撃、対MS砲撃がいつでも出来るようにしておけ。
バルーン射出準備急げ。フレアの用意も今のうちにするんだ」
裕紀は涙を拭いている巴の手をとり、戦闘態勢に入るためMS格納庫へと走った。
敵はBLACK LOGと見て間違いないだろう。
もしかしたら六歌仙に会えるかもしれないという淡い妄想が頭を馳せる。
もしも直接話が出来るなら聞かなければいけないことがある。
それはBLACK LOG入隊の理由だ。
任務を捨ててまで敵に入るというには何か理由がある。いや、合理的理由がなければ彼女は動かない。
今でも目を瞑ると聞こえてくる。見えてくる。
みんなの声が。
あの桜並木が。
裕紀は首飾りを握り締める。3人そろって買った首飾り。
彼女と戦うことのためらい、そして現実を受け止められない自分の甘さをひしひしと感じる。
しかし、時はそれを冷静に判断するだけの時間を与えてはくれない。
敵はBLACK LOGと見て間違いないだろう。
もしかしたら六歌仙に会えるかもしれないという淡い妄想が頭を馳せる。
もしも直接話が出来るなら聞かなければいけないことがある。
それはBLACK LOG入隊の理由だ。
任務を捨ててまで敵に入るというには何か理由がある。いや、合理的理由がなければ彼女は動かない。
今でも目を瞑ると聞こえてくる。見えてくる。
みんなの声が。
あの桜並木が。
裕紀は首飾りを握り締める。3人そろって買った首飾り。
彼女と戦うことのためらい、そして現実を受け止められない自分の甘さをひしひしと感じる。
しかし、時はそれを冷静に判断するだけの時間を与えてはくれない。
MS格納庫に到着すると整備兵が駆け寄ってきた。彼は有無を言わさず話を進める。
「ブリッジよりMSの発進命令が下されました。すぐにパイロットスーツに着替えてください。時間がありません」
ロッカールームへ行くと皆すでに着替え始めていた。
緊張、興奮、不安、恐怖、期待、全てが混ざったような不思議な空間が広がっている。
1人、また1人と部屋から消えて行き、残ったのは裕紀のみとなった。
裕紀は静かにチャックを上げる。首にはあの首飾りが輝いていた。
「ブリッジよりMSの発進命令が下されました。すぐにパイロットスーツに着替えてください。時間がありません」
ロッカールームへ行くと皆すでに着替え始めていた。
緊張、興奮、不安、恐怖、期待、全てが混ざったような不思議な空間が広がっている。
1人、また1人と部屋から消えて行き、残ったのは裕紀のみとなった。
裕紀は静かにチャックを上げる。首にはあの首飾りが輝いていた。
裕紀は整備兵の誘導に従いストライクへと乗り込んだ。
初稼動が初出撃になるとは誰も思っていなかっただろう。
シュミュレーションはこなしたが、実践とはまるで違うことは自分がよく分っている。
機体の電源を入れると周りが一気に明るくなり、カメラより外部が見える。
画面の一部に兵士の顔が映る。ブリッジからの通信だ。
「改めてご挨拶申し上げます。私は通信兵のルピナと申します。階級は准尉となっております。
現状をご説明いたします。敵数20。敵現在地後方X248-Y298-Z283。
貴方には敵MSの撃破を最優先に行動していただきます。
熱源を照合した結果、ジン系列の機体と思われますが
断片的に不一致する箇所が多々あり、なおかつ全ての機体の熱源が一致しないため
20機全てジンの個人改良形と思われます。
なので敵の機体の性能は未知数です。ジンではありますが、ある程度の性能を持っている可能性もあります。
またこちらは9と数では不利です。くれぐれもご注意を。
本戦では現在艦に配備されているエールストライカーパックを使用します。
何かご質問は?」
「六歌仙・・・いや。ブリッツの熱源は?」
「現在確認できておりません。しかしブリッツがミラージュコロイドを展開して奇襲を仕掛けてくるという可能性も捨てきれません。
なので艦護衛は別のパイロットがあたります」
「分った。ありがとう」
「了解しました。裕紀中尉は60秒後に発進となります。御武運を」
ルピナの顔が消える。
発進もあと数十秒と迫った時、巴からの通信が入った。
「六歌仙・・・。き、来てるのかな・・・」
期待と不安の入り混じった声はあきらかに震えていた。
「分らない。熱源は感知出来なかったらしいから・・・」
「うん・・・」
目の前のレッドランプが点灯する。発進の合図だ。
「悪い。行かなくちゃ」
そう言うと裕紀は通信を切る。ここからは自分のみが頼れる世界。
接続ケーブル切り離しのボタンを押す。
機体に付いていた十数ものケーブルが一気に切り離される。それらはゆっくりと垂れ下がっていく。
整備兵が手にする誘導灯に従い移動する。
カタパルトに足を乗せると、そこからは別の世界が広がる。
管制の声がマイクより響き渡る。
「進路クリア。システムオールグリーン。裕紀機ストライク、カタパルト射出準備完了。」
「了解。裕紀、ストライク、行きます!」
発進と共に展開されるフェイズシフト装甲。それは機体に色鮮やかさをもたらすと同時に戦火の火蓋を切る。
初稼動が初出撃になるとは誰も思っていなかっただろう。
シュミュレーションはこなしたが、実践とはまるで違うことは自分がよく分っている。
機体の電源を入れると周りが一気に明るくなり、カメラより外部が見える。
画面の一部に兵士の顔が映る。ブリッジからの通信だ。
「改めてご挨拶申し上げます。私は通信兵のルピナと申します。階級は准尉となっております。
現状をご説明いたします。敵数20。敵現在地後方X248-Y298-Z283。
貴方には敵MSの撃破を最優先に行動していただきます。
熱源を照合した結果、ジン系列の機体と思われますが
断片的に不一致する箇所が多々あり、なおかつ全ての機体の熱源が一致しないため
20機全てジンの個人改良形と思われます。
なので敵の機体の性能は未知数です。ジンではありますが、ある程度の性能を持っている可能性もあります。
またこちらは9と数では不利です。くれぐれもご注意を。
本戦では現在艦に配備されているエールストライカーパックを使用します。
何かご質問は?」
「六歌仙・・・いや。ブリッツの熱源は?」
「現在確認できておりません。しかしブリッツがミラージュコロイドを展開して奇襲を仕掛けてくるという可能性も捨てきれません。
なので艦護衛は別のパイロットがあたります」
「分った。ありがとう」
「了解しました。裕紀中尉は60秒後に発進となります。御武運を」
ルピナの顔が消える。
発進もあと数十秒と迫った時、巴からの通信が入った。
「六歌仙・・・。き、来てるのかな・・・」
期待と不安の入り混じった声はあきらかに震えていた。
「分らない。熱源は感知出来なかったらしいから・・・」
「うん・・・」
目の前のレッドランプが点灯する。発進の合図だ。
「悪い。行かなくちゃ」
そう言うと裕紀は通信を切る。ここからは自分のみが頼れる世界。
接続ケーブル切り離しのボタンを押す。
機体に付いていた十数ものケーブルが一気に切り離される。それらはゆっくりと垂れ下がっていく。
整備兵が手にする誘導灯に従い移動する。
カタパルトに足を乗せると、そこからは別の世界が広がる。
管制の声がマイクより響き渡る。
「進路クリア。システムオールグリーン。裕紀機ストライク、カタパルト射出準備完了。」
「了解。裕紀、ストライク、行きます!」
発進と共に展開されるフェイズシフト装甲。それは機体に色鮮やかさをもたらすと同時に戦火の火蓋を切る。