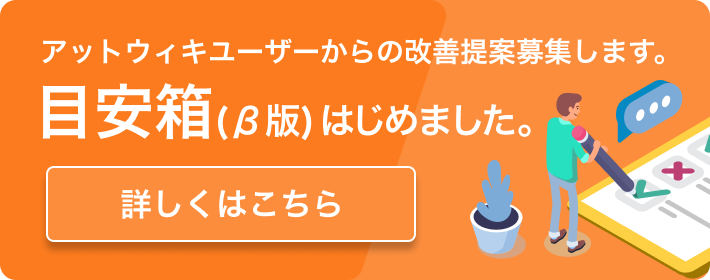84pの小説
遊義皇第十九話(旧)
最終更新:
84gzatu
-
view
とある洋風ホテルの静かすぎる一室にて、押し入る男達が居た。
「ふはははははははァッ! ロールウィッツ・ウェンディエゴぉー!
この正念党七人衆最強の男! 神次郎様が貴様のレアカードを奪いに来てやったぞ!」
この正念党七人衆最強の男! 神次郎様が貴様のレアカードを奪いに来てやったぞ!」
「神第五幹部、少々お静かに。」
「そうですよ、他の客たちが神さんの美声に集まってきたらどうす……って、何をしてるですか、あの人。」
正念党の七人衆の中でも群を抜いて非常識こと神次郎と部下2名が踏み込んだホテルの一室では、
写真で見た通りの容姿の男、ロールウィッツ・ウェンディエゴが泊まっていたが……ロールウィッツは、神次郎の予想すら超えたことをしていた!
写真で見た通りの容姿の男、ロールウィッツ・ウェンディエゴが泊まっていたが……ロールウィッツは、神次郎の予想すら超えたことをしていた!
「ふぅー、ふぅー、一刻待てぇぇい! レアハンターどもッ!」
ロールウィッツは仰向けとなり、頭と両足だけで全体重を支える……――プロレス技で言うところの『ブリッジ』の姿勢だった。
ブリッジだけならば、体を鍛えているとか、プロレスマニアだとかなんとか、いくらでも適当な理由が付けられるのだが、
――ブリッジしている自分の腹の上に、オモチャの積み木で塔を作っていたりしているものだから、その理由を察することは不可能である。
ブリッジだけならば、体を鍛えているとか、プロレスマニアだとかなんとか、いくらでも適当な理由が付けられるのだが、
――ブリッジしている自分の腹の上に、オモチャの積み木で塔を作っていたりしているものだから、その理由を察することは不可能である。
「ロールウィッツ! 何をしているのかこの神次郎に説明させてやろう!」
質問までも高圧的な神次郎に、なぜか高圧的に解答するロールウィッツ。
「ブリッジ・ジェ○ガに決まっているだろが!」
「ブリッジ・○ェンガ!?」
○ェンガとはタカラ○ミーから発売されているパーティ・ゲームの一種で、
直方体のブロックで出来た塔からターンプレイヤーがブロックを一本ずつ抜きとり、その塔の上に積み直す、という複数人でプレイする世界的ゲームだ。
確かによく見れば、ロールウィッツの腹上の積み木はジェン○だ。
直方体のブロックで出来た塔からターンプレイヤーがブロックを一本ずつ抜きとり、その塔の上に積み直す、という複数人でプレイする世界的ゲームだ。
確かによく見れば、ロールウィッツの腹上の積み木はジェン○だ。
「ただのジ○ンガじゃオレにゃぁ簡単すぎンだよ! だぁかぁらぁ!
難易度をあげるため、ブリッジした状態で腹に積み重ねてンだ! ンなこともわかんねーのかよ!?」
難易度をあげるため、ブリッジした状態で腹に積み重ねてンだ! ンなこともわかんねーのかよ!?」
普通は分からないと思う。
「この神次郎を待たせてひとり遊びとは……貴様ァっ! 何様のつもりだ!」
「ウェンディエゴ様に決まってンだろ! バッカじゃねぇの!?」
その『バカ』というのは、自身の姿をちゃんと理解した上で言っているんだろうか?
「この神次郎相手に、バカと判断するとは……さては貴様、新星誕生級のアホウだなっ!?」
「あ、アホウ!? このウェンディエゴ様がっ!?
……へ、まあいい。 ウェンディエゴ様は寛大だからよぉ、
レアハンター、てめーらとも遊んでやるぜ。
……本来なら、この腹ジェ○ガで決着をつけたいとこなんだけどよぉ……、
……こんな高等なゲームはてめぇらにはできねぇだろーしよぉー、デュエルにしてやってもいいぜ?」
……へ、まあいい。 ウェンディエゴ様は寛大だからよぉ、
レアハンター、てめーらとも遊んでやるぜ。
……本来なら、この腹ジェ○ガで決着をつけたいとこなんだけどよぉ……、
……こんな高等なゲームはてめぇらにはできねぇだろーしよぉー、デュエルにしてやってもいいぜ?」
ブリッジの姿勢なので、もちろんロールウィッツの頭部は上下逆転している。
つまり、実際は見上げているにもかかわらず、その視線は神次郎たちを見下ろし(みおろし)、同時に見下し(みくだし)ている。
つまり、実際は見上げているにもかかわらず、その視線は神次郎たちを見下ろし(みおろし)、同時に見下し(みくだし)ている。
「この神次郎が……貴様ごときに合わせられるだとぉ……!?
根拠も何もない、そのアホウ丸出しの自信はなんだ!? 貴様のような男が、最も私の神経を逆撫でするッ!!」
根拠も何もない、そのアホウ丸出しの自信はなんだ!? 貴様のような男が、最も私の神経を逆撫でするッ!!」
そう神次郎が叫ぶと、ロールウィッツはその姿勢を崩さず、嘆息をひとつ。
「ま……てめーらにゃぁー無理っつーもんだよなァ~~~?」
体位も視線も、完全に見下しまくっているロールウィッツによって、神次郎自慢のホウキ頭が怒りに震えた。
「その積木は――もうワンセットあるんだろうな?」
「このウェンディエゴ様がスペアを用意しないわけだがないだろーが。
だがな? この腹上ブリッジは、このウェンディエゴ様だからこそできる超大技……バッカなホウキアタマには無理だぜ。」
だがな? この腹上ブリッジは、このウェンディエゴ様だからこそできる超大技……バッカなホウキアタマには無理だぜ。」
「この救いようのないアホウがぁあああ! この私にできないことがあってたまるかぁっ!」
「な、なんだてめえ! 根拠もねぇ、バカ全開の自信はなんだぁ!? てめぇみたいなのが最も神経を逆撫でするゥッ!!」
……どこかで聞いたことのあるセリフだな、オイ。
「なるほど! 神さん! 第七幹部のエビエスさんがどうして神さんをこの人に当てたかの理由がわかりました!」
新しく神次郎の副官となった牡鹿啓介が、ハツラツとした笑顔で叫ぶように言った。
「ほう!? 牡鹿啓介! 貴様の考察を聞いてやろう!」
「お二人とも! 思考が同じです!」
この後、ロールウィッツと神次郎は、同時に異議を申し立ててから、
牡鹿の意見を否定する暇も惜しみ、アンティを成立させた勝負を開始した―――もちろん、ゲームは腹上ジェ○ガだ。
牡鹿の意見を否定する暇も惜しみ、アンティを成立させた勝負を開始した―――もちろん、ゲームは腹上ジェ○ガだ。
この色は英語だと思ってください。
所変わって、ここは大阪府内のキャンプ場。
その入り口では、一人の少女が気持悪そうに膝をついて呻き、傍らに立って見守る身長240センチの大男がいた。
言うまでもないが、正念党の七人衆の一人、ウォンビック・ブラックマインと、その部下:トガである。
所変わって、ここは大阪府内のキャンプ場。
その入り口では、一人の少女が気持悪そうに膝をついて呻き、傍らに立って見守る身長240センチの大男がいた。
言うまでもないが、正念党の七人衆の一人、ウォンビック・ブラックマインと、その部下:トガである。
「えぉぁ゛、がぁー、うううう。」
「トガ、相槌も要らんが、それと次からは酔った時は酔ったといえ。」
「はい、ブラックマインさ……うぅっあ゛ァー!」
「………相槌は要らんと言ったはずだ。 気分が悪い時は喋らず、吐きたいだけ吐け。」
先ほど買ったタコ焼き(完食済み)の袋に顔を突っ込みつつ、トガは心底自分が情けなくなっていた。
通訳としてウォンビックに信頼され、ここまで抱きかかえられきたというのに……そのブラックマインのスピードで酔うとは……。
通訳としてウォンビックに信頼され、ここまで抱きかかえられきたというのに……そのブラックマインのスピードで酔うとは……。
――そう、抱きかかえられて。
ウォンビックは車や電車などの乗り物は使わず、3次元的に建造物の上部や側面を時速60キロほどで走り抜け、ここまで来たのだ。
ウォンビックは車や電車などの乗り物は使わず、3次元的に建造物の上部や側面を時速60キロほどで走り抜け、ここまで来たのだ。
「ブラックマイン様、私のことはいいですから、早く鵜殿 八兵衛(うどの
はちべえ)とか言うデュエリストを探しに……。」
「探す必要は無い、お前は自分のことだけ考えてろ。」
もちろん、トガへの配慮の言葉なのだろうが、『捜す必要がない』という言葉はよくわからない。
ウォンビックは部下を気遣う時でもウソをつく人間ではないからだ。
ウォンビックは部下を気遣う時でもウソをつく人間ではないからだ。
「どうやら――鵜殿とやら、かなりの有名人らしいな。」
ウォンビックの言葉を受け、彼の視線の先へと目線を送るトガ。
そこには、キャンプ場とは思えない光景――それは長く、このキャンプ場の宿泊人数なんぞ余裕で超える人数で形成された順番待ちの行列だった。
その行き着く先へと視線を移せば、そこには着物を着て髪を結った一人の女性がいた。
そこには、キャンプ場とは思えない光景――それは長く、このキャンプ場の宿泊人数なんぞ余裕で超える人数で形成された順番待ちの行列だった。
その行き着く先へと視線を移せば、そこには着物を着て髪を結った一人の女性がいた。
「あれが鵜殿 八兵衛……? え、女ですよ!?」
ターゲットの写真はエビエスから交付されていいたが、ウォンビックしか見ていなかったらしい。
「今行けば俺たちの顔を売ることになる。 正念党としてもそれは困るらしいからな。
例えるなら、ミネストローネを温めているレンジがチン♪と鳴るのを待つように、行列がなくなるのを待つとしよう。」
例えるなら、ミネストローネを温めているレンジがチン♪と鳴るのを待つように、行列がなくなるのを待つとしよう。」
何日か前、二封気を捕まえるためだけに、二封気が乗っている電車ごと襲撃して帰った時、彼らはエビエスやホーティックにかなり怒られたらしい。
……それはそうとして、これがまだ『レンジが鳴るのを待つ』なら例えとしては分かるのだが、なぜあえて『ミネストローネ』と限定するのかが分からない。
……それはそうとして、これがまだ『レンジが鳴るのを待つ』なら例えとしては分かるのだが、なぜあえて『ミネストローネ』と限定するのかが分からない。
「そうですね、それまでにはなんとか治します……ブラックマイン様、鵜殿のヤツ、こっちを見てませんか?」
ウォンビックも見てみれば、確かに鵜殿はウォンビックたちを……いや、ウォンビック個人をジッと見詰めている。
「80メートルぐらいは離れていますし、私たち二人とも英語で、しかも大きな声も出してませんし……顔が割れたでしょうか?」
そしてスクっと鵜殿は立ち上がり、周囲の行列をざわめかせながら、一直線にウォンビックの方へと向かってきた。
「どうしますか、ブラックマイン様、一旦退却しま……うげええええええ。」
そこに来て、本格的にトガは吐いた。
「………お前がそんな状態では逃げられんだろう。
それに、相手から勝負を挑んできたとすれば、エビエスたちも文句はないだろうしな。」
それに、相手から勝負を挑んできたとすれば、エビエスたちも文句はないだろうしな。」
そんなことを言ってる間も、鵜殿はキャンプ場の鬱葱(うっそう)とした道なき道を、最短距離で着物でズカズカと進み、そして、ウォンビックの目の前でビシ、っと立ち止まった。
「…………。」
「あんさんのお耳……。」
爪先立ちをし、そのままグッっとウォンビックの両耳を摘んだ。
「……なんだ?」
「いい形……しかも、こんなに大きい耳も始めて見たわァ~~~。
こんに耳カスさんが溜まりそうで……あら、ほんに中はビッシリ耳カスさんがついてますやん。」
こんに耳カスさんが溜まりそうで……あら、ほんに中はビッシリ耳カスさんがついてますやん。」
ニギニギとウォンビックの耳を揉みながら、日本語で褒めまくる鵜殿(?)。
吐き終わって復活したトガは、強引に二人の間に割って入るが……身長の都合上、ウォンビックの耳を掴んでる鵜殿の手を撥ね退けられない。
吐き終わって復活したトガは、強引に二人の間に割って入るが……身長の都合上、ウォンビックの耳を掴んでる鵜殿の手を撥ね退けられない。
「な、なにしてんのよッ! この××××っ!」
「トガ、こいつは何をしてるのか訊いてくれ。 日本語は要領がつかめない。」
「あんさん、日本語分かります? 耳掃除をやらせてもろぉてよろしおすか?」
トガは日本語も英語も分かるので、二人の発言は分かるが………鵜殿が何をしたいのかがよくわからなかったが……、
さっきまで行列を形成していた人々(ざっと80人ほど)がここまで来てくれたお陰で、なんとか話が分かった。
さっきまで行列を形成していた人々(ざっと80人ほど)がここまで来てくれたお陰で、なんとか話が分かった。
「姫! 次は私を耳を浄化してくれるのではなかったのですか!?」
「お戻りください、姫様ァっ!」
「早く、早く私の耳を浄化してくださいませええええええ!」
どうやらコイツらは、鵜殿に耳掃除してもらうためだけに、山奥のキャンプ場まで来て、行列を作っていたらしい。
変態だ。 軽く変態だ。
変態だ。 軽く変態だ。
「信者はん、ちっと待っておくれやす。
このお人の耳に、惚れてもうたみたいなんですわ。」
このお人の耳に、惚れてもうたみたいなんですわ。」
信者の殺意を込めた視線が一瞬にしてウォンビックに集まるが、彼自身はなぜ自分が殺気を当てられなければならないのかもわかっていない。
「ぐう、確かにそやつの耳、我ら『聖耳法堂連合』の内にすらいない、見事な耳……ッ!」
「ですが、そのようなどこん馬の骨とも知れぬ者を、誇り高き『聖耳法堂連合』に加えるなんぞッ!」
なんだ。
その、せいじほーどーれんごーってのは。
その、せいじほーどーれんごーってのは。
「この××××どもォッ! ブラックマイン様の耳はあんたらなんかに掃除させない! 散れッ! 集まるなッ!」
人はイライラするとその理由を取り除こうとするが、自分自身がイヤになる自己嫌悪を煩った場合はどうするか?
答えは簡単、そのストレスを別のイライラに転化し、無関係の物にぶつける。
――トガの場合、鵜殿とその取り巻きたちへの不快感に自己嫌悪を含め、暴言として投げつけた。
答えは簡単、そのストレスを別のイライラに転化し、無関係の物にぶつける。
――トガの場合、鵜殿とその取り巻きたちへの不快感に自己嫌悪を含め、暴言として投げつけた。
「ああ、なんと汚らしい言葉……、我らはともかく、姫の聖耳までも汚すとは……。」
「よろしおすえ……あんさん、お連れはんはブラックマインはん言いますの?
ブラックマインはんの知り合いなら、ちょっと取り次いでくれまへんか?」
ブラックマインはんの知り合いなら、ちょっと取り次いでくれまへんか?」
「お断りよっ! ブラックマイン様の耳掃除なんてっ! 私だってやらせてもらってないんだから!」
……え、何、お前もやりたいの?
「……ん? 姫様、ブラックマインって言ったら……ヴァイソンダーヅの不動巨人、と違いますか?」
「褐色の肌に熊より大きな体躯、左手には通常では考えられないほど大きな改造ディスク、
そして暴言を吐く子鼠を連れている……姫様、こやつ、ウォンビック・ブラックマインに間違いないようです。」
そして暴言を吐く子鼠を連れている……姫様、こやつ、ウォンビック・ブラックマインに間違いないようです。」
有名人なんだなぁ、ウォンビック。
「って、あ……しまったっ!? ブラックマイン様! 素性がばれました!」
「……好都合だ。 トガ。 これで隠密行動から正々堂々のデュエルできるからな。」
「不動巨人、ね。 話は常々……こんなにええ耳をし張ったお方やとは……思わなかったわぁ。
……レアカードならデッキごと持ってはってくれてええから、耳だけでもお願いできへん?」
……レアカードならデッキごと持ってはってくれてええから、耳だけでもお願いできへん?」
「姫様! あれらのカードは、姫様が苦心して集めた物! それをレアハンターごときに……!?」
「ええの。 この耳を掃除できるなら安いモンどす。」
どうやらこの姉ちゃん、本職(?)は耳掃除で、デュエリストは副業らしい。
……だがしかし、耳掃除一回でそこまでするか。
……だがしかし、耳掃除一回でそこまでするか。
「……トガ、直訳を頼む。」
トガにしてみれば、複雑な心境だ。
レアハンターとしては、デュエルもせずにカードを入手できるならばこの上ないが、
恋する乙女(爆笑)としてみれば、些細な夢のひとつとして思い続けて、言い出すこともできなかったことをあっさりとこの女は実現して見せるのだ。
レアハンターとしては、デュエルもせずにカードを入手できるならばこの上ないが、
恋する乙女(爆笑)としてみれば、些細な夢のひとつとして思い続けて、言い出すこともできなかったことをあっさりとこの女は実現して見せるのだ。
だがしかし、部下として『通訳』している以上、ウォンビックの期待を裏切るようなことはできない。
「鵜殿に耳掃除をさせれば、カードはデッキごと渡す……と言っています。」
故意ではないだろうが、この言い方は悪かった。
『誰の耳を』という主語が抜けているし、それにトガの複雑そうな顔も合わされば、
ウォンビックが『鵜殿はトガの耳を掃除を要求しているが、トガは耳掃除されたくない。』と誤認するのも無理のない話だったりするわけで。
『誰の耳を』という主語が抜けているし、それにトガの複雑そうな顔も合わされば、
ウォンビックが『鵜殿はトガの耳を掃除を要求しているが、トガは耳掃除されたくない。』と誤認するのも無理のない話だったりするわけで。
「……トガ、正直に言え。」
「……え?」
「お前は、耳掃除させたくないのか?)」
だから、なぜお前らは、5W1Hを忘れるのか、と。
「嫌です……これがまだ、ブラックマイン様の孤児院の皆さんににならば構いません、ですが、あの鵜殿にやらせたくありません。」
これもまた、勘違いを含む表現である。
トガはウォンビックの経営する孤児院にかなり出入りしているので、仲の良い人間も多い。
つまり、トガ自身は『ウォンビックの家族である孤児院の人間になら耳掃除はやらせてもいいが、鵜殿にやらせるのは嫌だ』という意味で言っているが、
ウォンビックには、『仲の良い孤児院の人間になら私(トガ)の耳掃除をやらせてもいいが、あの鵜殿にやらせるのは嫌だ』と誤って伝わってしまった。
トガはウォンビックの経営する孤児院にかなり出入りしているので、仲の良い人間も多い。
つまり、トガ自身は『ウォンビックの家族である孤児院の人間になら耳掃除はやらせてもいいが、鵜殿にやらせるのは嫌だ』という意味で言っているが、
ウォンビックには、『仲の良い孤児院の人間になら私(トガ)の耳掃除をやらせてもいいが、あの鵜殿にやらせるのは嫌だ』と誤って伝わってしまった。
そして、ウォンビックは、部下に苦行を強要してまで簡単に任務を遂行しようとする人間でない。
「……トガ、鵜殿の要求を断り、当初の予定通り、〔サイクロン・ブレイク〕を賭けたデュエルを要請しろ。」
「い、良いんですか!? 耳掃除させればリスクもなくカードを回収できるんですよ!?」
「構わん。」
トガ、涙目。
そして恋する乙女は目を拭き、ビシィっと鵜殿たちを指差した。
そして恋する乙女は目を拭き、ビシィっと鵜殿たちを指差した。
「この××××の鵜殿ッ! あんたなんかに掃除させる耳はないわ!
それよりも、九大レア〔サイクロン・ブレイク〕のコピーカードと、あんたの〔第一時刻守り シネ〕を賭けて、 このブラックマイン様とデュエルしなさい!」
それよりも、九大レア〔サイクロン・ブレイク〕のコピーカードと、あんたの〔第一時刻守り シネ〕を賭けて、 このブラックマイン様とデュエルしなさい!」
トガの言葉に、今にも殴りかかりそうなほどに怒気を膨らませる鵜殿の取り巻きたち。
……そして、ひとりの側近っぽい男が、その怒気に身を任せて本当に殴りかかったりした。
……そして、ひとりの側近っぽい男が、その怒気に身を任せて本当に殴りかかったりした。
「レアハンターごときがァァッ! 一度ならず二度までも姫様の御耳を汚すなんぞとぉおおおおお!」
取り巻きの一人が拳を振り上げ、トガへ突進する。
が、走り方からして格闘技に関して素人なのは一目瞭然、ウォンビックもトガも慌てない。
――しかし、取り巻きはウォンビックやトガの攻撃を受ける前に倒れ伏すこととなった、自身が姫と呼び崇拝する鵜殿の投げた耳かき棒を耳に突き刺されて。
が、走り方からして格闘技に関して素人なのは一目瞭然、ウォンビックもトガも慌てない。
――しかし、取り巻きはウォンビックやトガの攻撃を受ける前に倒れ伏すこととなった、自身が姫と呼び崇拝する鵜殿の投げた耳かき棒を耳に突き刺されて。
「がっ痛ゥウウ! 姫様あああああ! 抜いて! 抜いてくださいィイイイ! 痛ァおをヲるぞぉぉっっッ」
男は痛みに身体を振りながら突き刺さった耳かき棒を抜こうとするが、
耳かきは上部のタンポポのワタゲに似た部分(梵天というらしい)まで深々と潜り込んでいる。
耳かきは上部のタンポポのワタゲに似た部分(梵天というらしい)まで深々と潜り込んでいる。
「タザキはん? このお人方は私のお客様どすえ? いきなり大声出して、無礼でっしゃろ?」
表情に起伏はなく、自分を崇めていた男を自分で痛めつけておきながら、ただ静かに諭すように言う。
「申し訳ありませんッ! 姫……様ッ!」
「――分かれば、よろしおすえ♪」
鵜殿は刺さった耳かき棒の梵天の糸の一本を指でつまみ、まるでティッシュボックスからティッシュを抜き出すようにあっさりと引っ張り出してみせた。
――驚くべきことに、その耳かき棒は通常(おおよそ15センチほど)の長さがあるにもかかわらず、男の血なんて一滴も付いていない。
……人間の内耳はそこまで長くはないので、どこかを傷付けなければこんな物は入るわけもないのだが、男の耳も抜いた今はもう支障はないらしい。
――驚くべきことに、その耳かき棒は通常(おおよそ15センチほど)の長さがあるにもかかわらず、男の血なんて一滴も付いていない。
……人間の内耳はそこまで長くはないので、どこかを傷付けなければこんな物は入るわけもないのだが、男の耳も抜いた今はもう支障はないらしい。
「さて――デュエルはお断りどす。
〔サイクロン・ブレイク〕なんてカード、ロック使いの私には用のないカードどす。
賭けデュエルで賭けて欲しいのはブラックマインはんの耳だけですわ。」
〔サイクロン・ブレイク〕なんてカード、ロック使いの私には用のないカードどす。
賭けデュエルで賭けて欲しいのはブラックマインはんの耳だけですわ。」
「……トガ、鵜殿はなんと言ってる?」
「〔サイクロン・ブレイク〕はいらないから、ブラックマイン様の耳を賭けろ、と。」
この当たり前のトガの言葉に、ウォンビックは目を丸くした。
ウォンビックは、鵜殿が耳かきしたいのはトガだと思っているので、そこにきてなぜ自分の耳を要求されているのかが分からない。
ウォンビックは、鵜殿が耳かきしたいのはトガだと思っているので、そこにきてなぜ自分の耳を要求されているのかが分からない。
「……………俺の耳でいいならば、賭けるしかあるまい。」
「え、賭けちゃうんですか!?」
なぜトガがショックを受けるかすら、ウォンビックは分かっていない。
「何かまずいのか?」
「問題はありませんけど、でも……ただ私が、嫌なだけです。」
精神の未熟さか、今までゴキゲンだっただけに、トガのテンションは一気に落ちたが、
ウォンビックにすれば、どうしてい機嫌が悪くなったかすら分からず、とりあえず自分の意見を述べることにした。
ウォンビックにすれば、どうしてい機嫌が悪くなったかすら分からず、とりあえず自分の意見を述べることにした。
「……お互いに欲しい物を賭けるからこそ決闘の意味がある。
トガ、俺の耳と、鵜殿の〔第一時刻守り シネ〕を賭けてデュエルするように交渉してくれ。
それに、俺は何を賭けていようとも負けはしない。 必ず勝利する。」
トガ、俺の耳と、鵜殿の〔第一時刻守り シネ〕を賭けてデュエルするように交渉してくれ。
それに、俺は何を賭けていようとも負けはしない。 必ず勝利する。」
――ブラックマイン様が鵜殿なんかに負ける訳がないじゃないか。――
そう考え、トガのテンションはまたもや急上昇し、再び鵜殿を指差し、高らかに宣言する。
そう考え、トガのテンションはまたもや急上昇し、再び鵜殿を指差し、高らかに宣言する。
「わかったわ! こっちのアンティはブラックマイン様の耳! そっちのアンティは……時刻守りシリーズ12枚全て! 不満はないわね!」
「ええ、よろしおすえ!」
正念党にの指令にあるのは〔第一時刻守り シネ〕の奪取のみだが、今ウォンビックは『交渉をしてくれ』と言った。
交渉とは、可能な限り良好な条件を相手に付けろという意味であり、トガは鵜殿の性格から12枚でも差し出すと判断して実行し、的中させたわけだ。
交渉とは、可能な限り良好な条件を相手に付けろという意味であり、トガは鵜殿の性格から12枚でも差し出すと判断して実行し、的中させたわけだ。
「ブラックマイン様! 交渉成功です! これからブラックマイン様の耳と時刻守りシリーズ12枚を賭けてデュエルです!」
「……12枚全てかっ!?……日本のカップヤキソバの湯きりのように見事だ。 トガ。」
「は…はい! ありがとうございます!」
トガ、有頂天。
「それでは………タザキはん? 車からあの『特製デッキ』を持ってきておまへんか?」
「っは……例のデッキとは、あの?」
「ええ、そうどす。 早く、お願いしますえ。」
「は……はいィイイイッッ!」
先ほど耳かきを突き刺された男は、正しく全力で走り出し、戻ってきたのは20秒後だった。
……そのスピードも驚愕に値するが、それ以上に持ってきた物が凄まじかった。
それは、高さにして1メートル50センチほどの超ロングデッキホルダーを据え付けたデュエルディスクだった。
……そのスピードも驚愕に値するが、それ以上に持ってきた物が凄まじかった。
それは、高さにして1メートル50センチほどの超ロングデッキホルダーを据え付けたデュエルディスクだった。
「……!?」
「ブラックマイン様のデッキより……枚数が多い!?」
「ブラックマインはん? あんさんの顔や耳は今始めて見たんやけど……戦術は情報サイトのマウスコミューンで見させてもらいましたわ。
戦術は防御一辺倒、攻撃するでもなく、特殊勝利をねらうでもナシに、ただ相手がドローしていって、35ターンでデッキ切れを起こすまで待つ……、
痺れましたわ。 ロック使いとして……あんさんがデッキ枚数150枚って聞いたから、その10倍の1500枚入りのデッキを作っちゃいましたわ。」
戦術は防御一辺倒、攻撃するでもなく、特殊勝利をねらうでもナシに、ただ相手がドローしていって、35ターンでデッキ切れを起こすまで待つ……、
痺れましたわ。 ロック使いとして……あんさんがデッキ枚数150枚って聞いたから、その10倍の1500枚入りのデッキを作っちゃいましたわ。」
鵜殿の言うとおり、ウォンビックの戦術はニードルワームなどのデッキ破壊パーツすらなく、
ただ相手がドローフェイズでカードを引いていき、最終的にそのままデッキが切れるまで防御し続ける、というもの。
故に、それを超える枚数のデッキと戦う場合、勝機はない。
ただ相手がドローフェイズでカードを引いていき、最終的にそのままデッキが切れるまで防御し続ける、というもの。
故に、それを超える枚数のデッキと戦う場合、勝機はない。
――だが、まあ、負けても耳かきされるだけ――
それがウォンビックの認識だったが、それが甘かった。
それがウォンビックの認識だったが、それが甘かった。
「ああああんッ! 楽しみどすわぁあああ~~~、ブラックマインはんの耳が、ほんの数十ターン後には私のものになるなんてッ!」
「え……?」
言い方がどうにも気に掛かる。
耳掃除、ではなく、『耳が手に入る』? 少々奇妙な言い回しではないか?
耳掃除、ではなく、『耳が手に入る』? 少々奇妙な言い回しではないか?
「そちらはん、ちゃんと言いいはったよ? 『耳を賭ける』って。
だから、このデュエルに勝ったらブラックマインはんの耳は、ブラックマインはんの物でなくなって、私のものになる、いうことや。」
だから、このデュエルに勝ったらブラックマインはんの耳は、ブラックマインはんの物でなくなって、私のものになる、いうことや。」
「な……そんな!
確かに耳を賭ける、とは言ったけど、
それを『耳掃除させろ』という意味でしょっ!?」
確かに耳を賭ける、とは言ったけど、
それを『耳掃除させろ』という意味でしょっ!?」
「それはそちらさんの勘違いやん、確認しなかったそちらが悪いんでっしゃろ?
耳を千切れ、とは言いまへん、ブラックマインはんの肉体ごと、たち『聖耳法堂連合』に来てもらえばいいだけどす。」
耳を千切れ、とは言いまへん、ブラックマインはんの肉体ごと、たち『聖耳法堂連合』に来てもらえばいいだけどす。」
トガは一瞬で真っ青になった。
自分の責任だ。 自分が任された交渉だったのに不利な条件で受けてしまった!……と。
自分の責任だ。 自分が任された交渉だったのに不利な条件で受けてしまった!……と。
「姫!? あのような者達を『聖耳法堂連合』に加えるというのですか!?」
「ブラックマインはんの耳の素晴らしさは、みんな分かるやろ?
それに……『聖耳法堂連合』に加えるんはブラックマインはんだけ。 あっちの子鼠はんは要らんわ。」
それに……『聖耳法堂連合』に加えるんはブラックマインはんだけ。 あっちの子鼠はんは要らんわ。」
そんな敵方の話を聞きつつ、トガは肩を震わせながら、鵜殿の主張を今度は5W1Hを守り、正確に伝えた。
「……ふむ、こちらの勘違いを誘うか、トガ、こういう交渉も世の中にはあるということだな、覚えておいてくれ。」
「申し訳ありません! 私の! 私の責任です! すいません! 本当にすいませんッ!」
自分の膝と胸が見えるほどに頭を下げ、何度も謝るトガ。
そして、それを見て自分達の姫の交渉成功と、敵方の交渉役の無様な姿を嘲蹴るように笑っているのは、さっきまで行列を作っていた聖耳法堂連合の人間たち。
そして、それを見て自分達の姫の交渉成功と、敵方の交渉役の無様な姿を嘲蹴るように笑っているのは、さっきまで行列を作っていた聖耳法堂連合の人間たち。
自分が笑われているだけでも屈辱だというのに、その嘲笑には上司であるウォンビックに対する侮辱も含まれていると思い、トガは既に頭を上げられないほどに泣いていた。
「……トガ、これは確かにお前の責任だがな、同時に手柄でもある。
お前は最初は断っていた相手とのデュエルをできようにし、しっかりと12時刻守りをアンティにするよう交渉した。
……相手のデッキ枚数が多いから時間こそ掛かるが、デュエルが終われば、俺たちは12枚のカードを持って帰れる。」
お前は最初は断っていた相手とのデュエルをできようにし、しっかりと12時刻守りをアンティにするよう交渉した。
……相手のデッキ枚数が多いから時間こそ掛かるが、デュエルが終われば、俺たちは12枚のカードを持って帰れる。」
「でも、鵜殿のほうがデッキ枚数が……!」
「俺は必ず勝利する。 さっき、そう言ったはずだが?」
涙が止まった。
「もし、ギャラリーの反応を気にしているならば無駄なことだ。」
例えるなら、こいつらは網戸の向こうの蚊を潰そうとする人間のように無力で、何もできない。」
例えるなら、こいつらは網戸の向こうの蚊を潰そうとする人間のように無力で、何もできない。」
だから、それなら『あいつらは網戸の向こうの蚊のように何もできない』でいいじゃん、なぜあえて自分達を蚊に例えるんだ?
「お前の『××××』や『×××』のような暴言は、お前が言うからこそ力があるということを忘れるな。
喋るしか能のないヤツの暴言で、いちいちダメージを受ける意味なんぞ、存在しない。」
喋るしか能のないヤツの暴言で、いちいちダメージを受ける意味なんぞ、存在しない。」
英語というのは、分からない人間には全く理解できないが、
ウォンビックのようにゆったりと喋ったものを聞き取るぐらいのことはできる日本人はかなり多く、この言葉を理解して黙る人間は数多い。
ウォンビックのようにゆったりと喋ったものを聞き取るぐらいのことはできる日本人はかなり多く、この言葉を理解して黙る人間は数多い。
「それでは、ウォンビックはん?」
両者、尋常じゃない大きさのデュエルディスクを構え、万国共通のあの言葉を言い放つ!
『デュエル!』
……まあ、この二人のデュエルを1ターンごとに描写したんじゃあ時間掛かるから、結果しか書かないと思うがね。
(作者視点)
部屋の主が腕立て伏せに励む中、その部屋のチャイムが鳴った。
部屋の主が腕立て伏せに励む中、その部屋のチャイムが鳴った。
「はい、510号室のゴールドです。」
ホテルでも部屋の間違いは絶えないわけで、苗字や部屋番号は正確に伝えるのがお互いのためである。
彼女――シグ・ゴールドのようにデュエルで生計を立てているものは、似たイメージの別デュエリストと間違われて挑戦されたりすることもあるので、その辺は重要である。
彼女――シグ・ゴールドのようにデュエルで生計を立てているものは、似たイメージの別デュエリストと間違われて挑戦されたりすることもあるので、その辺は重要である。
「シグサーン、開けてくださーい、あなたのプリティーブラザーのニックデース。」
インターフォンから聞こえてくる声は、自称するようにシグ・ゴールドの弟、ニック・ゴールドに間違いなかった。
「な、ニック!?
あんた、日本でなにしてるのよ!?」
あんた、日本でなにしてるのよ!?」
「取材レジャーデス、とにかく明けてくださーい。 コンタクトはそれからデース。」
シグは手早く玄関まで走り、チェーンを外し、ドアを開いた。
――だが、在るべきはずの弟の巨体は、シグの視界には入らなかった。
――だが、在るべきはずの弟の巨体は、シグの視界には入らなかった。
ドッ!
抉るような衝撃が、下方からシグの首へ向けて真っ直ぐに放たれた。
「がっ……!?」
「シグ・ゴールド様、突然の無礼をお許し下さい。 私は制々正念党のレアハンターです、
貴女様の持つ〔畏怖を纏いし異父 テュポーン〕を頂くために参上しました。」
貴女様の持つ〔畏怖を纏いし異父 テュポーン〕を頂くために参上しました。」
首を掴まれつつ、シグの視線は目まぐるしく動いて弟の姿を探すが、弟はどこにもいない。
……観察で発見できた物は、右腕一本でシグの全体重を支えているピアスを全身に付けた見覚えのない男が一人だけ。
……観察で発見できた物は、右腕一本でシグの全体重を支えているピアスを全身に付けた見覚えのない男が一人だけ。
黄金色のピアスによって、黒人か白人かすら分からないほどに埋め尽くされた腕、同じく眼球や眉がどこにあるかすら分からない顔面。
――わかるのは、首から伝わるピアスの冷たさのみ。
――わかるのは、首から伝わるピアスの冷たさのみ。
「部屋に入ったら首をお放します。 どうか騒がず、お静かに。」
ショベルカーのような精密さで室内へ侵入し、ドアを閉めたところで、ピアス男はシグから手を離した。
「弟は……どこ?」
「オーウ、ビバボイスモノマネー!……私の特技でして、ただの声帯模写です。」
小説なのが残念なほどの声真似を披露するエビエス。
「シグ・ゴールド、性別:女性、年齢:26歳、出身国:アメリカ、家族構成:母との二人暮し、職業:プロデュエリスト、
備考:世界ランキングの中で上位100の中で20名存在する女性デュエリストの一人、使用デッキは海竜族……間違いありませんね?」
備考:世界ランキングの中で上位100の中で20名存在する女性デュエリストの一人、使用デッキは海竜族……間違いありませんね?」
「……。」
突然の来訪者の、これまた突然な本人確認にシグは状況把握のために黙り込むことにした。
「更に詳しく述べさせていただけるなら……身長:175センチメートル、体重:56.4キログラム、血液型:A型、
握力47.2キログラム、靴のサイズ:24センチメートル、胸囲:72センチメートル……」
握力47.2キログラム、靴のサイズ:24センチメートル、胸囲:72センチメートル……」
次々と本人しか知らないような個人情報を言い当てていくピアス男――、
シグには、ここまで正確に自分の体格を書いた覚えもなく、ただピアス男への不信感として蓄積されていく。
シグには、ここまで正確に自分の体格を書いた覚えもなく、ただピアス男への不信感として蓄積されていく。
「要件は?」
「さきほども申したはずですが。
シグ様の所有するレアカード、〔畏怖を纏いし異父 テュポーン〕を頂きたい、と。」
シグ様の所有するレアカード、〔畏怖を纏いし異父 テュポーン〕を頂きたい、と。」
「そちらの提示するのアンティは?」
「〔サイクロンブレイク〕のコピーカードです。
コピーといえども質は最高、デュエルディスクや大会のセンサーも通過できます。」
コピーといえども質は最高、デュエルディスクや大会のセンサーも通過できます。」
続いて突き付けられた言葉も、驚愕に足るものだった。
世間での常識では、I2社の判定装置を通れるコピーカードは存在しないことになっている。
――が、凄腕と呼ばれるデュエリストがずっと驚いているだけのはずも無く、シグは精神的に立ち直った。
世間での常識では、I2社の判定装置を通れるコピーカードは存在しないことになっている。
――が、凄腕と呼ばれるデュエリストがずっと驚いているだけのはずも無く、シグは精神的に立ち直った。
「弟の名を語るより前にちゃんと用件を言って欲しかったわね。
9大レアの1枚のコピー……良いわ、そのデュエル、受ける。」
9大レアの1枚のコピー……良いわ、そのデュエル、受ける。」
シグはトラベルバックから鼠色に着色されたデュエルディスクを取り出し、腕にセットした。
「それでは……」
「失礼、その前にあなたのデッキをシャッフルさせてください。」
「? 構わないけど……変なことをしたら、どうなるか、わかってるわよね?」
デュエルディスクには、オートでデッキをシャッフルする機能がついている。
だが、このシステムのプログラムを変更すれば、ドロー操作も可能となるので、
ゲーム前の相手デッキのシャッフルは、デュエルディスクを使用するデュエルでのデッキシャッフルは権利がある。
だが、このシステムのプログラムを変更すれば、ドロー操作も可能となるので、
ゲーム前の相手デッキのシャッフルは、デュエルディスクを使用するデュエルでのデッキシャッフルは権利がある。
「では……ふっ!」
にゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅにゅッ。
シャッフルが速い、しかも丁寧だ。
エビエスは40枚のデッキを左右の手に正確に20枚ずつ分けて持ち、そのまま20枚ずつでワンハンドシャッフルを行っている。
「ええ、結構です。 あとはデュエルディスクのシャッフル機能で数回シャッフルしてください。」
「必要ないわ。」
前述したデュエルディスクのイカサマシャッフル機能は、事前に一回でも順番を崩すと改造しても狙い通りの順番にはできないので、
逆にエビエスがデッキの順番にイカサマをしたのを疑えば、デッキシャッフル機能を使うのもマナーとしては問題なかったりする。
逆にエビエスがデッキの順番にイカサマをしたのを疑えば、デッキシャッフル機能を使うのもマナーとしては問題なかったりする。
「そうですか? デッキシャッフルは納得のいくまで行った方がいいと思いますが……少々、老婆心が過ぎましたか。」
「私がシャッフルしたいのは私のデッキじゃあなく、あなたのデッキよ。
あなたほど見事なシャッフルはできないけど、貸してちょうだい?」
あなたほど見事なシャッフルはできないけど、貸してちょうだい?」
「いえ、それはできません。」
ピアス男は、いけしゃあしゃあと言ってみせる。
「? どういうことよ?」
「申し訳ありません、私はデッキを持っていない物で。
今すぐお作りしますので、2分ほど時間をください。」
今すぐお作りしますので、2分ほど時間をください。」
「……マジ?」
2分で作った即席デッキで、アンティ・デュエルを行う――もちろん、正気の沙汰ではない。
「本気です。」
「2分と言ったら2分ね? 1秒でもオーバーしたらそっちの反則負けよ。」
「もちろん不満は御座いません………りゃっ あええっえっえっどで、べだだだだだだ。」
「な、何!?」
「るび、にゃふっ、ぺんどぃるっ、うんふぁあッ」
奇声を上げながら小刻みに震えて30秒経過。
「……ふぅ、失礼しました。」
「あたし、麻薬とかには関わらないことにしてるんだけど?」
「至って正気です、それではデッキを作らせていただきます。」
無言で右掌を握り締め……ガキガキと氷を噛み砕くような音が部屋中に響き渡る。
カーペットにポロポロと金粉が散っていることから、どうやらピアスを握り潰してるらしい。
カーペットにポロポロと金粉が散っていることから、どうやらピアスを握り潰してるらしい。
「うっかりしてました、ピアスを付けていたらデュエルができません…あと何秒ですか?」
「1分と12秒。」
握っていた手を解き、自分のデュエルディスクのデッキスペースに押し当て、
パラパラ漫画をめくるようにシュシュっと紙が摺れる音が――鳴り止み、エビエスが手を退けるとそこにはデッキ40枚が置かれている。
パラパラ漫画をめくるようにシュシュっと紙が摺れる音が――鳴り止み、エビエスが手を退けるとそこにはデッキ40枚が置かれている。
「お待たせしました、デッキ完成です。」
今まで存在していなかった物が、瞬間的にエビエスの手の中に出現した。
常識的に考えれば、手品とか奇術とかそういう分類の現象であり、驚いて見せるのが礼儀なのだろうが、
目の前のピアス男の容姿にインパクトがありすぎて、こんなショボイ手品では驚くこともできない。
常識的に考えれば、手品とか奇術とかそういう分類の現象であり、驚いて見せるのが礼儀なのだろうが、
目の前のピアス男の容姿にインパクトがありすぎて、こんなショボイ手品では驚くこともできない。
「…もういいわね?」
「結構です。」
デュエルディスクがスタンバイモードから、ガチャッっと臨戦態勢となった。
『デュエル!』
「私のターンです(手札6)。 モンスターと伏せカードをそれぞれ1枚ずつセットし、ターン終了です。(手札4・伏せ1)」
「あたしのターン、ドロー!(手札6) 〔過去からの旅人 ネッシー〕を攻撃表示で召喚し、能力を発動するわ。」
シグが出したモンスターは、生きる(?)伝説。
世界でトップクラスに有名な海竜を模したモンスターだった。
世界でトップクラスに有名な海竜を模したモンスターだった。
| 過去からの旅人 ネッシー | 水属性 | 海竜族 | レベル4 | ATK2000 | DEF600 |
| このカードが召喚・特殊召喚された時、相手のデッキを上から3枚をお互いに確認し、元に戻す。 その中にモンスターが存在した場合、このカードのコントローラーはモンスターカードの枚数×800ポイントのダメージを受ける。(オリカ) |
|||||
「このカードには追加効果であなたのデッキを透視する効果があるわ。」
「わかりました。」
言いながらカードを引き、それらをシグに公開するエビエス。
1枚目:無限の力
2枚目:ガーディアン・ケースト
3枚目:サイクロンブレイク
2枚目:ガーディアン・ケースト
3枚目:サイクロンブレイク
その3枚に、シグはいくつかの違和感を抱いた。
まず、それらのカードはインクがところどころ摺れており、シグが今まで見てきた数百枚のコピーカードの中でも群を抜く低技術のコピーカードだ。
さらに、ガーディアン・ケーストのカード……一般にも流通してるレア度も低いカードだが……確かめなくてはならない。
まず、それらのカードはインクがところどころ摺れており、シグが今まで見てきた数百枚のコピーカードの中でも群を抜く低技術のコピーカードだ。
さらに、ガーディアン・ケーストのカード……一般にも流通してるレア度も低いカードだが……確かめなくてはならない。
「私のめくったカードの中に〔ガーディアン・ケースト〕があるので、
シグ様、〔過去からの旅人 ネッシー〕の効果でダメージを受けていただきます。」
シグ様、〔過去からの旅人 ネッシー〕の効果でダメージを受けていただきます。」
「もちろん、受けるわ。」
シグ:LP8000→LP7200
「あたしはカードを2枚伏せて終了よ。(手札3・伏せ2)」
確かめるだけならば簡単だ、この伏せカードを使えばいいだけだ。
シグは、そう思いながら攻撃もせずに、ターンを終了した。
シグは、そう思いながら攻撃もせずに、ターンを終了した。
「私のターンです、ドロー。(手札5) メインフェイズへ……」
「ちょっと待ってくれる? メインフェイズに入る前に伏せカードの 〔マインドクラッシュ〕で、〔無限の力〕を指定するわ。」
| マインドクラッシュ | 通常罠 | ||
| カード名を1つ宣言する。 相手の手札を確認し宣言したカードを持っていた場合、そのカードを全て墓地に捨てる。 持っていなかった場合、自分はランダムに手札を1枚捨てる 。 |
|||
デッキを確認し、ピンポイントで手札除去……なるほど、これが彼女の戦法か。
「当然、私の手札に〔無限の力〕は存在していますが、
2枚以上の〔無限の力〕を持っている可能性があるので、〔マインド・クラッシュ〕の効果で手札を公開します。」
2枚以上の〔無限の力〕を持っている可能性があるので、〔マインド・クラッシュ〕の効果で手札を公開します。」
「ええ、もちろん。」
シグにとって、無限の力は決して緊急に除去しなければならないカードではなかった。
それでもマインド・クラッシュを使ったのは、この副次的な相手の手札を見る処理のためだった。
先ほど、ネッシーの効果でデッキトップを覗いた時の、あの違和感を確かめる為に……。
それでもマインド・クラッシュを使ったのは、この副次的な相手の手札を見る処理のためだった。
先ほど、ネッシーの効果でデッキトップを覗いた時の、あの違和感を確かめる為に……。
「それでは、どうぞ。」
エビエス・手札:ウジャト眼を持つ男、魔力転送、徴兵令、ドリルロイド、無限の力
無限の力:手札→墓地へ。
「……あんた、あたしのデッキに何をしたのよ!?」
思惑通りに無限の力を排斥しながらも、シグは自分の推測が的中したことを知り、憤った。
「申し訳ありませんが、私にはなんのことだか皆目見当がつきません?」
「誤魔化さないで! 〔無限の力〕こそ違うけど、他のカードは間違い無くあたしのデッキと同じカードじゃない!」
エビエスの持つカードはイラストがところどころ摺れた低クオリティのコピーカードながら、
指摘どおり、エビエスの手札はシグが最強と信じ、デッキとして組み込んだ4枚のカードたちだ。
指摘どおり、エビエスの手札はシグが最強と信じ、デッキとして組み込んだ4枚のカードたちだ。
「……しかも、昨日手に入れてからまだデュエルで使ってない〔魔力転送〕まで……どこでデッキレシピを盗んだのよ!?」
「私に貴女のデッキを知る機会はないと思いますよ? ただの偶然でしょう。」
いけしゃあしゃあと言ってのけるピアス男。
「知らぬ存ぜぬで通すなら、その口にピアスを詰めるわよ…!?」
「――仮に他者のデッキをコピーできるデュエリストが居るとしたら、その人物は最強のデュエリストかもしれませんね。」
「な……にィ?」
否定も肯定もせず、エビエスは他人の話をするように口を開いた。
「1:ライフポイントを0にする
2:デッキがない状態でドローさせる
3:特殊勝利効果
4:無限処理・時間制限・サレンダーなどの判定
このゲームには、以上の4つの勝利方法が存在しますが、どの戦術でも相手と互角。
それに加え、仮にその人物が正念党員ならば、〔無限の力〕や〔サイクロン・ブレイク〕などの強力カードが使える分、優位と言うことですからね。」
2:デッキがない状態でドローさせる
3:特殊勝利効果
4:無限処理・時間制限・サレンダーなどの判定
このゲームには、以上の4つの勝利方法が存在しますが、どの戦術でも相手と互角。
それに加え、仮にその人物が正念党員ならば、〔無限の力〕や〔サイクロン・ブレイク〕などの強力カードが使える分、優位と言うことですからね。」
そこまで聞き、シグの脳裏に他のデュエリストから訊いたある噂話が蘇った。
「まさか……あなたは、あの『四界の王』ッ!?」
「――おや? 私は名乗り忘れていましたか、シグ・ゴールドさん。」
四つの勝利において常に優位に立ち、如何なるデュエリストにも負けない王者。
――故にその名を『四界の王』、ただの都市伝説だと思われているデュエリストのひとりだ。
――故にその名を『四界の王』、ただの都市伝説だと思われているデュエリストのひとりだ。
存在すら否定されていた『伝説のデュエリスト』と、自分は知らなかったとはいえ対峙している……この状況は……!